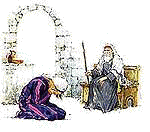![]()
1章1節~20節
1:1 エフライムの山地ラマタイム・ツォフィムに、その名をエルカナというひとりの人がいた。この人はエロハムの子、順次さかのぼって、エリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。 1:2 エルカナには、ふたりの妻があった。ひとりの妻の名はハンナ、もうひとりの妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子どもがあったが、ハンナには子どもがなかった。 1:3 この人は自分の町から毎年シロに上って、万軍の主を礼拝し、いけにえをささげていた。そこにはエリのふたりの息子、主の祭司ホフニとピネハスがいた。 1:4 その日になると、エルカナはいけにえをささげ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えた。 1:5 また、ハンナに、ひとりの人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。 1:6 彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどくいらだたせるようにした。 1:7 毎年、このようにして、彼女が主の宮に上って行くたびに、ペニンナは彼女をいらだたせた。そのためハンナは泣いて、食事をしようともしなかった。 1:8 それで夫エルカナは彼女に言った。「ハンナ。なぜ、泣くのか。どうして、食べないのか。どうして、ふさいでいるのか。あなたにとって、私は十人の息子以上の者ではないのか。」 1:9 シロでの食事が終わって、ハンナは立ち上がった。そのとき、祭司エリは、主の宮の柱のそばの席にすわっていた。 1:10 ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って、激しく泣いた。 1:11 そして誓願を立てて言った。「万軍の主よ。もし、あなたが、はしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主におささげします。そして、その子の頭に、かみそりを当てません。」 1:12 ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口もとを見守っていた。 1:13 ハンナは心のうちで祈っていたので、くちびるが動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。 1:14 エリは彼女に言った。「いつまで酔っているのか。酔いをさましなさい。」 1:15 ハンナは答えて言った。「いいえ、祭司さま。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒も、お酒も飲んではおりません。私は主の前に、私の心を注ぎ出していたのです。 1:16 このはしためを、よこしまな女と思わないでください。私はつのる憂いといらだちのため、今まで祈っていたのです。」 1:17 エリは答えて言った。「安心して行きなさい。イスラエルの神が、あなたの願ったその願いをかなえてくださるように。」 1:18 彼女は、「はしためが、あなたのご好意にあずかることができますように。」と言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔は、もはや以前のようではなかった。 1:19 翌朝早く、彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰って行った。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。 1:20 日が改まって、ハンナはみごもり、男の子を産んだ。そして「私がこの子を主に願ったから。」と言って、その名をサムエルと呼んだ。 |
「心を注ぎ出す祈りの体得」
今回から旧約サムエル記第一の学びに入ります。サムエル記の背景はAC1100~900年頃(約200年近く)の間の出来事で、預言者であり、最後の士師といわれているサムエルの誕生から始まります。
モーセ、ヨシュアの後イスラエルは、士師記21章25節の如く、ギデオン、サムソンをはじめとする士師の時代となり、サムエルは士師の時代から王制時代へ移行する頃の王を立てる役割を果たしています。
サムエルの父エルカナには、ペニンナとハンナの二人の妻がいて、ペニンナには子供がいたが、ハンナにはいなかったのです。当時、一夫多妻が許され社会的、法的に認められてはいたが、そんな家庭がうまくいっていたかどうか…そのような家庭の悲惨な様子が聖書には記され、教えています。
しかし3~5節エルカナ一家は複雑な家庭環境の中でも宗教行事はきちんと守り、特に仮庵の祭り(収穫祭ともいう)を祝うために毎年シロの町に上っていき、神殿に犠牲の供え物をしていました。
この神殿の祭司(3節 エリの息子でホフニ、ピネハスの2人)は神様の定めたルールも守らずいい加減で、堕落していました(そのことは2章12節からに記されており後回で学びます)が、信者としてエルカナ一家は忠実に神殿に捧げ物をしていました。
仮庵の祭りでは、神様に感謝を現すために動物の犠牲を捧げ、その一部を捧げた家族が受けることになっており(4~5節)、エルカナはそのルールにそって動物の肉を家族一人一人に分け与えたのです。
ペニンナには幾人かいるその子供一人一人にも分け与えられるのに、子供のいないハンナは一人分しか受けられず、子供がいないという寂しさをこの時痛感したようです。しかも、毎年毎年その事が繰り返されていました。
日頃夫のエルカナから愛されているハンナを快く思わず、むしろ恨んでいたペニンナにとって、唯一女として優位に立てるときでもあり、ハンナが余計にイライラするような態度をとったのでしょう。
ハンナのイライラは、ペニンナから受ける女性特有の仕打ちだけではなく、6~7節を原語で読むとわかるのですが、エルカナの態度にも原因があったようです。特にハンナという女性は、人に向かわず、手に向かっていった立派な信仰者と美化していわれていますが、最初からそうだったのでしょうか。泣いて食事もとらないで、半分思わせぶりな態度で人に向かっていたように思われます。“このイライラしている私の気持ちもわかってよ”とばかり夫に拗ねてみたり子供がないことの恨みを神様に向けたりしていたようです。
毎年毎年そんなことを繰り返しながら、人に向かっていても何の解決にもならないことを習得していったのではないのでしょうか。人に同情を求めてもかえって理解してもらえないイライラが残ったり、たとえ同じような悩みを持っている人同志でも、環境や諸々の事情の違いから理解し合えないものです。
むしろ人によって解決できる悩み等はたいした悩みではないのかもしれません。憂いや苛立ちを人にぶつけている間は、解決も見えてきません。
人や、自分に対して絶望したとき、神様に向かっていくことを学ぶのです。人が人のことを完全に理解するようなことは不可能です。でも全知全能、私たちの創り主の神様だけは、私たちが自分でも気づかないような深い心の傷や思いを理解してくださいます。私のことを本当に理解してくださるのは神様だけです。
ハンナがもうどうしようもなくなった時に、11節以下の祈り心を注ぎ出しての祈りを体得したのです。誓願をたてて男の子を与えてくださいと。
しかし、心の内で祈ると口元だけが動き、しかもあまりにも長時間祈っているハンナを見て、祭司エリからは酔っているのかといわれるくらいに…心を注ぎ出して祈っていたのです。その祈りのあとは気持ちも晴れ、顔付きまでもすっきりと変わっていたのです。周りの状況は何も変わっていないのに、ハンナ自身が変わっていきました。
年をとれば人間愚痴っぽくなると世間ではいわれますが、信仰の世界ではこれは当てはまらないと思います。ますますこころを注ぎ出しての祈りを体得し実践していってください。
エルカナ一家は家に戻り、やがてハンナは男の子を身ごもりサムエルの誕生となるのです。
質 問
① 今あなたの心にある愚痴や苛立ちは何でしょうか。
② どのようにしてそれを解決していますか。
③ 祈りの後に顔付きが変わっていた「ハンナの祈り」の秘訣は何でしょうか。