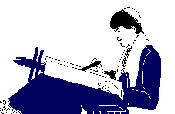![]()
2章11節〜21節
2:11 その後、エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は、祭司エリのもとで主に仕えていた。 2:12 さて、エリの息子たちは、よこしまな者で、主を知らず、 2:13 民にかかわる祭司の定めについてもそうであった。だれかが、いけにえをささげていると、まだ肉を煮ている間に、祭司の子が三又の肉刺しを手にしてやって来て、 2:14 これを、大なべや、かまや、大がまや、なべに突き入れ、肉刺しで取り上げたものをみな、祭司が自分のものとして取っていた。彼らはシロで、そこに来るすべてのイスラエルに、このようにしていた。 2:15 それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやって来て、いけにえをささげる人に、「祭司に、その焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。」と言うので、 2:16 人が、「まず、脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさい。」と言うと、祭司の子は、「いや、いま渡さなければならない。でなければ、私は力ずくで取る。」と言った。 2:17 このように、子たちの罪は、主の前で非常に大きかった。主へのささげ物を、この人たちが侮ったからである。 2:18 サムエルはまだ幼く、亜麻布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。 2:19 サムエルの母は、彼のために小さな上着を作り、毎年、夫とともに、その年のいけにえをささげに上って行くとき、その上着を持って行くのだった。 2:20 エリは、エルカナとその妻を祝福して、「主がお求めになった者の代わりに、主がこの女により、あなたに子どもを賜わりますように。」と言い、彼らは、自分の家に帰るのであった。 2:21 事実、主はハンナを顧み、彼女はみごもって、三人の息子と、ふたりの娘を産んだ。少年サムエルは、主のみもとで成長した。 |
「健全な成長の鍵」 サムエル記 第一 2章11〜21節
「その後、エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は、祭司エリのもとで、亜麻布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。」
サムエル記 4回目の学びです。前回までのところは、母ハンナが中心に登場し、何年も何年も願って、やっと与えられた愛児サムエル、そのひとり子を神に捧げるハンナの様子、神様だけを信頼して、感謝な祈りを捧げるハンナの献身ぶりを学びました。
献身といえば、神学校に行ったり、伝道者になることの代名詞のように使われていることが多いですが、そうではなく、クリスチャンは皆“献身者”です。キリストとともに古い自分は死んで、新しく生まれ変わった者、即ち神に自分を捧げたはずです。なのに、それを受け取っていない人がいたり、クリスチャンは暗いとか、冷たいとか言われて、世の人をつまずかせている場合もあるのです。
主に捧げるということは、爽やかで、喜びであり、自由です。自分で握り締めているものがあるならば、ハンナのように主に捧げ、自由になりましょう。
今回の学び2章11節からは、シロの神殿の生々しい様子が書かれていますが、祭司エリのもとにサムエルを置いて、エルカナ一家は家に帰っていきました。
[12節]
主に仕えていたサムエルとは対照的に、エリの息子達は、祭司でありながら主を知らず…とありますが、彼らは主を恐れることが身についていなかった(知らなかった)のです。
箴言1章7節に「主を恐れることは知識の始まりである。」とあります。神様とはこういう方です、と口では言えるかもしれませんが、実生活の中で神様を先立てての生活が出来ていないのです。それは周囲にもわかることで、わからないのは本人達だけ、また、ここでエリの息子達(2章34節で名前がホフニ、ピネハスと出てきます)とあえて書かれているのは、父であるエリの罪も指摘されているのです。具体的にどういうふうに主を知らなかったかというと、彼らは神の命令、基準、律法を平気で破っていたのです。
[13〜16節]
人々が神様に捧げた物を自分の欲で取り上げていたのです。これはほんの出来心という次元のものではなく、貪欲の罪です。レビ記3章3〜5節、16節に出てくる祭儀律法を破り、力ずくでも奪い取ろうとする実にあさましい様が書かれています。
[17節]
“子達の罪は、主の前に非常に大きかった。”とありますが、ここを読んでいて、神に仕えるもの…牧師という仕事は、絶えず初心に立っていないと、とんでもない方向ずれをしてしまいやすい仕事だと思わされました。もうわかっているからと侮っていると、ずれている自分に気が付かなかったり、純粋な初めの愛も薄れてしまいます。誰でも間違えやすいものです。絶えず絶えず初心に立ち返り、自分を吟味する必要があると思います。
[18節]
ここでは、純粋に神様に仕える可愛いサムエルの様子が窺えます。信仰は、年数や年齢は関係ありません。その時、主に仕える純粋さが問われるのです。
[19節]
ここからハンナの名前が消えて、“サムエルの母”と表現が変わっていることから、文中の中心がサムエルに移ってきたことがわかります。いくら、神様に捧げたからといっても、年に一度会い、手作りの上着を持参し、それを着せる母としての最善の喜びも許されていたのです。
[20節]
エリは、“サムエルが主に仕える者となったのは、主がお求めになったから”と祈っており、その視点にいることがわかります。主のお求めに従ったハンナに子が賜るようにと、エリは祝福の祈りをしています。
[21節]
ハンナには、主の祝福があり、後に5人の子供が与えられ、ハンナの讃歌そのとおりの事実がここに見られます。捧げるということは、一時的には損のように見えますが、後で必ず豊かにされます。握り締めていると、かえって不幸が生じます。ハンナの献身を通して学ばされます。
“サムエルは主のみもとで成長した”
エリの2人の息子と同じ環境に住みながら、主にあったサムエルと、自分達の基準で生活した(主のもとにいなかった)人との差が …信仰の成長の鍵… はここにあります。主のみもとで生き続け、成長させられたいものです。
主を見失ったと思えば、立ち返ればよいのです。
サムエルが彼らを反面教師にして主の御心を知ることを習得していったように、友人、知人の行動を通して、信仰や真理を学び、サムエルの幼子の信仰に立ち返っていきたいものです。