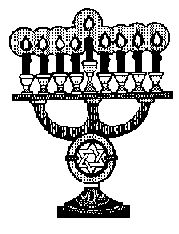![]() 丂丂
丂丂
1復俇乣侾侾愡
1:6 偁傞恖偨偪偼偙偺栚摉偰傪尒幐偄丄傢偒摴偵偦傟偰柍塿側媍榑偵憱傝丄 1:7 棩朄偺嫵巘偱偁傝偨偄偲朷傒側偑傜丄帺暘偺尵偭偰偄傞偙偲傕丄傑偨嫮偔庡挘偟偰偄傞偙偲偵偮偄偰傕棟夝偟偰偄傑偣傫丅 1:8 偟偐偟巹偨偪偼抦偭偰偄傑偡丅棩朄偼丄傕偟師偺偙偲傪抦偭偰偄偰惓偟偔梡偄傞側傜偽丄椙偄傕偺偱偡丅 1:9 偡側傢偪丄棩朄偼丄惓偟偄恖偺偨傔偵偁傞偺偱偼側偔丄棩朄傪柍帇偡傞晄廬弴側幰丄晄宧錳側嵾恖丄墭傜傢偟偄懎暔丄晝傗曣傪嶦偡幰丄恖傪嶦偡幰丄 1:10 晄昳峴側幰丄抝怓傪偡傞幰丄恖傪桿夳偡傞幰丄偆偦傪偮偔幰丄婾徹傪偡傞幰側偳偺偨傔丄傑偨偦偺傎偐寬慡側嫵偊偵偦傓偔帠偺偨傔偵偁傞偺偱偡丅 1:11 廽暉偵枮偪偨恄偺丄塰岝偺暉壒偵傛傟偽丄偙偆側偺偱偁偭偰丄巹偼偦偺暉壒傪備偩偹傜傟偨偺偱偡丅 |
偙偺彂娙偼僄儁僜嫵夛偺杚夛傪戸偝傟偨庒偄僥儌僥偵憲傜傟偰偄傑偡偑丄偦傟偼僥儌僥屄恖偩偗偱偼側偔丄僄儁僜嫵夛偱岞偵撉傫偱梸偟偄偲偄偆婅偄傪傕偭偰丄僷僂儘偼彂偄偰偄傑偡丅慜夞偺偲偙傠偱丄僷僂儘偼僄儁僜嫵夛偺恖偨偪偵俀偮偺帠傪柦偠偰偄傑偡丅
乮侾乯堘偭偨嫵偊傪愢偔偙偲偑側偄傛偆偵丅
丂丂丂棩朄庡媊 恖娫偺婃挘傝偱椙偄峴偄傪偡傞偙偲偱丄媬偄傪摼傛偆偲偡傞嫵偊丅
丂丂丂柍棩朄庡媊 丂恄條傪嫲傟傞偙偲偵壙抣傪抲偐偢丄恄偵廬偆偙偲傪寉傫偠丄宧錳偝傪寉傫偠傞嫵偊丅
乮俀乯暉壒偺崻杮揑偱側偄偙偲偵怱偑扗傢傟傞偙偲偺側偄傛偆偵丅巬梩偺偙偲偵偙丂丂丂偩傢傝丄娞怱側暉壒偑彫偝偔側偭偰偟傑傢側偄傛偆偵丅
丂偦傟傜偺柦椷偺栚揑偼垽偱偡偑丄偙偺垽偼僸儏亅儅僯僘儉偱傕丄恖娫揑側忣偱傕偁傝傑偣傫丅偦傟偼丄惔偄怱偲惓偟偄椙怱偲婾傝偺側偄怣嬄偐傜梌偊傜傟傞垽傪栚昗偲偟偰偄傑偡丅偱偡偐傜丄巹偨偪偺拞偐傜峣傝弌偟偨傝丄恖娫偺椡偱婃挘偭偰垽偟偰偄偔旀傟傞垽偱偼側偔偰丄怣嬄偺寢壥偲偟偰丄恄條偐傜梌偊傜傟傞堦曽揑側垽丄偡側傢偪傾僈儁亅偺垽傪栚昗偲偡傞傛偆偵偲尵傢傟偰偄傑偡丅偟偐偟丆垽偲偄偭偰傕丄恄條偐傜捀偔垽偱偡偐傜丄巹偨偪偼帺暘偵偼垽偑側偄偙偲傪傑偢擣傔側偔偰偼側傝傑偣傫丅
偱偡偐傜丄恄條丄巹偵偼垽偑側偄偐傜壓偝偄偲丄巹偨偪偑恄條偐傜垽傪捀偔偙偲傪栚昗偲偡傞偺偱偡丅僷僂儘偼乬巹偨偪偑栚摉偰偲偡傋偒僑亅儖乭傪偼偭偒傝偲巜偟帵偟傑偟偨丅偙傟偑慜夞傑偱偺偲偙傠偱偡丅
丂崱擔偼俇愡偐傜侾侾愡傑偱傪妛傃傑偡丅偁傞恖偨偪偼丄婾傝偺側偄怣嬄偐傜弌偰偔傞垽傪尒幐偟側偄丄榚摴偵偦傟偰柍塿側媍榑偵憱傝傑偟偨丅偙偙偱巊傢傟偰偄傞乽媍榑乿偼丄乬偔偩傜側偄偍挐傝乭偲栿偝傟傞尵梩偱偡丅栚揑傪尒幐偆偲丄巹偨偪偼昁慠揑偵偙偺偔偩傜側偄偍挐傝傪巒傔傑偡丅
丂儕亅僟亅偺奆條曽偼偙偺栚昗傪偼偭偒傝偝偣偰偄側偄偲丄婥偑晅偄偨傜強懏偟偰偄傞僌儖亅僾偺恖乆偑偔偩傜側偄偍挐傝傗柍塿側偍挐傝偵憱偭偰偄偰丄娞怱偺暉壒偑偍傠偦偐偵偝傟偰偄偨偲偄偆婋尟惈偑壗帪傕偁傞偲巚偄傑偡丅傑偢巹偨偪帺恎偑丄偙偺惔偄怱偲惓偟偄椙怱偲婾傝偺側偄怣嬄偐傜弌偰偔傞垽丄偙傟傪栚昗偲偟偰偄傞偺偩偲偄偆偙偲傪壗帪傕偼偭偒傝偝偣丄偦偺偙偲傪僌儖亅僾偺奆偝傫偵傕揱偊丄偦偙偵壗帪傕徟揰傪摉偰傞傛偆偵堄幆偡傞偙偲偼偲偰傕戝帠側偙偲偱偁傝丄偦傟偑儕亅僟亅偵梌偊傜傟偰偄傞戝愗側巊柦偱偁傝栶妱偱偁傞偲巚偄傑偡丅
丂偦偆偱偁傞偵傕娭傢傜偢丄榚摴偵偦傟柍塿側媍榑偵傆偗傞恖偨偪偼丄旂擏偵傕棩朄偺嫵巘偵側傝偨偄偲婅偭偰偄傞恖偨偪偱偁傝丄偦偺恖偨偪偼丄棩朄偺壗偨傞偐傕丄暉壒偺壗偨傞偐傕暘偐偭偰偄側偄偺偱偡丅偦偺恖偨偪偼棩朄傪梡偄側偑傜丄嬻憐榖偟乮係愡乯偵嫽偠偰偄傞恖偨偪偱偡丅偱偡偐傜丄怣嬄偵彮偟傕寢傃晅偐側偄偺偱偡丅偦偆偄偆棩朄傪傕偰偁偦傫偱偄傞恖偨偪偵懳偟偰丄杮棃棩朄偼椙偄傕偺側偺偩偲僷僂儘偼偼偭偒傝偲岅偭偰偄傑偡乮俉愡乯丅
丂巊搆偺摥偒侾侽復偱丄恄條偼儁僥儘偵柌傪尒偝偣丄傕偼傗惔偄摦暔偲墭傟偨摦暔丄怘傋偰椙偄怘暔偲怘傋偰偼偄偗側偄怘暔偺嵎暿偑柍偔側偭偨偙偲傪帵偟丄傑偨妱楃偵偟偰傕丄傕偆乽僉儕僗僩偺妱楃乿偩偗偱椙偄偲弎傋偰偄傑偡丅僉儕僗僩偺宐傒傪柧妋偵偡傞偨傔偵丄棩朄偼昁梫偱偡丅巹偨偪傕丄棩朄偦偺傕偺偼椙偄傕偺偱偁傞偲丄偼偭偒傝擣傔傞昁梫偑偁傝傑偡丅
丂乽偱偡偐傜丄棩朄偼惞側傞傕偺偱偁傝丄夲傔傕惞偱偁傝丄惓偟偔丄傑偨椙偄傕偺側偺偱偡丅乿乮儘亅儅俈丗侾俀乯
丂乽傕偟帺暘偑偟偨偔側偄偙偲傪偟偰偄傞偲偡傟偽丄棩朄偼椙偄傕偺偱偁傞偙偲傪擣傔偰偄傞傢偗偱偡丅乿乮摨俈丗侾俇乯
丂偱偡偐傜丄巹偨偪偑偟偨偔側偄偙偲傪偟偰偟傑偄擸傓偺偼丄偦傟偼棩朄偑椙偄傕偺偱偁傞偲擣傔偰偄傞偐傜擸傓偺偱偡丅
丂愭傎偳偺妱楃偵偮偄偰偼丄乽僉儕僗僩偵偁偭偰丄偁側偨偑偨偼恖偺庤偵傛傜側偄妱楃傪庴偗傑偟偨丅擏偺偐傜偩傪扙偓幪偰丄亀僉儕僗僩偺妱楃亁傪庴偗偨偺偱偡丅乿
乮僐儘僒僀俀丗侾侾乯偲偁傝傑偡丅偙偙偱偼丄僷僂儘偼乽僉儕僗僩偺妱楃乿傪庴偗偨巹偨偪偼丄傕偼傗乽擏偺妱楃乿傪庴偗傞昁梫偑側偄偲尵偭偰偄傑偡偑丄偦偺僷僂儘偑儘亅儅彂偱偼丄棩朄偼惞側傞傕偺偱偁傝偐偮椙偄傕偺偱偁傞偲尵偭偰偄傑偡丅偦偺偆偊僀僄僗條偼丄棩朄偵偮偄偰儅僞僀俆復偺侾俈愡偐傜俀侽愡偱丄傕偭偲尩偟偄巔惃偱岅偭偰偄傑偡丅偙偺屄強偱丄僀僄僗條偼棩朄傪攋婞偡傞偨傔偵偱偼側偔丄惉廇偡傞偨傔偵棃偨偲尵偭偰偍傜傟傑偡丅恄條偺夲傔傪寉傫偠偰偼側傜側偄偲岅偭偰偄傑偡丅
丂媣墦嫵夛偺弶戙偺杚巘偱偁偭偨扥塇愭惗傕擔梛妛峑偱丄乽廫夲乿傪巕嫙偨偪偵偟偭偐傝嫵偊傞傛偆偵偲尵偭偰偍傜傟偨偦偆偱偡丅側偤偐偲偄偆偲丆棩朄傪偼偭偒傝擣幆偟側偗傟偽嵾偲偄偆偙偲偑杮摉偵偼暘偐傜偢丄嵾偑暘偐傜側偗傟偽丄僉儕僗僩偺廫帤壦偺孳偄偺怺偝偑暘偐傝傑偣傫丅
棩朄偺慜偱偼丄巹偨偪偼帺暘偺嵾傪抦傞偽偐傝偱偁傞偲儘儅彂3復俀侽愡偱弎傋傜傟偰偄傑偡丅傑偨丄僈儔僥儎彂俁復俀係愡偱偼丄棩朄偼巹偨偪偑僉儕僗僩偺尦傊偄偔偨傔偺梴堢學傝偱偁傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅棩朄傪抦傞偙偲偵傛傝丄巹偨偪偼帺暘偺嵾傪抦傝丄帺暘偺椡偱偼媬傢傟傞偙偲偑弌棃偢丄偦偺偨傔僉儕僗僩偺傕偲傊摝偘崬傑側偗傟偽媬傢傟摼側偄嵾恖偱偁傞偲抦傜偝傟傞偺偱偡丅偙偺傛偆偵丄僉儕僗僩偺偲偙傠偵摫偔偨傔偺梴堢學傝偲偟偰棩朄偑偁傞偺偩偲尵傢傟偰偄傑偡丅
丂偟偨偑偭偰丄棩朄偑傏傗偗偰棃傑偡偲丄昁偢暉壒傕傏傗偗偰偒傑偡偟丄怣嬄傕傏傗偗偰偒傑偡丅偡傋偰偑傏傗偗偨傕偺偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偱偡偐傜丄棩朄偑椙偄傕偺偱偁傝丄巹偨偪偑傑偢庴偗傞傋偒傕偺偱偁傞偲偄偆偲偙傠偵棫偨側偄偲丄偡傋偰偑傏傗偗偰偟傑偆偺偱偡丅暉壒偺宐傒傪庴偗偰偄偔偆偪丄巹偨偪偼偲傕偡傟偽丄壗帪偟偐柍棩朄偵娮傝堈偄婋尟惈偑愨偊偢偁傝傑偡丅偱偡偐傜丄棩朄偼惓偟偄恖偺偨傔偵偁傞偺偱偼側偔偰丄棩朄傪柍帇偡傞晄廬弴側恖丄晄宧錳側恖丄墭傜偟偄懎暔丄晝傗曣傪嶦偡幰摍傪丄崘敪偡傞偨傔偵偁傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅偡側傢偪丄棩朄偼巹偨偪偵堘斀傪帵偡傕偺側偺偱丄棩朄柍偟偵偼巹偨偪偼堘斀偟偰偄偰傕婥偑晅偒傑偣傫丅棩朄偱嬛偠傜傟偰偄傞偐傜丄帺暘偑傗偭偰偄傞偙偲偼埆偄偙偲偩偲暘偐傞偺偱偡丅
丂儘亅儅彂俈復俈愡偱偼丄棩朄偱乽傓偝傏偭偰偼側傜側偄乿偲尵傢傟側偗傟偽丄傓偝傏傝偑嵾偩偲巹偨偪偼暘偐傝傑偣傫丅恄條偺婎弨偵徠傜偝傟偨帪偵丄巹偨偪偼傓偝傏傝偑嵾偩偲抦傜偝傟傞偺偱偡丅摿偵丄嘥僥儌僥侾復俋愡乣侾侽愡偱偼丄傓偝傏傞側偲偄偆傛偆側巹偨偪偺撪柺偺嵾偱偼側偔偰丄恖偺奜柺偵尰傟偨嬶懱揑側嵾傪巜揈偟偰偄傑偡丅偙偙偱偼僷僂儘偼棩朄傪寉傫偠偨傝丄恄條傪偍偦傟側偄恖偨偪傪丄摿偵堄幆偟偰偄傞傛偆偵巚偄傑偡丅側偤側傜丄僄儁僜偺挰偼堎朚恖幮夛偱偡偐傜丄儐僟儎恖幮夛偵斾傋傟偽丄偦偺摴摽姶傕椣棟姶傕旕忢偵掅偐偭偨偲巚傢傟傑偡丅偙偙偱尵傢傟偰偄傞傛偆側偙偲偼丄僄儁僜偺挰偱偼丄擔忢拑斞帠偵峴傢傟偰偄偨偲峫偊傜傟傑偡偺偱丄堩扙偵姷傟偭偙偵側偭偰偄偨偐傕偟傟傑偣傫丅嫵夛傕彮側偐傜偢丄偙偺傛偆側塭嬁傪庴偗偰偄偨偺偐傕抦傟傑偣傫丅
丂棩朄偼丄嵳媀棩朄偲摴摽棩朄偺俀偮偵戝暿偝傟傑偡丅
丂乽嵳媀棩朄乿偼丄媇惖偺摦暔側偳傪曺偘偰媀幃傪峴偆嵺偺偙偲傪掕傔偨棩朄偱偡丅
丂乽摴摽棩朄乿偼丄偄傢備傞椣棟揑側棩朄偱偡丅
丂偱偡偐傜丄嵳媀棩朄偼丄僉儕僗僩偑偡偱偵廫帤壦偵偐偐偭偰丄巹偨偪偺偨傔偵慡從偺巕梤偵側偭偰壓偝傝丄巹偨偪偼壗帪偱傕壗張偱偱傕丄僉儕僗僩傪捠偟偰恄條傪楃攓弌棃傞宐傒偵梐偐偭偰偄傑偡偺偱丄嵳媀棩朄偼傕偼傗昁梫側偔側傝傑偟偨丅
丂偟偐偟丄摴摽棩朄偼丄恄條偺婎弨傪偦偺傑傑尰偡傕偺偱偡偟丄偦偺摴偵曕傫偱偄偔偙偲偑恖娫偵偲偭偰岾偣側摴偱偁傝丄恖娫摨巙偺柍梡側徴撍傪杊偖曽朄偲偟偰恄條偺抦宐偑尰偝傟偰偄傞偲巚偄傑偡丅偱偡偐傜丄摴摽棩朄偼丄尰嵼傕桳岠偱偁傞偲偄偊傑偡偑丄怴栺偵惗偒傞巹偨偪偼丄乽儌亅僙偺棩朄乿偵巟攝偝傟偰偄傞偺偱偼側偔乽僉儕僗僩偺棩朄乿偵巟攝偝傟偰偄傞偺偱偡丅
丂乽屳偄偺廳壸傪晧偄崌偄丄偦偺傛偆偵偟偰僉儕僗僩偺棩朄傪慡偆偟側偝偄乿乮僈儔僥儎俇丗俀乯丅偱偡偐傜崱擔偺巹偨偪偼乽儌亅僙偺棩朄乿偺傕偲偵偁傞偺偱偼側偔偰丄乽僉儕僗僩偺棩朄乿偺傕偲偵偁傞偺偱偡丅乽僉儕僗僩偺棩朄乿偲偼丄乬僀僄僗條偱偁偭偨傜偳偆偡傞偱偁傠偆偐丄僀僄僗條偼丄巹偑丄偙偺偙偲偵懳偟偰丄偳偺傛偆偵偡傞偙偲傪丄婅偭偰偍傜傟傞偩傠偆偐乭(What would Jesus do ?)偲丄愨偊偢巚偄弰傜偡偙偲偱偁傝傑偡丅偟偐偟丄偦傟傪抦傞偨傔偵偼丄恄條偺婎弨偼偳偺傛偆側傕偺偐傪抦傞昁梫偑偁傞偺偱丄偳偆偟偰傕乽僉儕僗僩偺棩朄乿偑昁梫偵側傝傑偡丅偁傜備傞応崌偵丄僀僄僗條偩偭偨傜偳偆偡傞偐傪峫偊偰惗偒傞偙偲偑丄怴栺偺帪戙偵惗偒傞巹偨偪偺惗偒曽偱偡丅
丂乽恄偺傒偙偙傠偼壗偐丄偡側傢偪丄壗偑椙偄偙偲偱丄恄偵庴偗擖傟傜傟丄姰慡偱偁傞偺偐傪傢偒傑偊抦傞偨傔偵丄怱偺堦怴偵傛偭偰帺暘傪曄偊側偝偄乿丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮儘儅彂侾俀丗俀乯
丂乽庡偺傒偙偙傠偼壗偱偁傞偐傪丄傛偔屽傝側偝偄乿乮僄儁僜俆丗侾俈乯
丂偟偐偟丆巹偨偪偼惞楈偵懀偝傟側偗傟偽丄壗偑恄偺傒偙偙傠偱偁傞偐暘偐傝傑偣傫丅傑偨丄帺暘偱帺暘傪曄偊傞偺偱偼側偔偰丄恄條偵傛偭偰曄偊傜傟懕偗偰偄偔偺偱偡丅
偱偡偐傜怴栺偵惗偒傞巹偨偪偼丄偙偺僉儕僗僩偵巟攝偝傟偰偄傞幰丄偡側傢偪丄掙抦傟側偄嵾傪丄偨偩僉儕僗僩偺廫帤壦偱尷傝側偔幫偟偰偄偨偩偄偨僉儕僗僩偺垽偵懳偟偰丄乬巹偼偳偆惗偒傞傋偒偐丄壗傪夨偄夵傔傞傋偒偐丄壗傪婌傇傋偒偐傪丄偦偺亀僉儕僗僩偺垽偺棩朄亁偵棫偭偰峫偊側偝偄乭偦傟偑巹偨偪偵丄忢偵媮傔傜傟偰偄傞偙偲偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅
丂暉壒偼寬慡側嫵偊偱偁傞棩朄傪寉傫偠傞傕偺偱偼寛偟偰偁傝傑偣傫丅偦傟偽偐傝偐丄暉壒偼棩朄傪搚戜偲偟偰偄傞傕偺偱偁傝丄傓偟傠僉儕僗僩偵偁偭偰丄棩朄傪惉廇偟偰偄偔傕偺側偺偱偡丅偱偡偐傜暉壒傪怣偠偰偄傞偲尵偄側偑傜丄棩朄偵堘斀偟偰慡偔暯婥側恖偑偄傞側傜偽丄偦傟偼暉壒傪怣偠偰偄傞恖偲偼尵偊側偄偲巚偄傑偡丅傕偪傠傫巹偨偪偼嵾恖偱偡偐傜偟傚偭偪傘偆嵾傪斊偟傑偡偑丄偦偺帪捝傒傪姶偠嬯偟偔側偭偰恄條偵棫偪婣傝丄僉儕僗僩偺廫帤壦偵偡偑傜側偗傟偽傗偭偰偄偗傑偣傫丅
丂偦偟偰丄巹偨偪偺岎傢傝偑棩朄傪偄偄壛尭偵偡傞偲丄偡傋偰偑傏傗偗偰偟傑偄傑偡丅恄條傪偍偦傟傞怱傪幐偄丄恄條偵廬偆偙偲傪寉傫偠傞傛偆偵側偭偨傜丄偦傟偼悽懎庡媊偵娮偭偰偟傑偄傑偡丅
丂愰嫵偺嫵夛偵側傞偨傔偵偼丄怴偟偄恖偨偪偑棃傗偡偄嫵夛偱偁傞偙偲偼偲偰傕戝愗側偙偲偱偁傞偲巚偄傑偡丅摨帪偵丄恄條傪偍偦傟傞怱傗丄嵟廔揑偵偼恄偵廬偆偙偲偑嵟慞側偺偩丄偮傑傝恄條偺庡尃偲偄偆傕偺傪偼偭偒傝偟側偗傟偽丄嫵夛傑偨偼僌儖亅僾偺岎傢傝偼悽懎壔偟偰偟傑偄傑偡丅僷僂儘偼丄巹偼暉壒愰嫵偺偨傔偵偼壗偱傕偡傞丄儐僟儎恖偵偼儐僟儎恖偺傛偆偵丄棩朄傪帩偭偰偄側偄恖偵偼偄側偄恖偺傛偆偵側傞丅偦傟偵傛偭偰堦恖偱傕懡偔偺恖偑僉儕僗僩偺幰偲偝傟傞偙偲傪婌傇偲尵偭偰偄傑偡丅乮嘥僐儕儞僩俋丗俀侽乣俀侾乯
丂偦偺傛偆偵丄嫵夛偑怴偟偄恖偵奐偐傟丄怓乆側恖偨偪偺偨傔偵暉壒傪採帵偟偰偄偔偙偲偼偲偰傕戝愗側偙偲偱偡偑丄偦傟偲摨帪偵偦偙偵廤偭偨恖偨偪偵丄恄條傪嫲傟傞楃攓偺怱偲偄偆傕偺傪丄偟偭偐傝偲怉偊晅偗偰峴偔昁梫偑偁傝傑偡丅偙偺椉柺偑偁偭偰弶傔偰丄乽僶儔儞僗偺庢傟偨嫵夛乿偵側偭偰偄偔偲巚偄傑偡丅
丂偦偺偨傔偵丄乽僂僄儖僇儉乿偲乽儚亅僔僢僾乿偺偙偺椉曽偑戝帠偱偡丅暉壒偼棩朄傪搚戜偲偟偰偄傑偡丅恄偺媊丄恄偺惔偝丄恄偺婎弨偦偆偄偆傕偺偑偼偭偒傝偝傟傞偨傔偵丄棩朄傪捠傜側偄偲偳傫側偵恖偑廤傑偭偰傕丄偦傟傜偺恖偨偪偑僉儕僗僩傪愗幚偵媮傔偰峴偔傛偆偵側傝傑偣傫丅
嫵夛丄僙儖丒僌儖亅僾傪栤傢偢丄偙偺乽僂僄儖僇儉乿偐乽儚亅僔僢僾乿偐偺偄偢傟偐偵曃偭偨傜懯栚偱偡丅偱偡偐傜丄偳傫側庛偝偺恖傕庴偗擖傟傞偲摨帪偵丄偦偆偄偆恖偨偪偑恀偺楃攓幰偵側偭偰偄偔丄傑偨恄傪嫲傟傞傕偺偵側偭偰偄偔丄偦傟偼庢傝傕捈偝偢丄巹偨偪偑偦偺巔惃傪帩偭偰偄側偗傟偽偦偺傛偆偵偼堢偭偰偄偒傑偣傫丅
偦傟偼傑偨丄嫵夛偵棃偰偄傞巕嫙偨偪偵偮偄偰傕偄偊傞偙偲偱丄戝恖偨偪偑杮摉偵恄條傪嫲傟丄恄傪悞傔偰楃攓偟偰偄傞巔傪尒傟偽丄帺慠偵楃攓偡傞怱傪恎偵晅偗偰偄偒傑偡丅
媡偵偦傟傪帩偭偰偄側偗傟偽丄巕嫙偨偪偼恄條傪寉傫偠傞傛偆偵側傞偲巚偄傑偡丅偱偡偐傜丄偙偺乽僂僄儖僇儉乿偲乽儚亅僔僢僾乿偺椉曽傪戝愗偵偟偰偄偔岎傢傝傪婩傝媮傔偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅
摿偵儕亅僟亅偺曽偨偪偼丄偙偺椉曽偑戝帠偱偁傞偙偲傪丄惀旕怱偵巭傔偰捀偒偨偄偲巚偄傑偡丅丂偦偺偨傔偵傕丄奆偝傫偺僌儖亅僾偵偍偄偰丄偙偺乽僂僄儖僇儉乿偲乽儚亅僔僢僾乿偺僶儔儞僗偑偲傟偰偄傞偐偳偆偐丄傑偨丄偦傟偩偗偵尷傜偢丄庛偄強偼壗張偐傪丄奆偝傫偱暘偐偪偁偭偰捀偒偨偄偲巚偄傑偡丅