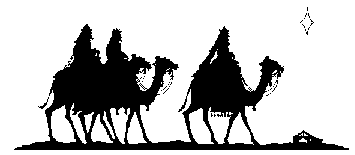![]()
1章18〜20節
1:18 私の子テモテよ。以前あなたについてなされた預言に従って、私はあなたにこの命令をゆだねます。それは、あなたがあの預言によって、信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。 1:19 ある人たちは、正しい良心を捨てて、信仰の破船に会いました。 1:20 その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は、彼らをサタンに引き渡しました。それは、神をけがしてはならないことを、彼らに学ばせるためです。 |
「信仰と正しい良心」
前回はIテモテ1章12〜17節の個所で,エペソ教会を託された若いテモテに,パウロの働きが自分の力によらず,どんなに神様の力に負っていたかを,経験を通して語っていました。
徹底的にキリストに逆らっていたパウロ自身が,「罪人のかしら」と言っていますが,それはかってのパウロだけではなくて,キリストに出会ってからも,ずっと自分は「罪人のかしら」であると言っています。
ですから,こんなパウロに力を与えて下さった神様は素晴らしい方であると,彼はまず主をほめたたえずにはいられないのです。
弱さの場に力強く働いて下さる主,また自分の力ではどうしょうもない罪の力の場に,この上ない憐れみを示して下さる主に,どんな時にも目を向けて行くようにとテモテに勧めています。
もちろん弱さを知ることは大事なことですが,その弱さの場にこそ,キリストの大きな力が働くのだから,どんな時にもこのキリストを見上げて行こうと,まだ若いテモテを暖かく励ましています。
18節からは,最初の主題に帰り,エペソ教会を混乱に陥れていた偽教師等の問題に戻ります。テモテはむろんパウロの本当の子供ではありませんが,信仰にあってはパウロにとってわが子以上で,「私の子テモテよ」と呼び掛けて本題に入って行きます。
「以前あなたについてなされた預言」とは,具体的に何を意味するのか詳しくは分かりませんが,これと同じようなことが使徒の働き13:1〜3に出てきます。
これはパウロとバルナバが,アンテオケ教会から異邦人伝道に遣わされた時の記事ですが,ここに書いてあるように,預言者や教師が集まって祈っていくうち聖霊に示されて,これから送り出される人の特に職務に関して,預言というものが出されることが,当時は習慣的に行われていたようです。
「それですから,私はあなたに注意したいのです。私の按手をもってあなたのうちに与えられた神の腸物を,再び燃えたたせてください」(Ⅱテモテ1:6)。
これは具体的にははっきりしませんが,テモテがエペソ教会に遣わされる時に,預言者や教師等に手を置いて祈られた時に,特に彼のこれからの働きに関して,預言が与えられたことがあったようです。
少なくともエペソ教会の牧会を託す内容が,それには含まれていたのではないかと思われます。
ですから,もう一度あの按手の時を思い起こしなさいと,パウロはテモテに言っています。“あの時は単なる人ではなくて,神様があなたを召したのです。その預言の言葉にしたがい,神様の導きにしたがって,あなたが今エペソ教会を託されている,その初めの召しの時を思い起こして,その上でもう一度,私はこの命令をあなたに委ねます。”とパウロは言っています。この命令というのは,Ⅰテモテ1章3節から5節にある,いくつかの命令のことです。
テモテは,その時の預言,すなわち,今テモテがエペソ教会を牧会しているのは自分から出たことでなくて,神から与えられた使命であるということ,それを一つの武具として,勇敢に戦うように勧められています。
私達もこのテモテのように,預言による方法ではないにしても,神様から託されている使命,役割というものが,必ずあるはずです。あるいは神様から直接でなくて,人を通して私達に与えられた使命かも知れません。でも神様はある時は,人を通して私達に語り掛られる時もあるわけですから,どんな形ちであるにせよ,神様から託されている使命,役割というものが何かしらあるはずです。
それを受けた時の思いに絶えず立ち返って,どういう神様との関わりの中で,奉仕なり,セルのリーダーの役割などを受けとったのか,その初めに受けとった時に帰って,その霊的戦いを続けるようにと,パウロはテモテに勧めています。そうでないと,何か嫌なことや面倒くさいことが起きた時や,あるいはそのために忙しくなってしまった時には,簡単にそれを投げ出すことになりかねません。ですから,今与えられている奉仕や役割が,それが主から与えられたものとして,絶えず確認されていくことは,とても大事なことです。
18節のテモテに与えられた預言は複数形なので,何度も何度も色々な形で,テモテにその預言なり,使命なりを確認させられるような出来事があったのではないかと思います。
ですから,私達は何が主から託されたことであり,何がそうではないのか,はっきりさせる必要があります。私達には限界がありますから,あれもこれも全部するということは決して出来ません。今自分がやっているこの出来事は,それが仮に人から頼まれたことであったにしろ,“これは私が神様から託されたことなのだ”とはっきり受けとることが大切です。どれが本当に主から受けとったことであり,どれが単なる自分の興味本位やっていることか,はっきり優先順位を付けて行かないと疲れ果てて,結局は全部ほうり出してしまう結巣になりかねません。ですから,“これは主から受けとったこと”ということをまずはっきり受けとり,例えそのために何か辛いことがあったり,忙しくなったとしても,これは主から受けとったことだからという思いでかかわることは,とても大切なことです。
信仰の戦いにおいては,初めにそれを受け取った時のことを絶えず思い返して,どういう導きの中でそれを受け取ったかということに立ち帰らされることはとても大切です。
パウロは好んで,「戦い」とか「兵士」という言葉を使っています。それは彼自身が戦いだということを実感していたのだと思います。信仰には絶えず戦いがあります。反対に戦いのない信仰生活は有り得ないと思います。戦いがあるから主により頼むことをさせられますし,そこに主の御業を拝させていただくことも出来ます。戦いというと苦しいイメージがありますが,それを上回る恵みがあります。パウロはここで,特に,牧会上の戦いを意識していたと思います。牧会は本当に戦いだと思います。私が父の晩年に,どうしてこういうことをするのかと,よく疑間をぶつけていたことがありましたが,その時に父が「今戦っているのだ」とよく言いました。その言葉を聞いて「ああ戦っているのか」と納得できました。それはまさに,戦いとしか言いいようのないことだったからです。
私自身も教会に関わらせて頂くようになって,今まで見えなかったことが見えて来る中で,戦いなのだと思わされています。それはサタンとの戦いである部分もありますし,福音を伝えていく上で,ある人達と対決しなければならない場合もあります。一つ一つが本当に戦いだと思いますし,辛いと思わないわけではありませんが,それだからこそ,そこにイエス様が働いておられる事実を見させられるから,何とかそこを乗り越えていけるのだと思います。
その戦いには,私達の中に土台となるものがはきっきりしていないと,困難に遭遇すると簡単に投げ出したくなります。そしてその土台は初め神様から召された時に与えられた,テモテであれば預言であったり,私達であれば御言葉であるかも知れません。いずれにしても牧会の中では本当に祈りなしにはやって行けないし,またお互いの執り成しの祈りなしには,出来ません。それは教会のことだけではなくて,セル・グループにおいても同じことだ思います。ですから他のリーダー達にも分かちあって祈って頂く,こういうリーダー会のような場所がないとやって行けません。
そういう意味において,戦いなのだと意識するのも大事なことですが,それは決して一人で戦う戦いではなく,キリストが共にいて下さる戦いであり,また兄弟姉妹に覚えて頂ける戦いであることも覚えて行きたいと思います。戦いがなければ決してキリストの御業を経験することは出来ません。むしろ戦いの中にある時こそ,私にはどうすることも出来ないけれど,「ああ,主が働いて下さった」と言うことを必ず見させられます。
最近恵みがぼやけているなと思ったら,ひょっとしたら戦いがなくなっているのかも知れません。だからといって無理に自分で戦いを作りだす必要はありませんが。自分でそうしなくても,神様は恵みぼけしないように,私達に戦いを要所,要所に備えていて下さいますから,戦いのないときは休養して,次ぎの戦いに備えていればよいのかも知れません。ですから戦いのある時の方が,恵みがはっきりするというのですから,信仰のことは分からないものです。
18節に「信仰と正しい良心」という言葉があります。信仰と正しい良心とはある意味において一つのことです。神様に対する信仰,もちろんそれは聖書でいう福音に基づく信仰のことです。信仰が保たれているならば,正しい良心があるはずです。「良心」という言葉は難しい言葉ですが,ここであえて言うならば,神様にしたがって行こうという気持です。例え失敗することはあっても,その心はあるはずですから,ここで言う信仰と正しい良心は一つのはずです。ギリシャ語の原文では,この「信仰と正しい良心」は18節には入っておらず,19節で「信仰と正しい良心」を保ちなさい。ある人達はそれを捨ててしまいました,という風になっています。
日本語の聖書では18節と19節に2回出てきますが,原文では1回しか出て来ません。この「信仰と正しい良心」が何故か,パウロがテモテ書で繰り返し使っています。l章5節でも「信仰」という言葉と「良心」という言葉が出てきます。3章9節でも「きよい良心」そして「信仰」が出て来ます。「信仰」と「良心」という言葉を,彼はテモテ書で意識して使っています。神様は信じているけれども,良心は捨てる。そういうことは有り得ません。それはいくら神様,神様と言っても違います。「正しい信仰」には「正しい良心」が伴う筈です。神様は信じているけれども,倫理的な罪にとどまり続けて平気でいたり,あるいは教会を混乱させたり,人々につまずきを与えたりして平気でいられるというならば,それは「信仰」も「正しい良心」も捨てているのと同じだと言わねばなりません。信仰,信仰と言いながら,実は信仰の破舶に遭っているということがあります。だから絶えず「信仰」と同時に,私の中に「正しい良心」が保たれているかを確かめる必要があります。本当に神様に従って,差し出された道を喜んで歩もうという気持を保っているかどうか,絶えず私たちの心の中を吟沫する必要があると思います。どんな神様に対する「信仰」があったとしても,「良心」を捨ててしまったらならば,その信仰は何の意味もなさなくなってしまうと思います。
20節では,具体的にその信仰の破船に遭った人の名前が出て来ます。ヒメナオとアレキサンデルです。二人ともエペソの教会では知られていた人であったようです。ですから,ヒメナオとアレキサンデルと聞いて,ああ,あの人達ねとよくわかる人達です。ヒメナオという名前は,Ⅰテモテ2章17節〜18節に出てきます。ここでは復活がすでに起こったと言って,信仰を覆していると言われています。これはどういう意味かと言いますと,当時の異端と言われたグノーシス主義の影響を受けたものですが,私達が死んだ後よみがえる復活のことを,この人達はキリストを信じた時にもうすでに復活が起きているのだと考えるのです。ですからキリストを信じた時に,もう悪人から清い者にされている。かつっては,誤ったり迷う者であったが,真の知識を得ている今は,もう誤ったり,迷ったりしないとするものです。
ですから聖書でいう第二の復活を信じた時に,もう起きてしまっているのですから,キリストを信じたら,私はもう復活をしているから,終りの日に,肉体の復活というものはないのだと主張する考え方なのです。要するに聖書通りに信じていないという訳です。キリストを信じたらもう悪はなくなっているのだ。そして終りの復活もすでに受けているのだ。だから聖書で言っている,天国で肉体が復活するということはないのだという真理から外れた教えを,癌のように,恐らくヒメナオが広めてしまったのではないかと言われているのです。
アレキサンデルはやはりⅡテモテの4章14節に出てきます。これもヒメナオと共に,100パーセントそうだと言い切れませんが,恐らく彼のことではないかと言われています。彼は使途の働きの19章33節に出て来るアレキサンデルではないかと言われています。もしⅡテモテ4章14節の銅細工人アレキサンデルであれば,何等かの形でパウロの伝える福音を阻止するためにパウロを苦しめたことになります。いずれにしても,ヒメナオとアレキサンデルは信仰の破船に遭いました。
20節「私は,彼らをサタンに引き渡しました」。サタンに引き渡すとはどういうことかと言いますと,大体大きく分けて3つの考え方が初代教会にもあったようです。
(1)病の中に,引き渡すという考え方です。
Iコリント11章30節の聖餐式について言われている所があります。相応しくないままで聖餐を受け,それをいい加減にするならば,そのために病人や死んだ者が大勢いると書かれています。
また使徒の働きの5章1節〜11節,同じく13章11節などに,神様を侮った人たちに対して,パウロたちが命じると息絶えた,目が見えなくなったというように,色々体に支障が起こるそんな形でサタンに引き渡すという表現が,ひょっとしたら使われる場合があるかもしれません。だからといって病気になったから,あの人は何か悪いことをしたのだと言ってはなりません。
(2)彼らの成すがままにまかせるということです。
やりたいだけとにかくやらせて,自分で痛い目に遭ってみればよい。
(3)教会から除名するというやり方です。
テトス書3章10節〜11節に分派を起こす者は,一度戒めてから除名しなさいと言われています。全然戒めないで,いきなり除名するということはないわけです。
しかし,ヒメナオとアレキサンデルは,何度も何度も忠告されたにもかかわらず分派を起こしたり,偽りの福音を説いて,自分に引き寄せようとするようなことを何かしらしていたのだと思います。
この除名ということに関してIコリント5章2節〜5節にも書いてあります。これは不品行についてです。
その2節には「そのような行いをしている者をあなたがたの中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです」,5節では「このような者をサタン引き渡したのです」とパウロは言っています。
パウロがサタンに,彼らを引き渡したと言われていますが,パウロが感情的に怒ってそのような処置をしたのでは決してありません。
それよりもむしろ,たとえ彼らが病気や怪我などの痛い目に遭ったとしても,そこで神様の前に悪いことをしたと悔い改めて立ち返り,少なくとも復活の時,終りの時に救われるならば,と願ってパウロは彼らをサタンに引き渡したのです。
そういう人がいたら教会が困るから除名するというのでなくて,その人がもう一度主に立ち返って欲しい,仮に体が目茶苦茶になったとしても,終りの日に救われるなら,それが幸いなことだから,また是非,そうあって欲しいと切に願ってしたことなのです。
20節「神様を汚してはいけないのだ」ということを学ばせるために,あえてサタンに引き渡したのだと言っています。私達は神様の愛を伝えると同時に,神を汚してはならないということも伝える使命が与えられています。いやそれすら,神様の愛を伝えるためといえるかも知れません。
私達がどのような人生を選んでいくか,最終的には自分で選ぶ自由意思が与えられています。神様を求めて生きることも,神様を汚して信仰を捨てることも最終的には,その人が自分で決めることが出来ます。それを他の人が変えることは決して出来ません。その人その人の選択です。でもそれをどうでもよいと思えないから,その人のために祈り続けるという執り成しの祈りが許されているわけですが,どこまで行っても神に従おうとしない人,神の秩序を乱して痛みも感じない人に対して,それをどこまでも「いいからいいから」と受入れて行くべきだと,聖書は決して言っていません。
ある時にはサタンに引き渡すことさえ,決断しなければならないこともあります。しかしそうであっても,その人が痛い思いをしても,もう一度初めの愛に立ち返って欲しい。サタンの支配から藁にもすがる思いで神にすがり,神を呼び求める者になって欲しいという,もっと後のことを思って敢えてそのような行動をとることがあります。「彼の霊が主の日に救われる」(Iコリント5章5節)ためにです。
小さい子が,部屋の中のストープに触ろうとして,親が幾ら注意しても聞かない時には,少しかわいそうですが,子供が実際に触って熱い思いをすれば,もう二度と触らないということがあります。子供に限らずこれは大人だって同じです。神様第一にするのだといくら言われても,頭では分かっていても,人から言われただけでは身に付きません。ある時には思い切り神様を後ろにして歩んでみて,痛い思いをしなければ分からないことがあります。主を先立てない失敗をする度に気付かされ,主を先立てることが最善だと,主を侮ることの恐ろしさを,体で分かっていくのです。
私達には体で痛い思いをしなければ,学べない真理というものがあります。また人が育って行く時には,大なり小なりそういう痛い思いをしながら,身に付けて行く所があります。だから何が何でもこの人を縛り付けて成長させてやるのだ,そういう風にグループの人達を自分で握りしめる必要はありません。
その人がある時には,自分で痛い思いをしながら学んで行く,そういう真理もあります。その時には陰で祈り続ける,そういうリーダーであって欲しいと思います。
神を汚してはならないことを学ばせるために,ある時はサタンに引き渡すということがあるのを心のどこかに止めておいていただければと思います。
お祈りさせて頂きます。