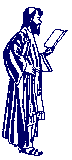![]()
2章8~15節
2:8 ですから、私は願うのです。男は、怒ったり言い争ったりすることなく、どこででもきよい手を上げて祈るようにしなさい。 2:9 同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、はでな髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、 2:10 むしろ、神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行ないを自分の飾りとしなさい。 2:11 女は、静かにして、よく従う心をもって教えを受けなさい。 2:12 私は、女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ、静かにしていなさい。 2:13 アダムが初めに造られ、次にエバが造られたからです。 2:14 また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、あやまちを犯しました。 2:15 しかし、女が慎みをもって、信仰と愛と聖さとを保つなら、子を産むことによって救われます。 |
「神の秩序」
2章1節以降,パウロは教会のリ-ダ-達が何をするにしても大切なのは祈りであることを,いろいろな表現で語ります。また,私たちに繋がっている家族,知人,友人達が,罪からの救い主はイエス・キリストただ一人であるという大事な真理を知り,全ての人が救われることを,神様も私たちも望んでいるので,そのために執り成しの祈りをすべきことが勧められています。さらに,困難な問題に直面している人については,問題の解決だけが目的ではなく,その問題を通して神様の素晴らしさ,救いの恵みの大きさを知ることが出来ることを目標として執り成すことが勧められていました。そして今日学ぶ8節が,祈りの勧めの締めくくりとなる個所です。
【8節】 祈りは男性に限られたものではないのに,ここであえて「男は」とされているのは,公同の礼拝での祈りを意識したためと思われます。「男は清い手を挙げて,祈るようにしなさい」と言われていますが,手を挙げて祈るのは,公の礼拝で男性が祈る祈り方なのです。教会の礼拝を導く責任は男性にあります。それは旧約聖書を見ても,聖書全体の儀式に関する所を見ても,男性に責任が課せられていることがはっきりと書かれています。したがって,礼拝を導く責任があるのですから,言い争ったり,怒ったり,言い争ったりする罪や,倫理的な罪に支配されることなく,むしろ清い手を挙げて祈ることに心を向けなさいと勧められています。
しかし,これは女性の方についてもいえることです。私たちが怒りや言い争いというものに支配されていると,必ず祈りが妨げられてきます。皆さんも心の中が怒りで一杯になっている時に祈れるでしょうか。もちろんその場で,ありのままにその怒りを注ぎ出せばよいのでしょうが,なかなかそのように自由には祈れず,祈りながらも再び怒りに支配されてしまい,祈りが祈りでなくなってしまったいう経験はないでしょうか。
ですから,「怒り」や「言い争い」に支配されるのではなく,祈りによって神様に心を治めて頂く方向に求めて行きなさいと言われているのです。そのような場合,具体的に人と和解することも必要となります。礼拝ということを考える時,礼拝者にとっては具体的な和解が必要であることは,イエス様も山上の垂訓でおしゃっています。マタイの福音書の5章21節から25節で,真の礼拝をささげるために,ただ神様との関係さえ良ければ足りるというのではなく,具体的に兄弟と和解しなさいと言われています。信仰とは具体的なことなので,この和解が出来ていない状態を放置していたら,神様を礼拝するということも妨げられてしまいます。ですから,和解を必死に求めるのはとても大事です。もちろん,いくらこちらが謝っても赦してもらえず,和解できない場合もあるかもしれませんが,でも本当に神様を礼拝し,崇めたいならば具体的な人間関係の闇になっている部分,罪の部分をいい加減にしないように,と言われているのです。
第2テモテ3章3節に「和解しない者」というのが出てきます。終りの日には,人間同士が和解することを大切と思わない者が現れると言われています。和解することはとても大切なことであり,またそれは必ず神様との関係にも現れるものですから,和解が必要とされているのに和解しようともせずに,放置されっ放しになることがないようにと言われているのです。祈りが妨げられないために,真の神礼拝が妨げられないために,怒りや争いから解放されて,本当の礼拝者になれるように,真の祈り手となれるように,そのことをよくよく心にとどめなさいと,礼拝を導く男性達に,特にそのことが言われています。
【9節・10節】 男性にお願いしたように,今度は女性にも同じように勧められています。外見を整えることで競いあったりするのは愚かなことですし,あるいは身なりで男性を誘惑して,お互いの祈りを妨げたりしないようにと戒めております。神を敬う信仰と,そこから溢れ出る行いによって身を飾りなさいと勧められています。表面を飾るのではなく,「信仰美人」になりなさいと言っています。口では神様を敬うと言いながら,態度や身なりでは,私を敬いなさいと言わんばかりの態度では,かえって格好悪いのだと言っています。
【11節・12節】 「女は静かにして……」とありますが,パウロがこのように大変強い口調で言うのには,時代的な背景もあります。パウロが関わっていた教会の中には,預言の賜物を受けている女性がかなりいました。そういう人たちが公同の礼拝で預言を語ることがかなりあったようで,コリント教会にはそのような女性が多くいたことが第1コリント11章5節に記されています。女預言者やそのお付きの婦人たちの多くは,家のことをほったらかしにして,熱狂的に預言活動をしていたようです。
第1テモテ5章13節や第2テモテ3章5節を見ますと,預言活動をしているからといって家のことをほったらかしにして,よその家を転々とし,お節介や噂ばなしに明け暮れていたので,異端的教えを持っている人達や律法主義的人達から,そしられる結果にもなったようです。さらに,テトス2章3節から5節を見ますと,男女を問わず,熱心に教会のことや預言活動をしていると言いながら,地に足が付かない生活をしているために,異端的な教えの人達から,言うことは言っているが,やるべきことは全然やっていないではないかと批判されるようなことが実際に起こっていたようです。こういう背景を踏まえてテモテ2章11節12節でパウロはこのように強く言わざるをえなかったのです。11節と12節で「静かにしていなさい」と2回も繰り返して言われていますが,これは普通の会話を阻止しているのではなく,教えたがりの女性の態度が,目に余るものがあったためのようです。
公の場所で教えることよりもむしろ,11節にあるように「良く従う心を持って,良く教えを受けなさい。教えることよりも,教えを受けて行く方向を求めて行きなさい。従う心を求めなさい。」とパウロは言います。
12節でパウロは「女が教えたり,男を支配したりすることを私は許しません」と言っています。“支配”するという言葉は,指図するとか,指導するというニュアンスがある言葉です。男性は何時の時代でも女性に支配されることを恐れているので,そうはされたくないため怒鳴ったりして,高圧的な態度にでるのかもしれません。それはともかくとして,女性預言者たちが,表面は神様を敬うと言いながら,態度においてや,身なりにおいて,さらに行いにおいても神様より目立とうとしている態度に対しパウロは一喝しています。
【13節】 創造の時の秩序を語ります。最初に男が造られたことには神様の深い御思いがあるので,その創造の秩序を乱してはいけないと彼は言っています。
【14節】 サタンに最初に惑わされたのはエバでした。このエバによってアダムは惑わされました。それだからといってアダムに罪がなかった訳ではありません。
【15節】 聖書の中でも難解とされている箇所です。「女は子供を産むことで救われる」と書かれていますが,これは文字通りに解釈すると,女の人は子供を生まなければ救われないということになりますがそうではありません。そこで,この個所についての解釈のいくつかを紹介します。
① これまで述べられていたように女が慎みを持っていれば子を生む時に安産であるというものです。(これは違うと思います。)
② 子を産むことで救われるということにより,家庭を大切にすることを比喩的に述べていると解釈するもので,これは多くの神学者に受入れられています。
これまでも述べられていたように,家庭をほったらかして家々を歩きまわっていたためにそしりを受けていた女預言者達のような生き方ではなくて,子供を産み育て,夫に仕え,家庭のことを優先する生活をしている婦人たちに神様の祝福があると言っています。
③ “女”をエバ,“救われます”の主語を女(エバ)ととる。アダムとエバを代表とする人間の救いは,特定の“子”(救い主キリスト)の誕生によってもたらされたという解釈。
エバは,蛇,即ちサタンにそそのかされて罪を犯してしまいましたが,それにも関わらず,救い主イエス・キリストの誕生によって救われるのです。
この解釈は,最近,多くの神学者によって支持されています。
どの解釈を取ったらよいか私には分かりませんが,15節でパウロが言おうとしているのは,「女は慎みを持つように」ということであると思います。本当に神様を敬うなら,自ずと慎みが身に付いてくるし,自然と滲み出てくるものです。ここでは,特に男を支配し,上に立とうとする女性たちによって,いささか教会が混乱していることを憂慮したためにこのように強調しているのだと思います。
ですから,パウロが女性を軽く扱っていたのでは決してありません。その証拠として,ガラテヤ書3章26節から28節を見ますと,キリストにあっては男子も女子もないと述べていますし,他の箇所では多数の女性の名前を挙げた上で,それらの女性を自分と対等な同労者と呼んでいることでもそれが分かると思います。
プリスクラとアクラのことを自分の同労者とロマ書16章3節で言っていますし,ユウオデアやスントケ(ピリピ4:2~3)のこともやはり,パウロは大切な同労者であると言っています。これを見ても,パウロは女性を蔑視している訳でも,軽く見ている訳でないことが良く分かると思います。
男女のどちらが上でどちらが劣っているということではなく,神様が秩序の神であるように,私たちも秩序正しくあるようにということを,彼は言っているだけです。これはどこまでも神様の秩序であって,人間の間の上下関係でもないし,もちろん優劣でもありません。この神の秩序に従うことは大切です。ですから,逆にここだけ読んで,女性蔑視であるとか,女性を男性より低く見ていると取るのはこの世の価値観です。これはどこまでも神様の秩序なのです。その神様の秩序を軽んじる時に,必ず混乱が起きるのは明らかです。結局,私たちに求められているのは,私たちが神様に従うか否かです。神様がそう願っておられるならば,それに従っていくのが信仰です。それは女性だけに求められていることではなくて,男性にも神様から求められていることであると思います。
お祈りします。