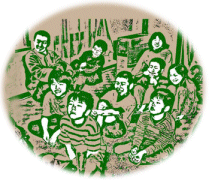![]()
6章1~2節
| 6:1 くびきの下にある奴隷は、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の御名と教えとがそしられないためです。 6:2 信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろ、ますますよく仕えなさい。なぜなら、その良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたは、これらのことを教え、また勧めなさい。 |
テモテ書では教会におけるいろいろな人への接し方について学んでいます。
6章では奴隷についての学びです。
(1)クリスチャンではない主人に仕える奴隷への進め
福音は、神様が[すべての人間は平等である]ということを明確に示している事柄だと思います。何故なら神様の前に立つ時には、皆同じ罪人であり、イエス様の恵みがなければ救われないからです。神様の前では、世の地位は一切無効になってしまいます。ガラテヤ3:26~29にあるようにキリスト・イエスにあるバブテスマを受けたものは、皆同じようにキリストを身に着た者、即ち身分の違いや、男も女も関係なく天国の相続人にされていて、平等であり、キリスト・イエスにあってみんな一つであるということが明らかにされています。
その教え(福音)が当時(ギリシャ世界やローマ世界)の奴隷達に浸透していきました。そしてその主人にも当然福音が伝えられていきます。その過程で、自由と平等を(奴隷たちが主人に対して)必要以上に主張し過ぎる傾向が出てきました。
この当時、奴隷制度というものが厳然とあり、非キリスト教世界では奴隷は家畜同様の存在として見られていました。ゆえにパウロもあえて「くびきの下にある奴隷」という表現をしています。(クリスチャンでない主人から見れば、所詮奴隷は奴隷という見方しかしていないからです)
まだキリストを信じていない主人達への伝道ということから考えると、やみくもにキリストの教えの一部分である自由と平等を主張しすぎることは、あまり賢くない方法だと、あたかも奴隷にとって都合の良い宗教のようにとられてしまいますよと忠告しているのです。正しい福音理解をしてもらうには、主人は主人として尊敬し、行動するように、その方が、かえって神の御名がそしられないためによいのだと、勧めています。
第一コリント9章19~23節ですべてのことは福音のためにしていますとあるように、パウロの頭の中は福音宣教が全てであり、人が一人救われるためには、労を惜しまず必要ならば奴隷にもなると、ここにその覚悟があります。キリストの弟子というならキリストが喜ばれることに専念していくと言っています。
キリストにある自由とは福音のためなら自分を突出せずいつでも相手に合わせることも出来る自由のことです。キリストの恵みを伝えるためには伝える相手と同じところに立つこと…まずイエス様がそれを示して下さり、私達罪人を救うために、この世界にまで下りて来て下さいました。
相手が心を開いてくれなければ、いくら福音を伝えても、その人には、ただうるさいだけになってしまいます。そのためにもまず、主人に尊敬の態度を示していくことだと教えています。
(2)信者である主人に仕えている奴隷への勧めクリスチャン同志だからと馴れ馴れしくならないで、ますますよく仕えなさいと勧めています。私達にもあてはまることですが、知らない人でもクリスチャン同志だとすぐ親しくなれるという反面、少しぐらい大目にみてよとつい甘えが生じたりもします。夫婦の場合もそうです。主人がクリスチャンでない方だと、つまずきを与えないようにといろいろの気遣いをされるでしょうが、信者同志だと何を言っても許されると言う気持ちが困じてわがままになったりもします。当事者同志が許しあって、受け入れあっていても、第三者がそれを見てつまずきを感じないとも限りません。
Ⅰコリント13章(愛の賛歌)5節“愛は礼儀に反することはせず”とあります愛とは親しく馴れ馴れしくべたべたしていることではなく、礼儀に反することはしないと、はっきり言われています。教会の交わりや家族の中で、このことが守られないならば、口先だけの愛の交わりになってしまいます。教会の交わりの中でも、よく人に仕えていくと、その益が私達に還ってくると〔テモテ書6章2節後半で〕いわれています。
奴隷と主人の関係で言われているこの2節ですが、私達、教会の兄弟姉妹の交わりにも当てはまることであり、心して聞き、受けていきたいところです。
質 問
① パウロのように“全てが福音のために”という生き方をしているでしょうか。もし、していないなら、それを妨げている要因はどこにあるのでしょうか。
② 今自分の態度で神の御名と教えがそしられていることはないでしょうか。
③ 主にある兄弟姉妹だからということで、軽んじている関係はないでしょうか。
④ 兄弟姉妹への言葉遣いや態度で、礼儀に反することはないでしょうか。