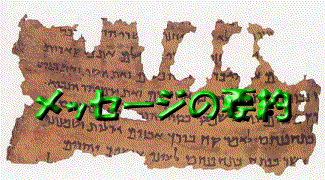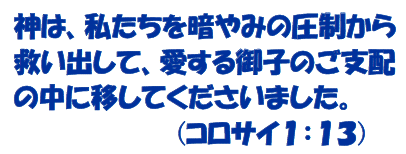12月31日 12月31日 |
礼拝メッセージ要約 主題:「キリストにある交わり」
エペソ人への手紙4:25~32 三浦真信牧師
キリストに出会い、キリストに従いたいと願っている者たちに、パウロは交わりの原則を語ります。「キリストのからだ」なる教会の交わりにおいて、これらのことを大切にしていきましょう。
十戒の後半部分(前半は対神に関わる内容)の対人に関する戒めが、さらにキリストの光を通して積極的な内容となっています。
<25節>
十戒では、第9戒「偽ってはならない」が土台となっています。「偽りを捨てて、隣人に対して真実を語りなさい」と、ただ「偽りを捨てなさい」ではなく、さらに積極的に「真実を語りなさい」とパウロは命じています。その理由は、「私たちは互いにからだの一部分」だからです。同じからだですから、真実を語るのは当然なのです。しかし「互いにからだの一部分」として、相手を尊ぶ思いがあることを前提としています。真実を語るときには、聞く相手が受け取れる時を待つ配慮も、ある時には必要です。「愛をもって真理を語る」(エペソ4:15)ことが求められます。
真実を語る時に、自分の肉の思いをぶつけようとしていないかどうかを吟味する必要があります。自分が砕かれるために真実を語ること、また相手がキリストにあって生かされることを願って真実を語りましょう。自分の自我を押し通そうとしているだけではないか?人を自分の支配下に置こうとしていないか?腹いせにただ自分の思いをぶつけているだけではないか?吟味しましょう。キリストの救いを受けた者たちは、「からだの一部として互いにそれぞれのもの」ということを前提としています。
<26~27節>
十戒の第6戒「殺してはならない」が土台となっています。人と関われば、カチンとくることを言われたり、相手は悪意がなくても勝手に言葉に引っかかってしまったりして、怒りの感情が出てくることが生じます。ここでは、怒ることで「罪を犯す」ことを問題にしています。怒りを温存していることで、罪を犯し、「悪魔に機会を与える」ことが問題です。だから、「日が暮れるまで憤ったままでいてはいけない」のです。できるだけ早く、怒りの感情を処理して、罪を犯さないようにし ましょう。
怒った時に犯す罪は、「殺人の罪」です。兄弟に向かって腹を立てる者、「能無し」と言う者は、人を殺しているのです(マタイ5:21~22)。そして人をさばく者は、神からさばかれるのです(マタイ7:1)。兄弟をさばく時に、喜んでいるのは悪魔だけです。静まって、主により頼みましょう(詩篇4:4~5)。自分の内にある怒りを主に申し上げましょう。「義のいけにえをささげ」(砕かれた心をささげ 詩篇51:17)、主により頼みましょう。主がその怒りを鎮め、主の平安に満たしてくださるまで祈りましょう。怒って罪を犯すときには、誰も幸せになりません。悪魔が手をたたいて喜ぶだけです。一刻も早く、神の平安を求めましょう。
<28節>
十戒の第8戒、「盗んではならない」を土台としています。盗むという行為は、人の権利を損なうことです。正当な方法以外でお金を入手すること、人の役割の領分を犯すこと、悪い噂(うわさ)を流して人の名誉を奪うこと、人の時間を自分の都合によって奪うこと、支払うべきものを支払わないこと、神にささげるべきものをささげないこと(マラキ3:8~10)…など、気がつかないうちに神から人から盗んでいるかもしれません。
ただ「盗んではならない」というだけではなく、むしろ「困っている人に施しをするたに働きなさい」と、積極的に勧められています。「奪うどころか、与えなさい」が、キリストの光を受けた者たちには命じられているのです。滅びに向かっていた者が、キリストの救いという素晴らしい宝をいただいたのだから、人の権利や持ち物を奪うのではなく、むしろ与えていくようにと、どこまでも「キリストから溢れる恵みをいただいている者として」という事実が土台となっています。主イエスも、「受けるよりも与えるほうが幸いである」と言われました(使徒20:35)。神から十分恵みを受けているのだから、人に対しては与えることを求めていくのです。人から受ける人、人から愛される人にならなくてもよいのです。聖書では、「神と人を愛しなさい、与える人になりなさい」と言われています。それは、神から愛され、神の恵みを十分受けていることが前提となっています。人から受けること、人から愛されることを求めている人は、いつまでも満足できません。人の愛は不完全だからです。神の完全な愛を受けて人には要求せず、人を愛する人は、結果として人からも愛されます。神の愛を十分受け取りながら、人に与える者となれるように求めていきましょう。神の恵みによってするのでなければ、与えることで高慢になったり、人に見返りを求めるようになり、かえっておかしくなります。神からただで受けたのですから、見返りを求めず、「なすべきことをしただけです」(ルカ17:10)というしもべの心を忘れないようにしましょう。
<29節>
十戒の第7戒「姦淫(かんいん)してはならない」を土台としています。「悪いことば」は、「ボロボロに腐った言葉、卑猥な言葉、人を壊す言葉、陰口」などの意味があります。「出す」の原語は、「旅をする」という意味の言葉です。ことばを一度出すと、一人歩きをします。ちょっと発した悪い言葉が、大きくなって交わりを破壊していくのです。そのような人を損なう言葉ではなく、「人の徳を養うのに役立つことば」(「人の成長に役立つことば」新改訳2017)を話し、「聞く人に恵みを与え」る言葉を語れるように、互いに主に求めましょう。人を生かし、立ち上がらせ、元気にしていく言葉を、交わりの中で互いに語り合えるように求めましょう。
<30~31節>
聖霊は人格を持っておられます。「無慈悲、憤り、怒り、叫び(怒号)、そしり(ののしり)」などを大事に持っていると、聖霊は悲しまれます。それらを捨てていく方向が、神の聖霊を喜ばせる生き方です。内におられる聖霊が喜んでおられる時に、私たちは喜びに満たされます。逆に、聖霊を悲しませている時に、私たちの心からも喜びが消え去ります。これらが心を支配してしまわないように、たえず聖霊に助けを求めましょう。それらを捨てるには、まず内にそのような肉の思いがあることを正直に認めることがスタートです。信仰生活において、今の自分の状態を正直に主の前に認めることがとても大切です。認めないと、律法学者たちのように、自分の義を言い立てていく生き方になってしまいます。しかし自分のうちにある肉の姿を認めたら、自分の義で立つことはできません。キリストのあわれみにすがり、キリストの義で生きる者とされていくのです。
<32節>
「神がキリストにおいて赦してくださった」、これが私たちの交わりの基本です。キリストによって罪赦された者として、互いに赦し合うのがキリストにある交わりです。「相手が変わったら赦す」というのではなく、「神が私を赦してくださった」という理由で、赦すのです。
この赦しは、人に求めるものではありません。「クリスチャンだから、赦すべきだ、人を愛すべきだ…」と、人にみことばを当てはめていくと、聖書の言葉が人をさばくために用いられて悪魔に機会を与えることになってしまいます。どこまでも、自分自身が神に赦された者として、赦しをゴールに置くことを求めていきましょう。
キリストの十字架の贖いによって、私たちは罪を一方的に赦された者です。神の愛を受けるにはふさわしくないのに、神はキリストを通して私たちを愛してくださいました。この一方的な神の愛、神の赦しが、キリストにある交わりの土台です。このことを大事な主の命令として、キリストにある豊かな交わりをこれからも求めてまいりましょう。
|
 |
 12月24日 12月24日 |
クリスマス礼拝メッセージ要約 主題:「暗やみを打ち破るキリストの栄光」
ルカの福音書2:1~20 三浦真信牧師
イエス・キリストが生まれた時に、パレスチナ一帯はローマ帝国が支配していました。その時のローマ皇帝アウグスト(本名ガイウス・オクタビアヌス)は、ローマが治める全地域で住民登録(人口調査)をするよう勅令(ちょくれい)を出します(1節)。イエスは、人間の歴史の真っただ中にお生まれになりました。この住民登録のために、イエスの父ヨセフと身重の母マリヤは、ヨセフの故郷であるベツレヘムに帰り、そこでイエスを産みます(4節)。皇帝アウグストの勅令(ちょくれい)という歴史的出来事を用いて、神は旧約の預言を成就されました(ミカ5:2)。
ヨセフとマリヤがベツレヘムに帰ると、大勢の人が住民登録のために帰郷していたため、宿はいっぱいで泊まる部屋がなく、飼葉桶(かいばおけ)でマリヤはイエスを出産します。王宮や立派な御殿ではなく、汚い馬小屋のような場所で生まれた救い主だから、「私のような罪に汚れた者はとてもきよい神には近づけない」と思っている人でも、近づくことができるのです。事実、生まれたばかりのイエスに最初に出会う人たちは、羊飼いたちでした。彼らは、この時の人口調査の対象にすらなっていませんでした。それほどに、身分が低く、当時は汚れた職業と人々から見なされて、社会からも距離をとられていました。
旅館街は人であふれている時に、羊飼いたちは「自分たちには関係ない」と疎外感(そがいかん)を感じながら、暗い野原で羊の夜番をしていました。そこに突然主の使いが現れます(8~9節)。暗やみを打ち破るまばゆい光が、辺り一帯を照らしました。そしてその光は、羊飼いたちの心の闇まで照らしていきます。
御使いは、「民全体のためのすばらしい喜びを知らせに」羊飼いたちのもとにきました(10~11節)。人口調査の数にも数えられない羊飼いたちに、民全体に関わる大ニュースが真っ先に届いたのです。「人口調査の対象になっていなくても、この救いはあなたがたが対象ですよ」と言わんばかりに、この素晴らしい救いの知らせが羊飼いたちに伝えられたのです。「布にくるまって飼葉桶(かいばおけ)に寝ておられるみどりご(赤ちゃん)」が、救い主としてのしるしでした(12節)。救い主は、羊飼いたちの近づき難い場所ではなく、生活圏におられるのです。汚れた仕事着のままでもお会いできる、馬小屋のような場所におられるのです。ですから会おうと思えば、いつでもお会いできる救い主です。
この福音が伝えられると、多くの天の軍勢が現れて、御使いたちといっしょに神を賛美します(13~14節)。羊飼いたちは、早速ベツレヘムに行き、飼葉桶(かいばおけ)に寝ている幼子イエスを探し当て、御使いを通して神が言われたことがすべて事実であったことを見て、神をあがめ、神を賛美しながら職場である野原に帰っていきました(15~20節)。
天の軍勢が見下ろしたのは、暗やみが覆(おお)う世界でした(ローマ3:10~18)。目的をもってこの宇宙を造り、人を造られた神を真に求める者もなく、すべての人が迷い出ている世界です。そこで人々は互いに偽りを言い、欺(あざむ)き合い、まむしの毒のような言葉を吐(は)き出し、その口は呪いと苦さで満ちているのです。互いを傷つけ合い、殺し合い、破壊と悲惨だらけの暗やみが世界を覆(おお)っています。本来いるべき造り主から迷い出た人間社会は、そのような現実の中にあって、平和とは程遠い道を進んでいます。神に対する恐れを失った人間社会は、混乱し、すべてが的外れです。人を造られた神との対立関係が、深刻な状況を世界に生み出しています。その破壊と悲惨が渦巻く現実社会に、神の子キリストは生まれたのです。
キリストは、社会の中で疎外されていた人たち、苦しみ弱り果てた人たちの友となり、寄り添ってくださいました。そして罪なき方なのに、当時のユダヤ教指導者たちの反感を買い、重い十字架刑に処せられ殺されます。しかしこれも預言の成就でした。 神からさ迷い出た人間は、自力で神のもとに帰ることができません。旧約時代には、人が罪を犯すたびに動物がいけにとしてささげられていました。キリストは、すべての人の罪の刑罰を身代わりに負って、ただ一度すべての人の罪のいけにえとして十字架で死なれたのです。そして三日目に死からよみがえり、罪の結果である死にも勝利してくださいました。キリストを信じる者は、もはや死に支配されることはありません。キリストを信じるなら、造り主を無視し、神を神とせず、自分の欲や他のものを神のようにしてきたこと、そしてそうせざるを得なかった私たちの内側に生まれる前からある原罪が赦され、罪から解放されるのです。
キリストが、十字架で私たちの罪を負って死なれたことで、私たちは魂の牧者である神の元に帰ることができたのです(Ⅰペテロ2:22~25)。「こんな罪に汚れた私は、神に近づくことなどできない」と思う罪人のためにこそ、キリストは生まれてくださったのです(Ⅰテモテ1:15)。そのような救い主がこの地に来てくださったことを心から感謝いたします。
|
 |
 12月17日 12月17日 |
メッセージ要約 主題:「自分の罪に泣ける幸せ」
ルカの福音書22:54~62 三浦真信牧師
<54節>
イエスは、ゲッセマネで苦しみもだえて祈る中で、十字架の道を神のみこころとして受け取り立ち上がります。その時に、イエスを捕らえに群衆たちが来ます。イエスが捕らえられると、弟子たちはみなイエスを見捨てて逃げ去ってしまいます(マタイ26:56、マルコ14:50)。群衆が近づいてきたときには、ペテロはじめ弟子たちは勇敢にイエスを守ろうとしましたが、イエスが捕らえられて冷静になった時に、恐怖心が出てきて逃げてしまったのでしょう。
それでもペテロは、「主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております」(33節)と言った手前、一度は逃げ去ったものの、イエスから「遠く離れて」ついて行きました。この時のペテロのように、今もイエスから遠く離れてついて行く人たちが大勢います。イエスのそばにいてついていくというよりは、少し離れた所からついていき、都合の良い時はイエスの弟子となり、都合が悪くなると「イエスのことなど知りません」という素振りをするのです。そのようなイエスとの関係、イエスとの距離を保つ中途半端な主イエスとの関係が、逆にどれほどみじめなことかを、ペテロはこの後知ることになります。また今、主イエスとの関係がどうであるのか、すべての人に問いかけられています。
<55~56節>
大祭司の家で、イエスの裁判が始まります(マタイ26:57~68)。イエスから遠く離れてついていったペテロは、イエスの裁判の様子がわかる大祭司の家の中庭に入ります。そこで人々(主に役人の人たち)が火を焚(た)いて座り込んで、裁判の成り行きを見守っていました。ペテロもその中に混じって腰をおろします。すると、たき火の明かりに照らされたペテロをまじまじと見た女中が、「この人も、イエスといっしょにいました」と言います。恐らくペテロは、自分のことを知っている人はそこにいないと思っていたのか、暗がりで顔はわからないと思っていたのでしょう。ペテロは不意を突かれて驚きます。
<57節>
そしてペテロはその女中の言葉を打ち消して「いいえ、私はあの人を知りません」と答えます。大の男が、女性の一言におどおどして嘘(うそ)をついています。数時間前に、イエスを捕らえに来た群衆に向かった時のような勇ましさはなく、ただ人目を気にしてビクビクして自分をかばうだけの弱いペテロでしかありませんでした。
<58~59節>
しばらくして他の男に「あなたも、彼らの仲間だ」と言われ、ペテロは「いや、違います」と2度目にイエスを否定します。そして一時間後に別の男から、「確かにこの人も彼(イエス)といっしょだった。この人もガリラヤ人だから」と言われます。ガリラヤ人とは、ガリラヤ地方出身の人という意味で、ガリラヤ地方独特のなまりでわかりました(マタイ26:73)。見た目だけでなく、言葉のなまりでガリラヤ人であることまで知られたことで、ペテロとしてはただひたすら強く否定する言葉しか見つかりませんでした。「あなたの言うことはわかりません」と三度目にイエスを否定します。マタイ26:74では、「そんな人は知らない」と言って、のろいをかけて誓い始めた…と記されています。
<60~61節>
嘘(うそ)に嘘(うそ)を重ね、3度目にイエスを否定する言葉を言い終えないうちに、鶏が鳴きます。その時に「主イエスが振り向いてペテロを見つめられました」。鶏の鳴き声と、振り返ってペテロを見つめるイエスのまなざしにより、ペテロは我に返ります。イエスが少し前に最後の晩餐の席で、「きょう鶏が鳴くまでに、あなたは三度、わたしを知らないと言います」(34節)と言われたイエスの言葉を、ペテロは思い出しました。
主イエスは、恐らく怒った顔ではなく、優しいまなざしでペテロをご覧になったことでしょう。「ペテロ、本当の自分の姿がわかっただろう?」とおっしゃるようなイエスの視線には、やがて自分の弱さをとことん知った後に立たされていく将来のペテロが見えていたことでしょう。どれほど立派なことを言っても、また「必ずこうします」と宣言しても、完璧に実行できない自分がいます。自分ではできると思っていた、もう少しましな自分だと思っていた、でも実際の自分はそうではなかったと知るときは、このイエスのまなざしを感じるときでもあります。主イエスに、またイエスの言葉に、従いきれないどうしようもない私たちのために、イエス・キリストは十字架の道を進んでいかれるのです。
<62節>
ペテロは、イエスのまなざしと、イエスの言葉を思い出して、外に出て激しく泣きました。3年間師として慕いついていき、生活を共にしてきたイエスを、三度も否定し裏切ってしまった自分のどうしようもなさに、ただただ泣くしかありませんでした。
ペテロには、どうしてもこの経験が必要だったのです。自分自身にとことん破れ果てることが必要でした。そこを通らなければ、ただ自分の熱心、自分の力により頼み、ペテロ臭をプンプン漂(ただよ)わせながら、「俺こそイエスの一番弟子だぞ」と言わんばかりの、鼻持ちならないペテロになっていたでしょう。それ以上に、あの大変な初代教会における様々なかん難の中で、ただキリストにより頼み、自分を明け渡して御霊の導きについていくことはできなかったでしょう。ペテロは、ここで初めて、とことん自分の罪、弱さに泣き崩れ、神様のあわれみ無しには立つことができないペテロになりました。イエスはこの時、「今はとことん自分のみじめさを味わいなさい。今度は私があなたを立ち上がらせるから。ここが、やがてあなたが福音宣教のために遣わされていく原点となるのです」というまなざしでペテロをご覧になったのでしょう。
ペテロは、ここで自分の罪を痛み悲しみ、激しく泣きました。人を恐れて、主イエスを裏切 り見捨てていく自分のどうしようもない弱さを知り、そこからまた主を求めていきます。やがて十字架の死からよみがえられた復活の主イエスに出会い、助け主聖霊を待ち望んで祈り続け、やがてペンテコステの日に聖霊を受けて大胆に主イエスの証し人として遣わされていきます。その時は、もはや自分の力ではない、ペテロの熱心でもない、主の力と導きだけで立たされていくのです。
同じように、イエスを裏切ったユダも、のちにイエスを売り渡したことを後悔します。しかし彼は、自分の弱さを認めて主に泣いていくのではなく、どこまでも自分で自分の罪を解決していこうとして、自ら命を絶ちます。ユダも、自分の罪に幻滅して、主に向かって泣いていくことができたなら、誰よりも大きな赦しと愛を知ることができたでしょう。でも彼は、それをせずに、自分でけりをつけていきました。
イエスは、「悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから」(マタイ5:4)と言われました。悲しみをもって、イエスに向かっていけるなら、主イエスに向かって泣いていけるなら、主イエスは悲しみの真っ只中で慰めを与えてくださいます。
「神はどのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも、自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです」(Ⅱコリント1:4)。苦しみの中で、「神から受ける慰め」を経験した者だけが、また苦しみに中にある人にこの神の慰めを伝えることができます。人からの慰めも助けになりますが、それでも一時的で不完全なものです。しかし神は、私たちがいつどこにあっても、慰めを与えることができます。その慰めは、永遠に続きます。私たちが究極的にできることは、自分自身が体験した神の慰めを人々に伝え、とりなし祈ることです。
どのような痛み苦しみも、主に向かって泣いていけるなら、人は神の慰めを受けて立ち上がらされていきます。「ペテロは外に出て、激しく泣いた」、ここがペテロの信仰の原点です。ここからペテロのミッションは始まっていくのです。キリストの力がペテロを覆(おお)い、キリストの力で、やがてキリストの証し人としてペテロは立たされていきます。私たちも、自分の罪に泣くしかないところで、自分に尽き果てるしかない場所で、キリストに引き上げられ、聖霊に扱われていきます。主の前で自分の罪に泣けることは、幸せなことです。そこに主の慰めがあり、主が立ち上がらせてくださいます。
|
 |
 12月10日 12月10日 |
メッセージ要約 主題:「剣を捨てて勝つ道」
ルカの福音書22:47~53 三浦真信牧師
<47~48節>
イエスが弟子たちと話しているところに、群衆がやって来ます。この群衆は、剣や棒を手にしており、祭司長や民の長老たちから差し向けられた人たちでした(マタイ26:47)。その先頭に立っていたのが、「12弟子のひとり」であるイスカリオテのユダであったと、ルカはあえて記して強調しています。イエスの12弟子のひとりとしてイエスに選ばれ、イエスと3年間共に生活しイエスから教えを受けていたユダは、その中でも会計係という責任ある役割を担っていました。そのユダが、イエスを捕らえる集団の先頭にいたのです。
人は、それなりの立場にある人や尊敬している人を、美化したり過度に期待する傾向があります。しかしどの人にも欠点があり、またいつどう変わるかわからない危うさがあります。12弟子のひとりであったユダがそうであったように、誰もがそのような要素を持っていることを心しておきましょう。
ユダは「口づけ」という、本来は親愛の情を表す行為で、イエスを裏切ります。「ユダ。口づけで、人の子を裏切ろうとするのか」とイエスは言われました。「ユダ」と呼びかけられたときに、ユダがハッとして我に返り、「自分は何ということをしているのだ」と気づいて、イエスの前に悔いくずおれることをイエスは願っていたでしょう。しかしユダはイエスを引き渡すために淡々とイエスに口づけをし、群衆にイエスであることを合図しました。
<49~51節>
群衆がイエスを捕らえようと近づいてきたのを見て、イエスの周りにいた弟子が、その中の大祭司のしもべに剣で向かいます。その直前に過越しの食事で小羊を調理するために、彼らは二振りの剣を持っていました(38節)。
この時に剣で撃ったのはシモン・ペテロで、右耳を切られた大祭司のしもべの名はマルコスでした(ヨハネの福音書18:10)。ペテロは、すぐにカッとなって行動する直情型の人でした。イエスは、そのペテロに向かって「やめなさい」と制して、マルコスの耳を癒します。ペテロが群衆に向かい争うことは、決してイエスのお心ではありませんでした。イエスは、「剣をさやに収めなさい。父(神)がわたしに下さった杯を、どうして飲まずにいられよう」(ヨハネの福音書18:11)と言われました。ゲッセマネで苦しみもだえて祈る中で、イエスは十字架の死という杯を神の御心として受け取りました。今群衆がイエスを捕らえに来たことも、飲むべき杯として受け取っておられたのです。
またイエスは、「剣を取る者はみな剣で滅びます」(マタイ26:52)とこの時に言われました。剣を取って人に向かっていくなら、自分も剣で滅びるのです。暴力、暴言で人に向かうなら、自分自身も暴力暴言でやられます。この世界を見ても、身近な人間関係の中でも、イエスが言われた通りのことが起きています。決して剣を取ることで平和は実現しませんし、問題は解決しません。振った剣は、必ず自分に返ってきます。
イエスは続けて、「それとも、わたしが父にお願いして、12軍団よりも多くの御使いを、今わたしの配下に置いていただくことができないとでも思うのですか」(マタイ26:53~54)と言われました。当時パレスチナを支配していたローマ帝国の軍隊(レギオン)はひと軍団5~6千人いました。その12軍団よりも多くの御使いを呼んで、イエスを捕らえに来た群衆を追い返すことがイエスにはできたのです。しかしそうしたら、神の子キリストを通して罪人を救うという旧約聖書の約束が実現されないことになってしまいます。ですからイエスは、ご自分を救うために神の子の力を用いませんでした。捕らえられるままに捕らえられ、やがて十字架刑によって、すべての人の罪を負って死なれるのです。
<52~53節>
群衆と共に来た祭司長、神殿の守衛長、長老たちに、イエスは言われます。彼らは、イエスをねたみ、イエスの教えに反発し、イエスを罠(わな)にかけ、ユダを買収した人たちです。イエスは昼間は神殿で、毎日神の国の福音を人々に語っておられました。しかし彼らは、イエスの教えを聞いている群衆を恐れて、昼間はイエスに手を出しませんでした。あえて人目につかない夜に、しかも暗がりのゲッセマネの園で、武器を持ってイエスを捕らえに来ました。自分たちの心の中にある、ねたみや欲を、人目につかない暗やみの中で実行しようとしているのです。神の言葉を教えている祭司長たちが、神の言葉とは正反対のことを実行しようとしています。正に暗やみの力、サタンの力に捕らえられている証拠です。暗やみの力に捕らえられている人たちは、暗やみを愛し、暗やみのやり方を押し通して自らを滅びに招きます。暗やみの力に服従するのか、神の言葉に従うのかがいつも問われています。
神の言葉は、知っているだけでは不十分です。知っていても、従うのは自分の欲であるなら、暗やみの力であるサタンに従うことになり、最後は滅びです(ピリピ3:19)。
イエスは、ご自分の弟子であったイスカリオテのユダに裏切られ、捕らえられていきます。しかしイエスは、そのユダの心を知りながらも、ユダを愛しユダを「友よ」と呼びかけて立ち返ることを願っておられました(マタイ26:50)。
イエスには、ご自分を捕らえに来た群衆を追い返す力がありました。しかしそれでは、人々を罪から救うためにイエスを遣わした神の御心が実現しないことになってしまいます。あえてイエスは、神の御心に従い、すべての人の罪を負って十字架で死ぬ道を歩まれたのです。悩み苦しむ人々を助けるためには、多くの奇跡を行われました。しかしご自分のためには、その力も用いず、剣も取らず、ご自分が死んで人々にいのちを与える道を行かれたのです。ご自分を無にして仕える者の姿をとり、ご自分を卑しくし、十字架の死にまで従われたのです(ピリピ2:6~8)。剣を取って人を損なうのではなく、ご自身を与え尽くして多くの人に永遠のいのちを与えてくださいました。罪によって人を滅ぼそうとする唯一の敵であるサタンに、十字架の死と復活により勝利されたのです。神の子としての力も権威も用いず、ご自身を捨てて私たちにいのちを与えてくださったキリストに感謝をささげましょう!
|
 |
 12月3日 12月3日 |
メッセージ要約 主題:「苦しみもだえる祈り」
ルカの福音書22:39~46 三浦真信牧師
<39~40節>
弟子たちとの最後の食事を終えて、イエスは「いつものように」オリーブ山に行かれました (21:37)。そして「いつもの場所」でイエスは祈ります。この「いつもの場所」は、オリーブ山の麓(ふもと)にあるゲッセマネ(「油しぼり」の意味)の園でした(マルコ14:32)。イエスは、ここを祈りの場所としていました。「いつものように」「いつもの場所で」神に祈り、神と親しく交わっておられたのです。そして弟子たちも、この祈りの園にイエスに従って入っていきました。主イエスは、私たちをも祈りの園に招いておられます。私たちにとって、この「祈りの園」のような場が必要です。祈りはどこでもできますが、一日のある時間を、神様のためだけにささげることは、私たち自身の力となります。
イエスは、「誘惑に陥らないように祈っていなさい」と命じられました。私たちは、祈っていないとすぐに誘惑に負けてしまうのです。それはサタンの誘惑です。自分の欲望を神として生きる誘惑です(ピリピ3:19)。欲望を神として生きるなら、その最後は滅びです。欲望を神としている人は、地上のことしか思っていません。「天に国籍を持つ」(ピリピ3:20)神の国の住人として生きていません。祈っていないと、気づかないうちに欲望の奴隷となってしまいます。欲望に縛られると、神の御心が見えなくなり、思いが地上のことでいっぱいになってしまいます。「欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます」(ヤコブ1:15)。神を神として生きていくために、祈りの園を確立しましょう。
<41~44節>
弟子たちが見える程度に離れた所で、イエスはひざまずいて祈られました。聖書の中で「杯」の意味は、これから起きる幸いではないこと(エレミヤ49:12など)と、幸いなこと(詩篇16:5など)の両方があります。ここでは、「十字架における死」を意味しています。それはイエスにとっては耐え難いことでした。なぜなら、罪の無い方なのに、すべての人の罪の濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)を着せられることだからです。人は少し人から責められたり悪者扱いされるだけでも、不快に思ったり怒ったりします。しかしイエスは何の罪も無い方なのに、すべての人の罪の身代わりとなって十字架で死なれるのです。しかも私たちと同じ肉体を持っておられたので、体の痛み苦しみも味わい、人からも一時は父なる神からも見捨てられる孤独を経験されるのです。ですから、「この杯をわたしから取りのけてください」と祈られて当然でした。「わたしは悲しみのあまり死ぬほどです」(マルコ14:34)と心の内を弟子たちに話しておられます。
イエスは「苦しみもだえていよいよ切に」祈られました。「汗が血のしずくのように」地に落ちるほどの祈りでした。それは「御使いが天から現れて」イエスを力づけるほどでした。旧約時代も、御使いは神の人が苦しんでいる時に助ける存在として登場しています(創世記16:7~(ハガル)、22:1~(アブラハム)、31:11、48:16(ヤコブ)、士師記6章(ギデオン)、13章(マノア)、ダニエル6:22(ダニエル)…)。御使いが天からイエスに現れて力づけなければならないほどに、イエスは苦しみもだえて祈られたのです。そして祈りに祈る中で、最終的に「しかし、わたしの願いではなく、みこころのとおりにしてください」という祈りに導かれました。苦しみもだえて心の中にある思いを注ぎだして祈る中で、最終的にはっきり神から御心を受け取られたのです。
このキリストの姿を通して、祈りというものを教えられます。キリストでさえ、人としてこの世におられた時に、このような壮絶な祈りをされました(へブル5:7)。神の子が、人の罪を負って十字架で死なれるとは、これほど壮絶な苦しみでした。また人の罪とは、神の子を十字架にはりつけにするほどのものなのです。私たちの罪が、キリストにこの苦しみを負わせたのです。
キリストは、苦しみもだえる祈りの中で、神の御心がなることをご自身の願いと変えられました。祈ることで、御心がわかるようにされます。「神のみこころにかなう願い」は、その通りになります(Ⅰヨハネ5:14)。どんなことも祈って大丈夫です。本心を祈る中で、聞かれないことは御心ではないと知ります。また祈りの中で、その動機が示されます。自分の願いが、欲や古い肉からくるものであることを示されたり、心の中にある傲慢(ごうまん)や人を裁く気持ちがあったり、御心がなるまで待てない不信仰が示されたりします。祈ることで、神の御心、そして自分の対処されるべき罪が示されていくのです。私の肉に根差した願いではなく、神の御心がなることが最善だと心から受け取れるように変えられるのです。
「真の信仰は、神を思い通りに操(あやつ)ろうとすることではない。自分をみ旨にかなう位置に置こうとすることである」(フィリップ・ヤンシー)
<45~46節>
「イエスは祈り終わって立ち上がり」ました。御心をはっきり受け取った時に、立ち上がることができます。
弟子たちは、「悲しみの果てに、眠り込んで」いました。最後の食事の時にイエスから、ご自身が受ける苦しみ、また弟子たちが受ける試練のことを聞いて、悲しみに心が覆(おお)われていたのでしょう。また「心は燃えていても、肉体は弱いのです」(マタイ26:41)とイエスは言われました。弟子たちには、死んでもイエスについていくという熱い思いがありながらも(33節)、肉体の疲れや弱さゆえに、イエスが苦しみもだえて祈っている時に、起きて一緒に祈っていることすらできない彼らの弱さをも、イエスは理解し受け留めてくださっています。
たえずサタンの誘惑があります。欲望を神として生きるようにと、サタンは私たちを誘惑してきます。だから「祈っていなさい」と主イエスは繰り返し弟子たちに言われました。祈りの生活を確立していくように、弱い私たちのために祈りの見本を示してくださったのです。
ある時は、苦しみもだえながらでも、主の御心をはっきり受け取り切るまで祈ることが必要です。中途半端なところであきらめず、主から御心を受け取らされるまで、祈り続けるのです。受け取れないなら「受け取れません、この杯を取りのけてください」と本音で主にぶつかっていくのです。その中で、自分の肉や欲、高ぶりや不信仰を示され、最終的には「私の願いではなく、神の御心が最善です」と心から受け取って、すがすがしく立ち上がらせていただくまで祈り切るのです。一人ひとりの祈りの園で、主イエスのなさった祈りを実践してまいりましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()