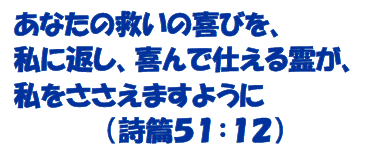2月25日 2月25日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「神が祝福する生き方」
士師記17:1~13 三浦真信牧師
士師記の17章~21章は、士師の時代に並行して起きた二つの出来事を記しています。確固たる霊的指導者がいないこの時代が、いかに暗く混乱した時代であったかがわかります。
<1~6節>
「ミカ」とは、「だれが主のようであろうか?(主なる神より偉大な方は他にいない)」という信仰的な意味の名前です。そのようなミカですが、母親から多額のお金を盗んだことから記されています。母親は、誰が盗んだかわからないときには、犯人を呪っていましたが、ミカが自分が盗んだことを告白すると、息子ミカの祝福を祈ります。そして返却されたお金で、信仰の名のもとに偶像を造り家に置きました。またミカは神の宮を持っていて、エポデ(祭司用の服)とテラフィム(異教で占いに使う道具)を作り、自分の息子を祭司としました。
この一連のおかしな出来事は、「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(6節)結果でした。主なる神を礼拝しながらも、家には偶像を置き、また自分勝手に祭司を立て、神が忌み嫌われる占いの道具を作って、何の違和感も感じないほどに、霊的に鈍感になっていたことがわかります。
神が与えられた十戒の一番最初に、「あなたは、わたしの他に神々があってはならない。自分のために偶像を造ってはならない。それらを拝んではならない」(出エジプト20:3~5)とあります。それがミカの家では堂々と破られていました。
また占いに用いられる道具を造りましたが、神は占いを禁じておられます(エゼキエル13:6~9)。そしてミカは勝手に自分の息子を祭司としましたが、当時祭司は、アロンの子孫であるレビ人がなると定められていました(出エジプト29:9)。「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」結果、神の言葉が蔑(ないがし)ろにされ、無秩序と混乱がイスラエルを覆(おお)っていました。
<7~9節>
若いひとりのレビ人が、滞在する所を見つけるためにユダのベツレヘムを出て旅を続け、ミカの家に来ました。ベツレヘムはレビ人に割り当てられた地ではありませんでしたので(ヨシュア21:9~41)、このレビ人は一時的にベツレヘムに滞在していただけのようです。9節の表現は、「私はれっきとした祭司としての資格があるレビ人であり、今自由契約の身です」と自分を売り込むような言葉です。
<10~11節>
ここでいう「父となってください」とは、年齢に関係なく「霊的指導者、アドバイザーになってください」の意味です。ここで契約が成立します。若いレビ人はミカと一緒に住み、息子の一人のように家族同然の生活を始めます。
<12~13節>
ミカは、レビ人が祭司となったことをとても喜んでいます。心のどこかでは、律法に反してレビ人ではない自分の息子を勝手に祭司にしたことで、うしろめたさを感じていたのでしょう。ミカとしては、れっきとしたレビ人を祭司としたので、主の祝福を受けられると安心したのでしょう。しかし実際には神が喜ばれる礼拝とはかけ離れていました。
モーセ、ヨシュアという指導者がなくなり、12人の士師を立てて神はイスラエルを外敵から守られましたが、霊的には暗く混迷した時代でした。「イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(6節)結果、秩序が乱れ、神の言葉から外れても何がどう外れているかもわからず、誰も指摘もしない中で、社会も混乱していました。
生ける主なる神を礼拝しながら、偶像もその場にあって何も感じないほどに、霊的に鈍くなっていた時代です。異教の地カナンに来たイスラエルの民たちが、少しずつ「周囲がしているから、近所の人もやっているから…」と言いながら、気がついたらおかしな状態もおかしいと感じなくなっていったのでしょう。
神が命じておられることは、それに従っていくことが一番の祝福の道です。神が「天地万物の造り主である神以外のものを神としてはいけない」と言われる時には、それに従うことが祝福の道です。偶像は、神から私たちを引き離す強力なサタンの力が働きます。
神の言葉に従うことが、神に造られた人間にとって一番しあわせなことです(申命記4:40)。「しあわせになりたければ、神の言葉に従って生きることだ」と聖書ははっきり語っています。それは苦難がなくなることではありません。苦難続きの中でも、神の言葉に従っている人はしあわせなのです。みことばを蔑(ないがし)ろにしている時には、平和でも不平不満でいっぱいになります。
たしかに私たちは今キリストの十字架の恵みにより、驚くほどの自由が与えられています。しかしすべてが有益であったり、すべてが徳を高めるわけではありません(Ⅰコリント10:23)。「すべてのことは、してもよいのです(聖霊を汚す罪以外は)」という自由を与えられていますが、だからといってそれでしあわせになるわけではありません。主の言葉から外れていることに気がつかないまま、どんどんそのズレが大きくなっていくと、ミカの時代のように霊的鈍感になり、気がつくと取り返しのつかない(神に立ち返ることができないこと)ズレになりかねません。
めいめいが自分の目に正しいと思えることを行っていたら、必ず秩序が乱れ、神の祝福から逸(そ)れていきます。自分の目にではなく、神が正しいとされる道を歩みましょう。神が祝福される生き方が、聖書ではっきり示されています。だから聖書を読みましょう。みことばを生活の土台としましょう。失敗したり、ズレに気がついたら、悔い改めましょう。「御子イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます」(Ⅰヨハネ1:7)。怒り、汚れ、悪を温存しないで、心の中に植えつけられたみことばを生活の中で思い起こし、みことばに自分を委ねていきましょう。みことばの方向に切り替えていきましょう(ヤコブ1:20~21)。神に従いましょう。そうすれば悪魔は逃げ去ります(ヤコブ4:7)。
|
 |
 2月18日 2月18日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「沈黙のメッセージ」
ルカの福音書23:8~12 三浦真信牧師
<8~9節>
ガリラヤの領主であるヘロデ(ヘロデ・アンティパス)は、ローマ総督ピラトの元からイエスが送られてくると、非常に喜びました。以前からイエスの噂(うわさ)は聞いていたので、ヘロデはイエスに会いたいと思っていました。またイエスの行う奇跡も見たいと思っていました。
しかしイエスは、かつてヘロデのことを「あの狐」と呼んでいます(ルカ13:31~33)。狐は、とても悪賢い動物として例えられていました。実際当時のローマ皇帝であるティベリウスに取り入るため、ヘロデは自分の領地にあったガリラヤ湖をテベリヤ湖と改名して西岸にローマ風のテべリヤという町を建設します。腹違いの兄弟ピリポ(3:1)の妻ヘロデヤを略奪したことをバプテスマのヨハネに諫(いさ)められると、彼を捕らえて首を切ったり、自分の立場を守るためなら何でもするようなところがありました。ヘロデは、イエスの噂(うわさ)を聞いた時には、バプテスマのヨハネが蘇(よみが)ったのではないかと当惑しています(9:7~9)。そのようなこともあり、またイエスの奇跡を見たいこともあり、イエスに会ってみたいと思っていました。
ヘロデがイエスに会いたい動機は、どこまでも興味本位なものでした。それは当時のイエスについてきた群衆の多くも同じでした。すごい奇跡を見たい、聞いたことのないような話を聞きたいと、新しい刺激を求めて興味本位に来た人たちは、イエスが捕らえられ十字架の道を歩まれると、今度はイエスの敵となります。イエスご自身ではなく、イエスの付き物を求めてついてきただけだからです。イエスご自身を本当に求めているかは、苦難の時にわかります。
イエスに実際に会えて大喜びしたヘロデですが、イエスはヘロデの質問に何もお答えになりませんでした。イエスには、この時に沈黙を貫くことが、ご自分にとって不利益であることはよくわかっていたはずです。しかしあえて何も答えませんでした。ヘロデが神を恐れる人であったら、このイエスの沈黙に対して、自分の態度がどのようであったかを自問したことでしょう。
<10~11節>
祭司長と律法学者たちは、何としてもイエスを犯罪人にしようと、激しくイエスを訴え続けました。ヘロデは、あれほどイエスに会えたことを喜びましたが、イエスが彼の質問に何も答えなかったため、兵士たちといっしょにイエスを侮辱(ぶじょく)の限りを尽くし、王様のような派手な服を着せてピラトに送り返しました。興味本位にイエスを求めただけだと、自分が求めたように答えられないと、今度はあらゆる侮辱でイエスを送り返すようなことになるのです。
<12節>
ガリラヤの領主ヘロデと、ローマの総督ピラトは、これまで敵対していました。それは立場の違いもあったでしょうし、ピラトがかつてガリラヤの人たちにした行為に対してヘロデが怒っていたこともあるかもしれません(13:1)。しかしその二人が、互いの立場(ガリラヤ領主・ローマ総督としての)を守ることで一致し、仲良くなりました。
イエスは、興味本位にイエスに質問したヘロデに対して、何ひとつお答えになりませんでした。イエスに侮辱(ぶじょく)されたと思い込んだヘロデは、イエスを徹底的に侮辱して送り返します。これはヘロデだけではなく、今もイエスに対して人々がしていることです。しかしイエスが沈黙しておられる時は、その沈黙自体に大切なメッセージがあります。主は私たちに、手取り足取りその場で教えてくださるのではありません。あえて沈黙の期間を経て、自分で考えたり、主に祈り問いかけ続けるようにしながら、主からの語りかけを受け取るようにされます。その間に、私たちの中にある肉の思いや、自分勝手な神へのイメージを白紙にさせられます。何でもスピードが要求される時代にあって、私たちは主イエスの答えを性急に求め過ぎるきらいがあります。すぐにイエスが答えないと、「何で答えないんだ!」と言って、イエスを侮辱していないでしょうか?イエスが沈黙しておられるように思える時こそ、自分の心を空(から)っぽにして、主の御声を聞いていく時です。実はいつも主は語りかけておられるのです。私たちの側が、自分の思いや勝手なイメージが強すぎて、神が語っておられる声を受け取れないのです。
主の手が短くて救えないのではありません。主の耳が遠くて聞こえないのではありません。私たちの罪咎(つみとが)が神との仕切りとなっているのです(イザヤ59:1~2)。神が与えようとしておられるものと、私たちが求めているものがずれているのです。そのズレを、神はたえず修正してくださいます。求めてすぐ与えられたら、主との深い信頼関係にはなりません。時間をかけ、自分の心や動機が探られる中で、主が最善のものを与えてくださることを時間をかけて知る中で、神への信頼が深められていきます。神が私たちに与えたいのは、その神への信仰です。
神が沈黙しておられるように思える時、実は主がたくさん語りかけておられる時でもあります。自分の心を空(から)にして、主の御声を聞きましょう。へりくだり、ひざまずいて主に向かいましょう。私たちのずれているところを、主にはっきり示していただき、神との仕切りが取り払われ、すっきりと主の御顔を仰げるように求めましょう。
|
 |
 2月11日 2月11日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「罪無き方が受ける苦しみ」
ルカの福音書23:1~7 三浦真信牧師
<1節>
ユダヤ人最高議会(サンヘドリン)で、イエスは冒とく罪と判決されました。そこで彼らは、ユダヤを統治しているローマ帝国の総督(そうとく)ピラトのもとにイエスを連れていきます。ピラトは、ユダヤ地方の5代目総督(そうとく)でした(紀元26~36年)。ピラトは、日ごろは地中海沿岸にあるカイザリヤにいました。そこに官邸があり軍隊もありました。でもこの時期は、過越しの祭りのため世界中のユダヤ人がエルサレムに集まり、エルサレムの人口が何倍にも膨れ上がります。暴動でも起きたら大変なので、それを監視するためにローマ総督(そうとく)はこの時期エルサレムに滞在していました。
ユダヤ人議会にとっては、ローマ総督(そうとく)ピラトがちょうどエルサレムに滞在していたため、すぐにピラトのもとに連れていくことができました。
<2節>
サンヘドリンの人たちは、イエスをピラトに訴えます。ただユダヤ人議会の裁判では、イエスが自分のことを神の子と言ったことによる冒とく罪でしたが、ローマの法律でそれは犯罪にはなりません。そこでピラトに対しては、イエスがローマの法律に反する政治犯であることを立証しようとしました。そのため以下のことでイエスを訴えます。
① イエスは国民を惑わした(扇動(せんどう)罪)
② カイザル(ローマ皇帝の称号)に税金を納めることを禁じた(法律違反)
③ イエスは自分のことを王キリストと言っている(反逆罪)
①に関して、イエスは国民を惑わすどころか、多くの生き悩む人たちを助けました。サンヘドリンの人たちとしては、自分たちの教えと違うことを教えて惑わしたと言いたいのでしょうが、実際は生きることに戸惑い、悩む人々をイエスは助けたのです。また決して人々を巻き込んで扇動(せんどう)するようなこともしませんでした。ただ淡々と苦しむ人たちに寄り添われたのです。
②に関しては、全く反対でした。律法学者・祭司長たちがイエスを罠にはめようとして送ったスパイの悪意ある質問に対して、「カイザルのものはカイザルに、そして神のものは神に返しなさい」とイエスは言われました(ルカ20:25)。当時使われていたデナリ銀貨に彫られている肖像がカイザルであったことを指して、このように言われました。ローマに納めるべき税金はローマに納め、神に返すべきもの、神にささげるべきものは、神にささげるようにと命じたのです。
③に関しては、キリストという称号が「油注がれた者」というギリシャ語でした(へブル後では「メシヤ」)。ユダヤにおいて、王は預言者から油を注がれて任職しました。確かにイエスは、キリストとして世に遣わされました。しかし当時のイスラエルの王となるために来られたわけではありません。やがて滅びゆく罪の世から人々が救われ、永遠に続く神の国の王となるため、霊的な意味での王として来られたのです。ローマ帝国に代わる地上の王になることなど、イエスの心には全くありませんでした。事実、5000人の給食の奇跡の後に、人々がイエスを自分たちの王にしようとした時に、イエスはただひとり山に退かれました(ヨハネ福音書6:15)。ユダヤの王になりたければ、この時その流れに身を任せていればなれたかもしれません。しかしイエスはそれを拒否して、山に退かれたのです。
このように、サンヘドリンの人たちのピラトに対する訴えは、どれも正しいものではありませんでした。
<3節>
総督(そうとく)ピラトは、サンヘドリンの最後の訴えを受けて、「あなたはユダヤ人の王ですか」と尋ねます。イエスはあえてご自身を守ることもかばうこともせず、「そのとおりです」と答えます。真の意味では、ユダヤ人議会やピラトが思っているような王ではないのですが、あえて弁明はされませんでした。
<4節>
イエスの答えを聞いても、総督(そうとく)ピラトは「この人には何の罪も見つからない」という判断でした。ローマ人であるピラトは、イエスに対して何の偏見もなく客観的に見られたので、冷静に判断することができました。
<5~7節>
祭司長、またいつしか巻き込まれていった群衆は、「イエスがガリラヤからユダヤ全土で教えながら民を扇動(せんどう)している」と言い張ります。
総督(そうとく)ピラトは、イエスがガリラヤ出身であることを聞いて、ガリラヤ地方の領主であるヘロデのもとにイエスを送ります。ここでピラトは、自分が「イエスに罪はない」と判決を出してユダヤ人たちに暴動でも起こされたら困ると思ったのでしょう。
ヘロデも、やはり過越しの祭りのこの時期は、エルサレムに滞在していました。このヘロデは、ヘロデ大王の次男ヘロデ・アンティパスです。ヘロデ大王の死後、ローマ帝国がこの地域を分割して、ヘロデ大王の息子たちに継がせます。一番目の息子アケラオは、ユダヤとイドマイ地方を受け継ぎますが、悪政のため紀元6年に失脚します。そしてその地域はローマに取り上げられ、ローマの直轄地となります。それ以来ユダヤ地方はローマの総督(そうとく)が送られるようになり、その5代目総督(そうとく)がピラトでした。そしてヘロデ大王の2番目の息子ヘロデ・アンティパスは、ローマ帝国の支配下でガリラヤとペレヤ地方の領主になります。ですからガリラヤ地方は、日常的にはこのヘロデ・アンティパスが治めていたのです。
ローマ総督(そうとく)ピラトも、ガリラヤの領主ヘロデも、ちょうどエルサレムに滞在中であったため、裁判はスムーズに進んでいきました。すべてが十字架に向かって整えられていたのです。
ユダヤ人最高議会サンヘドリンの議員たちと群衆たちは、イエスを重い犯罪人に仕立てようと、必死でイエスの罪状を挙げて訴えました。その群衆の中には、つい数日前までイエスを慕ってついて来ていた人たちもいたことでしょう。でもイエスが捕らえられると、今度はサンヘドリンの人たちに味方をして、イエスに敵対していきます。いかに群衆が不安定なものであり、当てにならないかがわかります。人からの関心、評価などは、時が過ぎたり状況が変われば簡単に変わるのです。いかに人の目を気にして生きることが空しいことかを教えられます。
そのような群衆たちを巻き込みながら、サンヘドリンの議員たちはイエスをローマ総督(そうとく)ピラトに訴えました。客観的に冷静に見て、ピラトは「この人には何の罪も見つからない」と判断しています。また「彼らがねたみからイエスを引き渡したことに気づいていた」(マタイ27:18)のです。ねたみの心は、自分よりも第三者の方がよくわかることがあります。あくまで、ユダヤ人議員たちのイエスに対するねたみから、イエスが訴えられているだけで、イエス自身には何の罪もないことをピラトは知っていました。しかもこの裁判中に、ピラトの妻から、「あの正しい人(イエスのこと)にはかかわり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に会いましたから」と、わざわざ遣いが送られてきました(マタイ27:19)。ピラトの妻も、イエスを「正しい人」と呼んでいます。
実際に罪を犯していないばかりか、罪そのものを持たないキリストが、苦難の道を歩み、十字架につけられるのです。自分の罪のためではなく、ご自身は「罪を知らない方」なのに、キリストは私たちの代わりに罪とされました(Ⅱコリント5:21)。それは私たちがこのキリストにあって神の義となるためです。罪を知らない方なのに、誰よりもひどい犯罪人の一人とされ、キリストは十字架で死なれます。でも罪のない方だからこそ、完全に罪人を救うことができるのです。
私たち人間は、少しでも人から悪者扱いされることを嫌います。ひどい時には、自分の罪を人に責任転嫁してでも自分をかばうものです。でもキリストは、全く罪を知らない方なのに、すべての罪をかぶってくださったのです。それはキリストを信じる者が、神と和解し、神の子となり、神の義と祝福を人々に流す存在となるためでした。
「罪のない方が、私の罪のために死なれた」ことを受けとめる時に、私たちの生き方が問われます。十字架のキリストを実生活の中で思い起こすときに、私たちの人間関係や生活そのものが問われます。キリストの十字架は、私たちの生活そのものに大きな影響を与える出来事なのです。この方にあって今、神の国民とされ、祝福の基とされたことを感謝しましょう。
|
 |
 2月4日 2月4日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「異なったキリスト理解」
ルカの福音書22:63~71 三浦真信牧師
<63~65節>
イエスが、この後議会にかけられるまで、監視人がつきました。彼らは、イエスをからかい、むちでたたき、悪口をあびせます。ゲッセマネの園で、十字架の苦難を神のみこころとして受け取られたイエスは、彼らのすることに抵抗も対立もしませんでした。
<66節>
ここの「議会」は、ユダヤの最高議会サンヘドリンのことです。サンヘドリンは、「民の長老たち」24人、「祭司長」24人、「律法学者」22人、そして議長となる大祭司1人の、計71人で構成されています。この時は、イスカリオテのユダがイエスを売り渡したことで、かねてからイエスに恨みを抱いていた人たちがチャンスとばかりに、夜明けから議員を招集しました。
<67~68節>
キリスト、メシヤに対する当時のユダヤ人の理解が根本的に違っていました。彼らはキリストを、ローマ帝国からユダヤを解放して力強い王国を建てる政治的リーダーと理解して待ち望んでいました。しかし実際のキリストは、すべての人を罪から救うために十字架で死なれます。王として国を建て上げるのではなく、自ら低く低くへりくだり、十字架の死をもって人々にいのちを与えてくださる方です。地上のいのちや繁栄ではなく、永遠のいのちを与えてくださる方です。しかし人々の凝(こ)り固まったキリスト像があるため、イエスは「その真理を語っても、あなたがたは決して信じないでしょう」と答えました。
またこれまでも、彼らにイエスは何度か質問しましたが、彼らは自分たちの立場を守るために答えませんでした(20:7など)。イエスが、真のキリストを伝えるために、彼らに質問したり話しても、答えないし受け入れもしないのです。
<69節>
「人の子」とは、イエスのことです(9:20~22)。イエスは、十字架の死後よみがえり、天に上り「神の大能の右の座に」着きます。イエスはそのことを、ここで宣言しました。そしてご自身が、神と等しい方であることをも表現されたのです。
<70節>
イエスの「人の子は神の大能の右の座に着きます」という言葉を受けて、議員たちは「ではあなたは神の子ですか」と問います。イエスの中には、「確かに私は神の子だが、あなたがたが抱いている神の子の概念とは根本的に異なっています」という思いで、「あなたがたの言うとおり、わたしはそれです」と答えました。
<71節>
サンヘドリンの議員たちは、イエスがキリスト、神の子であるとは受け入れませんでした。ですから、「神の子ではないのに、イエスは自分を神の子と偽った」と結論付けます。
イエスとサンヘドリンの議員たちとは、そもそもキリスト理解が全く異なっていました。異邦人であるローマから解放する強い王としてのキリストを思い描いていた議員たちからすると、この後十字架で死んでしまうイエスがキリストであるとは到底受け入れられませんでした。ユダヤ人にとって、十字架にかけられるキリストは、躓(つまず)きでしかありませんでした(Ⅰコリント1:22~24)。しかし十字架につけられたキリストを救い主、神の子と信じる者にとっては、十字架のキリストこそ人々を罪から解放する力であり、神の知恵であることを実感できるのです。
私たちも、キリスト理解がずれていないか、たえず点検しましょう。当時のユダヤ人たちのような勝手なキリスト理解でいると、「なぜ神の子なのに、世界の苦しみを放っておくのか」「なぜ神の子キリストなのに、私の抱えている問題を解決しないのか」という思いに支配されてしまいます。確かに、キリストは神の子で何でもできる方です。死からもよみがえった方です。キリストにある者は、このキリストの復活の力を体験します。でも同時にキリストの十字架の死をも体験するのです。キリストと共に生きるとは、キリストの十字架の死と復活を共に体験することです(ローマ6:4~5、ガラテヤ2:20)。
イエスが、十字架の死に向かって砕かれたように、私たちも砕かれるような出来事に会います。砕かれたどん底から、またキリストを求め、キリストの復活の力を体験します。キリストは、砕かれ砕かれ、罪人の代表のごとく十字架で死なれました。でもこの十字架にこそ、人の罪を完全にきよめ、新しいいのちを与える奇跡を生み出す力があります。
今キリストをどのような方と信じているでしょうか。キリスト理解がずれていないでしょうか。たえずみことばで確認する必要があります。キリストと一つになる方向は、古い自分に死に、自我が砕かれていく方向です。自分の思いも砕かれていき、神のなさることに明け渡していく方向です。自分で勝手に作り出したキリスト像から解放され、聖書が示す真実のキリスト信仰へと導いていただきましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()