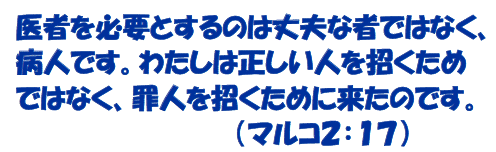3月25日 3月25日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「2人の犯罪人」
ルカの福音書23:39~43 三浦真信牧師
<39~41節>
イエスの両隣に、2人の犯罪人が十字架にかけられました。そのうちの1人は、イエスを十字架につけた人と同じように「キリストなら自分を救ってみろ」と言い、それに加えて「今十字架で苦しんでいる私たちも救え」とイエスに言いました。
しかしもう1人は違いました。最初は、2人ともイエスのことをののしっていたのです(マタイ27:44、マルコ15:32)。でも1人はずっとイエスをののしり続け、もう1人の犯罪人は途中から変わってきました。十字架上のイエスの隣にいて、「父よ。彼らをお赦しください」とイエスを十字架につける人たちのために祈られるイエスの姿を見ているうちに、彼自身の内側に変化が起きてきました。「おまえは神をも恐れないのか」と、イエスをののしり続けるもう1人の犯罪人に彼が言ったように、神への恐れの念が生じてきたのです。そしてその神への恐れは、罪の自覚が彼の内に生まれてきたことを表しています。それは「われわれは自分のしたことの報いを受けているのだからあたりまえだ」という言葉からもわかります。彼は自分の犯した罪の大きさを思い、この十字架刑は当然の報いだと思うようになりました。その結果、罪を裁く権威を持っておられる神への恐れが生じてきたのです。ですからイエスをもうののしることができなくなりました。
人をののしり神をののしる時、あるいは心の中で人を軽蔑する時、それは自分が神の前にどれほどはずれた者かを忘れている(あるいは知らない)状態です。造り主なる神の御前に立つなら、神からはずれ切っている自分の姿が見えてきます。そしてそのままでは滅ぼされても当然の者であることを知り、滅ぼすことも救うこともできる神への恐れが生じるのです。その時には、「お前は人をののしることができるほどの立派な人間か?」と問われます。
同じ犯罪人でも、1人はどこまでも自分の罪を認めずイエスをののしり続け、もう1人は自分の罪を認めて今の痛みも当然の結果と受け取り、大きな違いが生じてきました。
<42~43節>
自分の罪を認めた1人の犯罪人は、「あなたの御国の位にお着きになるときには(原文は「あなたの王国に入る時には」)、私を思い出してください」とイエスに言いました。キリストが王として君臨する国に、キリストは入られます。この犯罪人は、「自分の犯した罪の大きさを思うならとても御国に入る資格はないので、せめて私を思い出すだけでもしてください」とイエスに願います。
しかしイエスは驚くことに、「あなたは今日、わたしと共にパラダイスにいます」と答えられました。パラダイスとは、罪を悔い改めてキリストを受け入れた人が、死んだ後にキリスト再臨の時までいるところです。これに対して、罪(造り主なる神から離れた状態)を認めず最後までキリストの助けを求めなかった人たちがいくところは、「よみ」(ハデス、ゲヘナなど)と呼ばれています(ルカ16:22~24)。最終的には「第2の死」(ヨハネの黙示録20:13~15)が待っています。
自分の罪を認めた1人の犯罪人は、御国に入る資格は自分にはなく、せめてイエスに自分のことを思い出していただくことを願いましたが、イエスは「今日あなたは、よみではなく、パラダイスに私と共にいる」と言われたのです。
パラダイス第一号は、最も重い十字架刑に処せられた犯罪人でした。正に「罪人のかしら」である彼が、真っ先に救われたのです。そこに神のあわれみの大きさ、福音の恵みがあらわされています(Ⅰテモテ1:15~16)。
同じ犯罪人でも、1人は罪を認めずイエスをののしり続け、もう1人は自分の罪を素直に認めて罪の結果も当然と受けとめつつキリストのあわれみを求めています。罪を認めた犯罪人は、地上の刑罰は受けましたが、死んだ後の救いの約束をイエスからいただきました。この2人の犯罪人のどちらを選択するか、すべての人に問いかけられています。
法律を破るような罪を犯していなくても、きよい神の御前に立つときには、すべての人が罪ある存在であることを、聖書は宣言しています(ローマ3:10~18)。イエスを十字架につけた祭司長・律法学者たちは、どこまでも自分の義(正しさ)を主張して、神の御心からはずれている自分たちの姿、心の汚れを認めませんでした。ですから、キリストから遠く離れていました。
キリストは罪人を救うためにこの世に来られた方です。罪を認めてイエスの救いを求めるなら、どんな人でもキリストは救ってくださいます。「主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる」(ローマ10:13)のです。これが聖書が伝えている最も大切な福音(Good
News)なのです。
|
 |
 3月18日 3月18日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「父よ。彼らをお赦しください」
ルカの福音書23:32~38 三浦真信牧師
<32~33節>
イエスは、「どくろ」(ゴルゴタ)と呼ばれている所で、犯罪人たちと共に十字架につけられました。十字架刑は当時最も重い刑でした。強盗殺人などを犯した二人が、イエスの右と左につけられたのでしょう。
かつてイエスの二人の弟子(ヤコブとヨハネ)が、「イエスが栄光を受けられる時には自分たちをイエスの右と左においてほしい」と願い出ました(マルコ10:35~41)。イエスは正に今、十字架上ですべての人の罪の贖いを成し遂げようとしておられます。それは、人間的には屈辱と苦悩に満ちた場所ですが、そここそがイエスの栄光の場所なのです。でもイエスの右と左にいたのは、正真正銘の犯罪人たちでした。そこにイエスの弟子たちはいませんでした。イエスがやがてユダヤの政治的王になり、イエスについていった自分たちを良い地位に置いてくださる方としてしか彼らは見ていませんでした。イエスに対して求めるものが違っていたのです(マルコ10:38)。地上での誉れ、名誉、栄光を求めていた弟子たちは、十字架までイエスについていくことができませんでした。
<34節>
このイエスの言葉は、イエスが十字架上で語られた7つの言葉の最初です。直接はイエスを十字架にかけた兵士たち、またイエスへのねたみからイエスを十字架につけたユダヤ人指導者たちを指しますが、イエスはすべての人の罪を負って死なれるのですから、すべての人に対してのとりなしの祈りでもあります。「何をしているのか自分でわからない」のに、自分では正しいことをしていると思っているのが、造り主なる神からさ迷い出た人間の姿です。とんでもなく的はずれなことをしていても、「私は正しい」と主張し続けている私たちのために、イエスは大祭司として神と人を仲介しとりなしてくださっています。十字架上で大祭司として「父よ。彼らをお赦しください」と祈ってくださいました。
自分を十字架につける人々には、普通でしたら憎しみをもってにらみつけることでしょう。でもイエスは敵対してくる人々のために、「彼らをお赦しください」と祈られたのです。苦しみの極限状態では、人の本性が現われます。イエスは十字架上で苦しまれる中でも、このとりなしの祈
りをされました。むりやりイエスの代わりに十字架を担がされてここまで来たクレネ人シモン(26節)も、この十字架上のイエスの言葉を聞いて驚いたことでしょう。
ギリシャ語の「愛」には、「エロス」(本能的な愛)、「フィレオー」(兄弟愛、親子愛、師弟愛など)、「アガペー」(無条件、一方的な愛)などがあります。イエスの「愛」は、正に「アガペー」の愛でした。このアガペーは、愛する原因が自分の中にあるものです。相手の何かに一切よりません。相手が敵対してきても、自分をののしったり抹殺しようとしても、それによって憎んだり嫌ったりしないのです。敵のためにも、祝福を祈る愛です。人間の中からは出てこない愛です。でもキリストの愛を受け、聖霊に満たされた時に、奇跡的にこの愛で敵のためにとりなす祈りが与えられます。ステパノがそうでした(使徒7:54~60)。ステパノの生まれつきの性質ではなく、聖霊が働かれ、死に直面するステパノにこの祈りが与えられたのです。
「彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた」。イエスの上着は縫い目から4等分され、4人の兵士たちで分けられました。そして下着は縫い目がないので、それを4人でくじを引いて分けたのです(ヨハネ福音書19:23~24)。詩篇22:18の預言通りになりました。
<35~38節>
民衆も、ユダヤ教指導者たちも、兵士たちも、イエスがこれまで苦悩する人たちを助けてきたのに自分自身を救えないとはどうしたことかと、イエスをあざ笑いました。
兵士たちは、痛みを和らげる酸いぶどう酒をイエスに差し出して「ユダヤ人の王なら、自分を救え」と言います。それは「これはユダヤ人の王」と書いた札がイエスの頭上に掲げてあったからです。この札は、ローマ総督ピラトが、イエスに何の罪も見つからなかったのにユダヤ人たちがイエスを十字架につけろと訴え続けたことへの腹いせに、掲げさせたものです。ユダヤ人たちが、イエスを自分たちの王として認めたくはないことを知って、彼らへの皮肉を込めて掲げました。しかし結果として、イエスをあざ笑う道具となってしまいます。
イエスは、ご自分を救う力をお持ちでした。十字架から飛び降りることも、御使いたちに命じて自分を助けることもできました。でもイエスはご自身を助けるためには、一切神の子としての力も権威も用いませんでした。どこまでも神の御心である十字架の死にまで従われたのです。 「父よ。彼らをお赦しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです」と、イエスは今もイエスに敵対しイエスを無視する者たちのためにとりなし祈られます。
イエスは、「自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい」(マタイ5:44)と言われました。そしてイエスご自身が、それを十字架上で実行してくださいました。これは、イエスのご命令でもあります。「敵を憎んで良い」とは言われませんでした。自分を受け入れてくれる人を愛したからと言って、そのようなことは誰でもしていることです。それで満足してはいけないのです。「敵を愛し敵のために祈りなさい」が、主イエスのご命令です。そしてイエスご自身がその見本を見せてくださり、敵対する罪人のためにとりなし、いのちも捨てて罪人の救いを成し遂げてくださいました。この無条件の愛と恵みを受けた者として、イエスのこのご命令を軽々しく聞き流すことはできません。「どうせできないから無理です」と最初からあきらめてはいけません。イエスの十字架に死によって、とてつもない罪の負債が支払われ、私たちが滅びからいのちに移されたことを思うなら、私たちが誰かに敵対心や憎しみをもったままで平気でいられるはずがないのです。具体的な人間関係の中で、たえずこの主イエスのご命令の前に、自分がどうであるかを問われます。
イエスは、預言通り「そむいた人たちのためにとりなし」をされました(イザヤ53:12後半)。イエスの神へのとりなしがあるからこそ、今も私たちはキリストの御名によって大胆に神のもとに行くことができるのです。今もイエスが神と私たちの間を仲介し、とりなしてくださいます。敵対する罪人のためにも、とりなし命をささげて救ってくださった方のご命令に対して、自分自身が人との関係でどのようであるか問いかけましょう。
|
 |
 3月11日 3月11日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「自分のために泣きなさい」
ルカの福音書23:26~31 三浦真信牧師
<26節>
イエスは、ご自分がかけられる重い十字架を担いで行かれました。しかし夜を徹して行われた裁判と鞭で打たれたことで体力が消耗していて、途中で担げなくなってしまいます。兵士たちは、丁度その場に居合わせたクレネ人シモンに、イエスの代わりに十字架を負わせます。
クレネは北アフリカの海岸都市にありました。シモンは、恐らく過越しの祭りの時期であるエルサレムに巡礼に来ていたのでしょう。五旬節(ペンテコステ)にも、この地の人々がエルサレムに来ています(使徒2:10)。
シモンは「むりやり」十字架を負わされました(マルコ15:21)。「なぜ自分が十字架を背負わなければいけないのか?」と最初は思いながら、何度も倒れよろめくイエスの後をついて行ったことでしょう。本来ならシモンは祭りに出るために神殿に行くはずだったのに、イエスの代わりに十字架を負うことになり、そのまま十字架刑が行われるゴルゴタの丘まで行くことになります。しかしそこで十字架にかけられたイエスを見て、十字架上でイエスが語られる言葉を聞き、そのままイエスを信じイエスについて行く人になったようです。
マルコ15:21だけ、このクレネ人シモンが「アレキサンデルとルポスの父」であったことが記されています。マルコの福音書は、ペテロの通訳としていつも側にいたマルコが、ローマで書いたと言われています。ローマのクリスチャンたちにとっては、「アレキサンデルとルポス」は有名な兄弟だったのでしょう。ローマ16:13では、パウロもローマの教会に宛てた手紙で、「ルポスと彼の母によろしく」と書いています。クレネ人シモンが、むりやりイエスの十字架を担がされたことで、イエスの十字架を目の当たりにし、イエスを信じる者となり、その救いが家族にまで及び、初代教会を支える家族となりました。使徒13:1にある「ニゲルと呼ばれるシメオン」が、このクレネ人シモンのことであった可能性があります。もしそうであれば、クレネ人シモンは初代教会で重要な役割を果たしたアンテオケ教会初期の指導者であったことにもなります。
私たちにとっても、「むりやり負わされた十字架」があります。背負いたくはないけど、背負わざるを得ない十字架があります。でもそれを背負いながらもイエスのあとについて行くなら、そこに十字架の恵みが待っているのです。その十字架を通してでなければ、受けられなかった恵みがあるのです。ですからキリストを信じる者にとっては、すべてのことが益となるのです(ローマ8:28)。
<27~31節>
大勢の民衆や、イエスのことを嘆き悲しむ女性たちがイエスのあとについて行きました。イエスは彼女たちに、「わたしのことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と、自分の子どもたちのことのために泣きなさい」と言われました。イエスのあとをついてくる女性たちの中には、イエスに出会って人生を変えられた人たちもいました。「罪を犯していないイエスが十字架刑になってかわいそう」という思いでついてきた人もいたでしょう。でもイエスは、ご自分のためにではなく、むしろイエスの後についてくる人々、そして私たちを含むすべての人のために十字架で死なれます。私たちの罪が、罪なきキリストを十字架につけるのです。「神の子キリストが十字架で死ななければならないほどの自分の罪のために泣きなさい」とイエスは言われたのです。自分の罪を認めてキリストを受け入れないなら、そこに待つのは永遠の刑罰です。
当時不妊の女性は社会的にとても辛い状況にありました。でも「子を産まないことが幸せだ」というほどの時が来るとイエスは言われます(29節)。本来なら人生の喜びであるはずのことが、反対に不幸と感じるほどの苦難が来るのです。それは近いところでは、紀元70年に実際にあったローマ軍侵攻によるエルサレム滅亡でした。歴史家フラウィウス・ヨセフスの記録によると、その時に数百万人が虐殺され、まるでこの世の地獄と思えるような様相でした。子供がいることで逃げることが困難になったり、子供が苦しむ姿を見ながら何もできず、子を産んだことさえ災いと思うほどの苦難が及びました。そしてそれよりもはるかに恐るべき永遠の刑罰が待っているのです。あまりにも悲惨な出来事のために、人々は山に押しつぶされ、丘の下敷きになっても、この恐怖から逃れられるなら幸いだ…という時がくるのです(30節)。
「生木」であるイエスでさえ、このような十字架の苦しみを受けるなら、「枯れ木」のように罪あるままの人間はどれほどの苦しみに会うことでしょう(31節)。キリストとの関係がなく、霊的に枯れた者に下る神の大審判がどれほど恐ろしいものかを思って、主イエスは「自分自身と、自分の子どもたちのために泣きなさい」と言われました。自分の罪を認めず、キリストから無条件で差し出された救いを拒むなら、紀元70年に起きたエルサレム滅亡どころではない、終わりの日に、そして死の後に永遠に受ける苦しみがどれほどのことかを真剣に考えるように主は促されました。
キリストの救いを軽く考えてはいけません。キリストを拒み、キリストとの関係をもたない結果もたらす永遠の苦しみを思うなら、救われても救われなくても良いなどとは決して言えません。救
(裏面に続く) われなければ大変なことになります。この地上でどんなに幸せでも、それなりに思い通りの人生を歩んだとしても、また子供たち、孫たちが、幸せに暮らしていたとしても、もし神との関係を断絶する自分の罪に泣いてキリストを求めることがなければ、かえって今の幸せが逆に不幸のどん底に変わる時がきます。「いつか信じればいい」「死ぬ直前に信じればいい」などと言っている間に、突然命が取り去られるかもしれません。キリストの救いが差し出されている今、自分の罪に泣き、生木であるキリストにつながっていのちを得ましょう。
今何を悲しみ、何を喜んでいますか?キリストが悲しまれることを悲しみ、キリストが喜ばれることを喜びとしましょう。罪の結果である永遠の苦しみから、キリストを信じる者たちは解放されるのです。これに勝る喜びと安心はありません。「いつか、いつか…今は幸せだから…」と言っていたら、突然滅びが襲いかかります(Ⅰテサロニケ5:2~11)。今は恵みの時、今は救いの日です(Ⅱコリント6:2)。ですから今キリストを信じ受け入れましょう。また今キリストを宣べ伝えましょう。
|
 |
 3月4日 3月4日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「バラバを釈放する人間の罪~ねたみがもたらす悲劇~」
ルカの福音書23:13~25 三浦真信牧師
<13~16節>
ローマ総督ピラトは人々を集め、イエスを有罪とする理由がないことを伝えます。何も罪が見つからなければ、そのまま釈放すれば良いのですが、あえて「懲らしめたうえで」釈放すると言っています。全く何もしないと、群衆が納得せず暴動でも起こされたら困ると思って、妥協案を提示したのでしょう。ピラトは少しずつ真理を曲げて民衆に譲歩します。ここから民衆に引っ張られて、最終的には全く真理とは違った方向に進んでいくことになります。
<17節>
この節は、ルカの福音書の権威ある写本の中にはほとんど見出されていないため、本文からは外されています。しかし並行記事のマタイ27:15、マルコ15:6には記されています。マルコ15:6~11では、群衆の方から、慣例通り囚人を赦免するようにと要求していることがわかります。それに対しても、ピラトは「ユダヤ人の王イエスを釈放するか」と問いかけています。それは祭司長たちが「ねたみからイエスを引き渡した」ことが明らかだったからです。
ねたみというのは、厄介なものです。ねたみほど残忍で恐ろしいものはないと、箴言の作者も言っています(箴言27:4)。人類最初の殺人事件は、ねたみが原因で起きています(創世記4:1~16)。神はカインのささげ物に目を留めず、弟アベルのささげ物に目を留めました。そのことを兄カインがねたんで、弟を殺害します。カインはその後その罪の大きさに苦しむことになります。カインは、なぜ自分のささげ物に神が目を留めなかったのか、自分の問題は何であったのかを神に問いかけるべきでした。しかしカインは自分の問題に向き合うことなく、弟アベルの存在をねたみ殺していきました。
自分の内側に、ねたみの心があると気づいている人は、その問題に向き合えるからまだ安心です。しかしそれがねたんでいる自分の問題だと気がつかず認めない人は、相手を恨み相手のせいにしていくから厄介です。イエスを十字架にかけようとした当時のユダヤ人指導者たちも、ねたんでいる自分の問題に向き合わず、イエスを恨みイエスを抹殺(まっさつ)してく方向に行ってしまいました。ねたみの心は恐ろしいものです。しかも誰の心にも起きてくるものです。それに気づいたら、温存しないで神に速やかに処理していただきましょう。
<18~22節>
群衆は、暴徒で牢に入れられていた正真正銘の犯罪人バラバを釈放して、イエスを十字架につけるように繰り返し訴えます。ねたみからイエスが訴えられていて、実際には何の罪もイエスには無いことを知っているピラトは、3度もイエスの釈放を宣言します。
<23~25節>
それでも人々はイエスを十字架につけろと叫び続け、ついにその声が勝ってしまいます。ピラトは、イエスが無罪だとはっきりわかっていたのに、群衆の要求を受け入れてしまい、真の犯罪者バラバを釈放し、罪なきイエスを民衆に引き渡し十字架刑にします。
ピラトは、どこまでも自分の身を守るために、真実を曲げてしまいました。ピラトとしては、ここで暴動にでもなったら、ローマ帝国からお叱りを受け、自分の総督としての立場も危うくなると恐れたのでしょう。どこまでも自分の立場を守るために、間違った判決を下してしまいます。
でも実際には、このことがピラトにとって命取りになりました。自分の立場を守るためだけに、無罪であるイエスを有罪にしてしまったことで、民衆は「何か気に食わないことがあれば暴動を起こせばピラトは真実さえも曲げてしまう」ということを学んでしまったのです。そのため、逆にピラトが総督であった期間は暴動が絶えませんでした。あまりに頻繁にピラトの管轄で暴動が起きるため、ピラトは紀元37年にローマに呼び出され、その不始末を咎められて自殺します。彼にとっては、総督という立場を失ったら生きていけなかったのです。どこまでも総督の立場にしがみついていました。永遠には続かない一時的な立場にしがみついていることがいかに不自由なことかを、ピラトの人生を通して教えられます。
しかも彼は、世界のベストセラーである聖書に、とんでもない冤罪(えんざい)の責任者として記録され、時代を超え世界中でその汚点を人々に知られることになりました。
本来十字架刑になるのは、囚人バラバの方であって、イエスは全く罪のない方でした。人々の要求は、真の犯罪人であるバラバを赦し、罪なきイエスを十字架にかけることでした。これは遠い昔のユダヤ人たちの出来事で終わらず、今も私たちがしていることなのです。
自分の中にあるねたみや古い肉の思いに気づかず、認めないでいると、人をさばき人を責め、人を十字架につけていきます。それはイエスが歩まれた十字架の道とは正反対です。イエスと一つになりたいなら、むしろ自分の古い肉をたえず十字架につけましょう。キリストと共に、この古い肉は十字架で死んだものとして認めましょう(ガラテヤ5:16~26)。肉を満足させる方向は、御霊の方向と対立します。その結果、本当に自分がしたいこと、すべきことができなくなってしまうのです。肉を生かしていこうとすると、不自由になります。御霊に明け渡し、御霊に導かれていく方向が一番楽なのです。ガラテヤ5:19~21にあるような肉が自分の内にあることをたえず認め、それらを十字架につけてしまったものと認めましょう(ガラテヤ5:24)。
肉を生かす方向は、バラバを赦していくのと同じです。私たちの生まれながらの性質は、自分の内にあるバラバを生かしたいのです。それを認めて処分したくないのです。でもそれは、御霊と対立するからそのままでは不自由になります。私の内にあるバラバ(肉)を赦すのか、それを十字架につけていくかで、生き方が違ってきます。肉はキリストとともに十字架で死んだものと認めて、聖霊に処分していただきましょう。
ねたみを生かし、肉を生かしていく生き方は、イエス時代の律法学者たちの生き方です。そこでは自分の罪を認めないから、罪からの救い主であるキリストを抹殺していきます。自分の内側にある肉を正直に主の前に認めましょう。自分が憎んでいる人、「あの人さえいなければ…」と思っている人がもしいたら、それを相手の問題とする前に、自分の内にある何が問題であるかを主に問いかけましょう。そして古い肉はたえず十字架で処分されたものとして、主が喜ばれる、聖霊に満たされる方向に導いていただきましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()