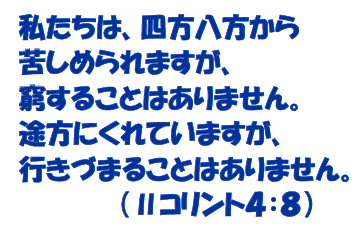4月29日 4月29日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「信仰の原点、感謝、使命に生きる」
マルコの福音書8:34進藤龍也・「罪人の友」主イエス・キリスト教会牧師
国内や海外各地の刑務所を、受刑者を更正させる目的で訪問しています。かつては悪事をして刑務所に入った私が、この働きのため刑務所に行くというのは神様の不思議なみ業と言えます。神様は、見えるものの先にある、人知をはるかに超えた良い出来事を与えて下さるお方であり、まさに不思議なお方です。キリストは既にこの世に勝たれたお方ですし、全てが新しくなったと言われます。神様はキリストを通して、私達の目に見える現実ではなく、完成形を見て下さるのです。救われた当初の喜びがその後、現実の生活の中で薄れてくることが多いです。その喜びをいかに持続させるか、実は喜びは選択できる、私達が選び取れるもので、信仰生活を送る上での秘訣だと思っています。
刑務所伝道では、福音を伝えるのに加えて、出所した人を寝泊まりさせ、仕事を見つけ、部屋を借りられるまでサポートする方が大変です。刑務所の中でイエス・キリストに出会って救われた経緯があり、同じ境遇の人の気持ちが分かるから、私はこの使命のために働いています。
<信仰の原点>
私自身と私の教会では「信仰の原点、感謝、使命」を大切にしています。信仰の原点、信仰はただ信じるだけ、神様からの恵みです。十字架の意味は「マイナス」が「プラス」に変わることです。他人に話せない、思い出したくも無い過去の失敗や罪も、イエスキリストにあっては、取り返しのつかない事は何もありません。私のような元犯罪者には、聖書で言う「罪人」が良く分かります。法律という基準を犯したから「罪人」とはっきり分かります。悔い改められたのは聖霊が働いて下さるからです。
私が捕まった日が実は、神様の御手が働いていたと今は信じています。聖書を読むきっかけは、ミッションバラバの鈴木啓之(ひろゆき)牧師の話を聞いて、手ほどきを受けたのが信仰の原点です。「わたしは決して悪者の死を喜ばない。かえって、悪者がその態度を悔い改めて、生きることを喜ぶ。・・・・イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。」(エゼキエル33:11)。私はこのみ言葉でイエス・キリストに出会い、解放と喜びを与えられました。2001年8月に刑務所内
でキリストを信じ、2003年11月に出所し、12月に洗礼を受けました。
<感謝を忘れない>
人生はイエス・キリストを信じても山あり、谷ありで平坦はすぐ無くなります。信仰の戦い、苦しみがある時には、ダビデが言う「私の命をあらゆる苦難から救ってくださる主は生きておられる」(I列王記1:29)を思って、乗り越えてきました。ダビデは逃亡生活の最後に、ユダの長老達に贈り物をして感謝を表しています。感謝を口ずさみ、感謝を忘れないことが大切です。刑務所から出所して家に帰り、15歳のとき以来離れていた母親に土下座して迷惑をかけた事を謝りました。母は、後に洗礼を受けるようになり、今は礼拝を共にしています。
出所後の生活を送る際に、様々な人からお世話になった事が忘れられません。献金によって教会内の敷地にプレハブの建物を作られ、3人が寝泊まりしました。朝食を買って来て下さった方もおられました。与えられてきた親切な事を忘れずに、今、自分にできることをしています。刑務所にいる時にある引退牧師が文通して下さったので、私も今刑務所にいる人から手紙をもらった時には無視できません。毎日の積み重ねにより、いつの間にかキリストのみ姿に変えられていく-クリスチャンの目標はキリストの身の丈にまで成長することです。(ガラテヤ4:19)
愛せない人を愛する、赦せないことを赦すための戦いの中から、信仰が増し加えられて行くのではないでしょうか。どうしても赦せなかったこと-IDを盗んで、多額の借金を私に負わせた人を私はどうしても赦せませんでした。恩を仇で返されたのですが、その人のためにもキリストは血を流されたことを神様から直接示されて以来、赦せるようになり今は全く憎しみがありません。赦しと愛の秘訣は、「赦します。愛します。」と口に出す事で、その告白に自分の気持ちがついて来るものなのです。
<使命に生きる>
自分を捨て、自分の十字架を負うとはどういうことでしょう。自分を捨てるのは、自己中心から、神を第一に生きて行く事です。十字架を負うことには、①私の罪のために死んでくださったイエス様を認めて生きる、②教会にいることや生かされている事の意味を考える、③イエスについて行く、ことがあります。刑務所から出る前には恐れがありました。私の弱さ-覚醒剤、女、酒、暴力-それらの誘惑に再び戻らないようにならねばと誓って出所しました。目標設定、ビジョン を明確にすることは必要です。自分を捨てる、つまり砕かれることで、キリストが私の罪を十字架を負われた事実が見えて来ます。そうすると、いろいろな困難も乗り越えて行くことができるのです。
刑務所にいた時に、出所したら私と同じ受刑者を助けるために召されたのだという明確なビジョンを持ちました。神と共に見る夢は、み言葉を添えて想像すると実現します。安定感があっていつも教会にいる人、人に仕える事のできる人が霊的な人です。救われた私たちは、本来の自分を取り戻すことになります。それが生きる喜びなのです。
弟子になる決意をして私は歩んできましたが、皆さんにも是非そうして頂きたいのです。いやしを受けたら帰ってしまう群衆か、それともイエスと共にいてそのミニストリーを共にしていく弟子となるのか。教会にずっと来られている方は、是非弟子の自覚を持って帰って欲しいものです。
イエス・キリストにあって、取り返しのつかないことはありません。私達が漠然と持つ、死んだらどうなるかと言う不安も、イエス・キリストが死んで蘇ったことで、死を打ち破り解決して下さいました。イエス・キリストを信じ受け入れて、人生が変えられます。みことばに力があるので、このような私も変えられたのです。
(要約まとめ:田内博)
|
 |
 4月22日 4月22日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「主が正しいと見られること」
士師記(ししき)18:1~31 三浦真信牧師
<1~6節>
「そのころイスラエルには王がなかった」で始まる18章は、この時代「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(17:6)という社会状況が続いていることを強調しています。神のみことばからはずれていても、そのことにも気がつかず、ただそれぞれの人の基準で生活していたことを示しています。その結果、霊的にも暗く混乱した社会となっていました。
イスラエル12部族の一つであるダン族が、自分たちの住む地を求めていました。彼らにはすでに割り当て地が与えられていました(ヨシュア19:40~48)。しかし先住民であるエモリ人の圧迫のためにその土地を占領できずにいました(士師(しし)1:34)。神から割り当てられた土地を得るために戦うべきなのに、ダン族はあきらめて他の安易に得られる気に入った場所を求めていったのです。そのために偵察隊を派遣し、彼らはエフライムの山地にあるミカの家に途中泊まります。
ミカの家で、ベツレヘムなまりの若者(17:7)の声を聞き、彼がミカの家の祭司であることを偵察隊は知ります。その若者が祭司であると聞いて、彼らは自分たちのこの旅が成功するかを神に伺ってほしいと彼に求めました。ダン族が相続地を占領できなかったのは、彼らの不信仰のためでした。それでも、神が割り当てた相続地以外の土地を得るために神が助けてくださるかどうかを知りたかったのでしょう。その祭司は、神に伺うこともせず、「あなたがたのしている旅は、主が認めておられます」と自分の判断を伝えました。神が立てられた祭司であるなら、神が割り当ててくださった相続地をどこまでも受け取って戦い続けるように勧めるべきでした。しかしミカの家の若い祭司は、神に伺うこともせず自分の思いだけで、人に受けが良い内容を答えていきました。神の御心ではないことを、あたかも神の御心であるかのように語ったのです。それは主の名をみだりに唱(とな)えることです(出エジプト20:7)。
<7~10節>
偵察隊5人は祭司の言葉を信用して、さらに北方に進みライシュという町に着きます。そこでは住民が平穏に生活し、足りないものもなく、拘束する者もなく、いざという時には孤立した地域であることを見て、そのことを帰って報告します。
<11~20節>
そしてライシュの町を占領するため、ダン族5人の偵察隊と600人が武具を身に着けて向かいます。その途中でまたミカの家に寄り、勝手に彫像(ちょうぞう)などを奪っていきます。ミカの家の祭司が止めに入ると、彼らはその祭司にダン族の祭司になることを提案します。その若い祭司もそれを喜んで受け入れ、ミカの家を出ていきました。ダン族は、ミカの家の彫像(ちょうぞう)も祭司も堂々と盗んでいったのです。
<21~26節>
ダン族の略奪に気がついたミカは、取り返そうとして彼らの後を追います。しかし彼らに脅され、とても勝ち目がないことを悟って、あきらめて帰りました。
<27~31節>
ダン族は、ミカの家の祭司とミカが造った物を奪い去り、目的地ライシュに行きます。その町を攻撃して占領し、ライシュをダンと改名しました。そこにミカから奪った彫像(ちょうぞう)を自分たちのために立てます。シロにあった神の宮がペリシテ人に破壊されるまで、ミカの家の彫像(ちょうぞう)がダン族のために立てられていました。またミカの家から連れてきた祭司は、モーセの子孫であり、捕囚の日までその子孫がダン族の祭司でした。
士師記(ししき)17章~18章は、イスラエル12部族の一つであるダン部族の北方への移動という出来事が記されています。そこで浮き彫りになっているのは、神の民でありながら、霊的に暗く神から遠く離れているイスラエルの姿です。
神の宮を所有していたミカは、親の大金を盗み、母親にばれるまでは知らないふりをしていました(17:1~2)。家には偶像を置き、勝手に祭司を立てました。モーセに与えられた律法にある、「あなたは自分のために偶像を造ってはならない…盗んではならない」(出エジプト20:4~5、15)が神の基準でした。しかし「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(17:6)ため、神の目に正しいことが無視されていました。
ミカの家に来たレビ人祭司も、ミカが生活の保障を約束するとその家の祭司になり、偵察隊に神に御心を聞かれると、主に伺いもせずに自分の判断で受け入れやすい内容を答えます。それは神の御心とは正反対でした。ダン族から自分たちの民族の祭司になることを提案されると、彼らがミカの家のものを盗んだことには目をつぶって、その提案を受け入れついて行きます。その日和見主義的な行動は、いかに自分にとって都合が良いか、有利であるかということが基準であり、「神の目に正しいことは何か」ということが蔑(ないがし)ろにされていました。神から律法を与えられたモーセの子孫でありながら、神の言葉に従うことも、また神に伺うこともしませんでした。
ダン族も、神から割り当てられた土地があるのに、妨害を受けると戦いを放棄して、目に見えて麗しく占領しやすいライシュを奪い取り、ミカの家から盗んだ彫像(ちょうぞう)と祭司を自分たちのために立てていきました。まことの神は無視され、人が造った偶像と、神の言葉を語らず神の御心も聞かない祭司が立てられていきました。
神の言葉が軽んじられていくときに、いかに暗やみの出来事が起きていくかを警告しています。「神のみおしえを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません」(詩篇119:165)神の言葉を愛し、大切にしていくことこそ、平和な生き方です。自分の思いや基準を先立てるところには、罪の混乱があります。最初の人アダムが、神の言葉をうしろにしたことから、罪が入り、混乱・争い・苦しみに満ちた世界となりました。神の言葉をなおざりにして、自分の目に見える正しいことを生活の基盤としたら、必ずおかしくなりその結果を刈り取る時がきます。
「主が正しい、また良いと見られることを」をしましょう。それがしあわせの道です。神は私たちを拘束しようとしておられるのではありません。私たちを祝福するため、しあわせな人生を歩めるように、みことばでその道を示してくださっているのです。私たちの生まれながらの肉は、すぐに自分の目に正しいと思う道を選びます。だから生活の現場で正気に戻る時が必要です。神の言葉をたえず聞き、神の言葉を思い起こし、神に「これでよいのでしょうか?」とどのようなことも尋ね求めましょう。「主が正しい、また良いと見られること」をしていくことが、神の祝福を受けていく道です。何度はずれても、またみことばに立ち返りましょう。神は私たちの失敗を赦さない神ではありません。すぐにはずれてしまう弱い者だとご存じです。だから神の子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって十字架で死なれました。十字架のキリストを通して、何度でも悔い改めて神に立ち返ることができます。キリストにあっては、何度でもやり直しができるのです。
今日自分の思いを優先して、神のことばをうしろにしたことに気づかされたなら、悔い改めてもう一度主の言葉に立ち返りましょう。「主が正しい」と見られることを、大切にしましょう。
|
 |
 4月15日 4月15日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「十字架の奇跡 」
ルカの福音書23:47~49 マタイ27:51~56 三浦真信牧師
イエスが十字架上で息を引き取られてから、いくつもの不思議な出来事が起きました。その一つとして、「神殿の幕が真っ二つに裂けた」(23:45)ことがあります。マタイ、マルコの並行記事では、エルサレム神殿の幕が「上から下まで」裂けたことが記されています(マタイ27:51、マルコ15:38)。完全に幕は裂けたのです。
「神殿の幕」とは、聖所と至聖所を隔てている幕のことです。聖所から至聖所に入っていくことができたのは、神にとりなしをする大祭司だけでした。大祭司も年に一度だけ、贖罪(しょくざい)の日に贖(あがな)いの供え物(動物の血)をもって入ることができるだけでした(へブル9:11~12)。大祭司は人間なので不完全です。また動物の血も完全に罪を取り除くことはできません。しかし完全な大祭司キリストは、たった一度の十字架の死により、完全な供え物となってくださいました。不完全なら繰り返し必要ですが、完全な大祭司であり完全な神の小羊キリストは、一度で完全な罪の贖(あがな)いを成し遂げてくださったのです。キリストが「完了した」(ヨハネ19:30)と十字架上で勝利を叫ばれた時に、もう贖(あがな)いは成し遂げられたのです。
今私たちは、イエスが流された十字架の血により、大胆に至聖所に入ることができます。「イエスご自身の肉体が垂れ幕(たれまく)」となり、イエスが「私たちのためにこの新しい生ける道を設けて」くださいました。「邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい水で洗われた」のです。「約束された方は真実」なのです(へブル10:19~23)。イエスの血により罪きよめられた者たちは、「道であり真理でありいのちであるイエス」(ヨハネ14:6)を通して、いつでもどこでも神にお会いすることができるのです。聖所と至聖所を隔てていた幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。大胆にイエスの御名によって神と交わる至聖所に入りましょう。
<47節>
イエスの死後、「地が揺れ動き、岩が避け、墓が開いて多くの聖徒たちのからだが生き返り」ました(マタイ27:51~54)。イエスの十字架の一連の出来事をそばで見ていたローマの百人隊長は神をほめたたえ、「ほんとうに、この人は正しい人であった」と言っています(マタイ、マルコでは「この方はまことに神の子であった」)。イエスの十字架刑執行を見守るローマの隊長が、神をほめたたえる人に変えられたのです。イエスを十字架につける側にいた百人隊長が、イエスを神の子と信じ崇める人に変えられました。これもキリストの十字架の死がもたらした奇跡です。
<48節>
これまでイエスをののしりあざけった群衆たちも、イエスの十字架上の言葉を聞き、3時間の暗やみを経験し(44節)、イエスの死と同時に起きた様々な超自然的な出来事を目の当たりにして、「胸をたたいて悲しみながら」帰っていきました。「胸をたたいて」という表現は、悔い改めを表すときに使う言葉でもあります(ルカ18:13)。群衆の中にも、ローマの百人隊長のように、自分の罪を悔い改め、そしてイエスを神の子と認めて崇めた人たちがいました。
<49節>
男の弟子たちはイエスが捕らえられると皆逃げてしまいましたが、イエスの死までずっとイエスのそばにいた女性たちがいました(マルコ15:40~41)。イエスと出会って人生を変えられ、暗やみから光の中に移された多くの女性たちが、最後までイエスについていきました。それだけイエスを慕う思いが強かったのです。
神の子イエス・キリストが、すべの人の罪を負って十字架にかけられた時に、様々な不思議な出来事が起きました。それらを通して、異邦人であり当時ユダヤを統治していたローマの百人隊長が、神をほめたたえ崇める人に変えられ、イエスをののしっていた群衆の中からも、胸をたたいて悔い改めイエスを信じる者たちが起きてきました。
人は簡単には変わらないものです。いくら人が説得してもなかなか変わりません。しかし神の子の十字架の死と復活は、人を変える力があります。このイエスの十字架の時に、数々の奇跡が起こされ、神の力、神の愛、神のエネルギーが注がれたのです。「この十字架のイエスを見て救われ生きよ!」と神が特別なメッセージを送っておられるかのように、この十字架の重要性を強調するかのように、キリストの十字架の死の前後には多くの奇跡が起きているのです。
「キリストの十字架は私のためであった」「イエスを十字架につけたのは私自身だ」「私の罪がイエスを十字架につけたのだ」と気づき悔い改めた時に、イエスの十字架が私たちを新しく造り変えます。
キリストの十字架の死がもたらした何よりもの奇跡は、イエスに敵対していた者たちが罪を認め悔い改めて、神をほめたたえる人に変えられたことです。そして今も十字架のキリストを見上げる時に、この奇跡は起きるのです。キリストに出会った人たちを通して、今も神の国は広がり続けています。すでに神殿の幕は上から下まで真っ二つに引き裂かれ、イエスご自身が垂れ幕(たれまく)となり、道となって私たちを神のもとに招いておられます。今イエスを信じる者たちは、大胆に至聖所に入り神とお会いすることができるのです。祈ればいつでどこでも答えてくださる主がおられます。この特権を大胆に用い、どのような時にもキリストの御名によって祈りましょう!
|
 |
 4月8日 4月8日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「十字架上での勝利の叫び」
ルカの福音書23:44~46 三浦真信牧師
<44~45節>
イエスが十字架にかけられたのは、朝9時頃です(マルコ15:25)。そして昼の12時までに「十字架上での7つのイエスの言葉」のうち以下の3つが語られています。
① 「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)
② 「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます」(ルカ23:43)
③ 母マリヤのことを、12弟子の1人であるヨハネに託した言葉(ヨハネ19:26~27)
その後昼の12時頃から午後3時まで、太陽は光を失い全地が暗くなりました。過越しの祭りの期間で満月の時期であり、暦上も自然現象としての日食が起きる時ではありません。明らかに神が超自然的力で起こされた出来事です。これと同じようなことが、イスラエルが奴隷として苦しんでいたエジプトの地から脱出する直前にも起きています(出エジプト10:22)。
ルカはイエスの地上での最期の出来事を、「第2の出エジプト」と捉えています。イエスが山上でモーセ・エリヤと「エルサレムで遂げようとしておられるご最期について」(9:31)話されました。この「ご最期」という言葉を、ルカはあえて「エクソダス」という原語を使っています(医学的な「死」は普通「サナトス」です)。またⅡペテロ1:15で、ペテロも「死(この世を去る)」をあえて「エクソダス」で表現しています。「エクソダス」は、「出エジプト」を表す言葉です(英語でも出エジプトはExodusです)。キリストの死は、人類を罪の奴隷から解放するための出エジプトであり、またキリストを信じる者たちにとっての死も、罪の世から御国に移される出エジプトと同じ意味を持つのです。エジプトで過酷な労働を強いられ、苦しくてうめき叫ぶイスラエルの民たちの声を神は聞き、モーセを遣わして彼らをその束縛から解放しました。キリストもご自身のいのちを捨てて苦しむ私たちを罪から解放し、また死を迎えることを恐怖から(約束の地を目指して旅立つ)希望に変えてくださいました。ですから、イエスが十字架で死なれる直前に3時間、出エジプトの直前のように全地が暗くなったことは、第2の出エジプトを象徴しているかのようです。
この3時間の暗やみの中で、人々はどうしていたでしょうか? 最初は恐怖でパニックに陥り、叫んだりわめいたりしたかもしれません。でも少し落ち着くにつれて、様々な思いが心に生じたことでしょう。「自分たちがしていることは本当に正しかったのか?」「キリストを十字架につける自分たちは何者なのか?」イエスの十字架上での言葉を思い起こし、自分自身を省みた人も少なからずいたことでしょう。人生の中で暗やみに覆(おお)われる日が、誰にもあります。その暗やみの期間は、立ち止まって自分の歩みを振り返る時です。それまで神に頼らず歩んできたことを反省し、神に立ち返り、これからの生き方を問い直す大切な時です。本当に大切なことは何か、従うべきお方がどなたかを、考え直す時です。暗やみのおかげで、あえて忙しい手を強制的に止められ、静まって考え神に祈らざるをえなくなるのです。イエスが十字架にかけられている3時間の暗やみの時に、人々はこの出来事の意味を問いかけられたことでしょう。その中から、イエスを信じる者たちも起きてきました。
この暗やみの時間が終わる3時ごろに、イエスの十字架上での第4の言葉がありました。
④ 「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マルコ15:34)。
このイエスの切実な叫びによって、暗やみが打ち破られます。イエスは神と等しい方でありながら、罪は犯しませんでしたが人間と同じ痛み苦しみを味わってくださいました。ダビデも苦しみの中でこの祈りをしています(詩篇22:1)。イエスは、肉体の痛みも心の苦痛も、私たちと同じように感じられたのです。父なる神からも人からも見捨てられるどん底の孤独にも耐えてくださいました。イエスは、この苦難の意味も目的もご存知でした。それでも「どうして?」と叫ばざるを得ない苦しみを経験してくださったのです。私たちが苦しい時、頭ではわかっていても「どうして?なぜ?」と叫ぶしかない時があります。イエスご自身が、人としてのその叫びをしてくださいました。ですから私たちは安心して同じ叫びを主にしていくことができるのです(へブル4: 15~16、5:7)。
⑤ 十字架上の5番目の言葉は、「わたしは渇く」(ヨハネ19:28)です。
死の直前で、肉体的にもイエスは、舌があごに貼りつくほどに口が渇いていました。同時に救いのために、この苦しみをも受けずにはいられないほどの、人々の魂への愛の渇きがありました。
⑥ 十字架上6番目の言葉は、「完了した」(ヨハネ19:30)です。
「ああ、もう何もかも終わりだ…」という絶望ではなく、「父なる神から託された人類救いのわざがここに完成した!」という勝利の宣言です。
<46節>
そして十字架上のイエスの7つの言葉の最後は、
⑦ 「父よ。わが霊を御手にゆだねます」です。
これも、「なすべきことはすべて終わり、あとは主の御手にすべて託します」という勝利の叫びです。イエスは、父なる神から遣わされ、父の御心を最後まで行い、その霊を神の御手にゆだねました。誰かを恨んだり憎むこともなく、神に従い通し、使命を果たし終えて安心してその霊を父の御手にお渡しになりました。
イエスが十字架にかかっておられるうちの約3時間、全地を暗やみが覆(おお)いました。この歴史的出来事の中で暗やみを経験した一人ひとりが、イエスの十字架の意味を問いかける時となりました。またイエスの十字架上の言葉の重みと、人間の罪の深さを感じた人もいたでしょう。
罪なき方がすべての人の罪を代わりに背負い、父なる神からも人からも見捨てられる孤独のどん底を味わいました。そして最後まで父の御心に従い、ついに人類の救いを完成し、勝利を叫ばれたのです。私たちに対する罪の呪いは、すべてイエスが代わりに受けてくださいました。救いの手順を、イエスがしっかりつけてくださったのです。あと私たち人間に問われているのは、この方の救いを受け入れるか否かだけです。イエスを信じる者は、死さえも第2の出エジプトとして、希望にあふれた旅立ちとなります。
罪なきキリストの壮絶な苦しみが、またその打ち傷が、私たちを癒すのです(イザヤ53:5~6)。イエスは十字架で、完全勝利を収めたのです。ハレルヤ!
|
 |
 4月1日 4月1日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「途方(とほう)にくれたとき」
ルカの福音書24:1~8 三浦真信牧師
ユダヤ教指導者たちのねたみによって、罪のないイエス様は十字架にかけられ、死んでお墓におさめられました。イエス様の葬(ほうむ)られたお墓は、ほら穴式になっていて入り口を大きな石でふさがれていました。複数の兵士たちが、交代でその墓を見張っていました。なぜならイエス様がかつて、ご自分が十字架で死なれ三日目によみがえることを弟子たちに伝えていたからです。誰かがイエス様の遺体(いたい)を盗んで「イエスがよみがえった」と言わないように見張っていたのです。
イエス様が死んでからしばらくたって、それまでイエス様についてきていた女性たちが、イエス様のお墓に向かっていきました。彼女たちは、イエス様に出会うまでは、暗く悲しい毎日を送っていました。イエス様に出会って、初めて本当の喜びを経験したのです。ですからイエス様が死んでしまって、とても悲しみました。彼女たちは、その愛するイエス様の遺体(いたい)に良い香りのする薬や油を塗ってあげようとして、お墓に向かいました。
ところがお墓に行く途中で、一つの問題に気がつきます。お墓の入り口をふさぐ石は、とても重くて大人の男性5~6人でようやく動かせるものでした。とても女性たちだけでは動かせません。彼女たちは、そのことをどうしようかと話しながらも、引き返すことはせずお墓に向かっていきました。それほどにイエス様の遺体(いたい)がおさめられているお墓に行きたいという強い思いがあったのでしょう。またこれまでイエス様のなさる数多くの奇跡を彼女たちは見てきました。病の人がいやされたり、イエス様の話を聞きに来ていた大勢の人たちを、わずかなパンと魚で満腹にしたり…だから心配なことがあっても、神様が必ず何とかしてくださるから大丈夫と信じていたのでしょう。
心配しながらもお墓に向かって歩いていくと、あの大きな墓の石はころがしてあって、墓の入り口が開いていました。彼女たちが驚いてお墓の中に入ると、イエス様のからだがありませんでした。彼女たちは途方(とほう)にくれてしまいます。イエス様が死なれたことでもすでに彼女たちは途方(とほう)にくれていました。イエス様にお会いして喜びの人生に変えられ、彼女たちはイエス様を信頼してずっとついてきたのです。そのイエス様が死んでしまったのですから、当然のことです。大切な人が突然いなくなってしまった時に、だれもが途方(とほう)にくれてしまいます。彼女たちは、イエス様が死んだことでも途方(とほう)にくれ、お墓に来てイエス様の遺体(いたい)がなくなっていて、また途方(とほう)にくれてしまいました。
するとまばゆいばかりの服を着たふたりの人が、彼女たちに近づいてきました。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、「なぜ生きているイエス様を、死んだ人がいるお墓の中で探すのですか?ここにイエス様はおられませんよ。イエス様が言われていた通りに、よみがえられたのです」とその人たちは伝えました。そして女性たちは、イエス様がそう言われたことをその時に思い出しました。
このあと彼女たちは、他のお弟子さんたちとイエス様にお会いします。もう二度と会えないと思っていたイエス様と会うことができて、とても喜びました。イエス様は、その後「世の終わりまでずっとあなたがたと共にいますよ」と言って天に上られました。そして今もイエス様を信じる人たちといっしょにいつもイエス様はいてくださいます。
途方(とほう)にくれる時、どうしてよいかわからず困っている時、大切な人がいなくなってしまって悲しみにくれる時にこそ、復活したイエス様にお出会いする時です。人とはいつか必ずお別れする時がきます。でもイエス様は永遠にいっしょにいてくださいます。人の気持ちはすぐに変わります。でもイエス様は、ずっと変わることなく私たちを愛してくださいます。だからイエス様は「私の愛の中にとどまりなさい」とおっしゃいました(ヨハネ福音書15:4~10)。ずっと変わることなく私たちを愛し、ずっと共にいてくださる方は、イエス様だけです。この死からもよみがえられたイエス様が、ずっと私たちを愛し、ずっと共にいてくださるから、苦しいことや途方(とほう)にくれることがあっても大丈夫です。
「私たちは四方八方から苦しめられますが、窮(きゅう)することはありません。途方(とほう)にくれていますが、行きづまることはありません」(Ⅱコリント4:8)。死からよみがえり、今も私たちと共にいてくださるイエス様の愛の中にとどまりましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()