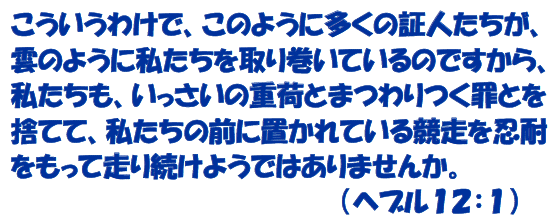6月24日 6月24日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「神のことばに立ち返る~無秩序と混乱の中で~」
士師記19章 三浦真信牧師
士師記19章~21章では、その時代に起きたギブアでの暴行事件と、それに対する全イスラエルの対応について記しています。
<1~10節>
「イスラエルに王がいなかった時代のこと」という前書きで始まります。これは、「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(17:6)ことを暗示しています。これから起きる悲惨な出来事、社会的腐敗の根本原因がここにあることをほのめかしています。
ひとりのレビ人に、そばめ(正妻以外の妻)がいました。神に仕えるレビ人に、そばめがいたことが珍しくないかのように書かれていることで、この時代の霊的暗黒を象徴しています。そのそばめが彼を嫌って、ベツレヘムにある実家に帰ってしまいます。恐らくそばめと正妻との間にトラブルがあったか、夫から暴力をふるわれたか(そばめが虐待されることがよくありました)でしょう。
4か月して、レビ人はそばめの実家に彼女を引き戻しに行きます。そばめの父は、4か月間娘をどうしたらよいかとやきもきしていたのでしょう、喜んで娘の夫を迎えます。父親はすぐに二人を返さず、彼らは4泊することになります。楽しい時間を共に過ごして、「娘を大切によろしく」と暗に伝えたのでしょう。5日目もレビ人は引き止められましたが、そばめを連れて彼女の実家を出発します。そして当時エブス人の地であったエルサレムに着きました。
<11~21節>
レビ人は、エルサレムが当時外国人の町であったため、エルサレムには留まらず、同じイスラエル人であるベニヤミン部族の町ギブアに泊まることにしました。当時同国人の旅人を泊めてもてなすことはよくありましたが、ギブアではレビ人たちを泊めてくれる人がなかなか見つかりませんでした。それでもようやく一人の老人が彼らに声をかけ、彼らを家に温かく迎え入れます。
<22~30節>
老人の家で楽しく彼らが食事をしていると、「よこしまな者」たちが、その家を取り囲んで戸をたたき続けました。「よこしまな者」は、へブル後原語は「ベリッヤアルの(邪悪な、滅びの)子ら」となっています。ギブアの町に住む皆がこのようであったわけではなく、特別「よこしまな者たち」と呼ばれる人たちが街を徘徊し、夜は広場が危険な状況でした(20節)。
そのよこしまな者たちは、老人の家にいたレビ人を引き出せと要求します。「あの男を知りたい」とは、レビ人を強姦したいということでした。老人は交換条件を出しますが、彼らは聞き入れず、ついにレビ人は「自分のそばめをつかんで、外の彼らのところへ」出しました(25節)。その結果そばめは彼らにレイプされ、夜通し暴行を加えられて亡くなるという悲惨な結末を迎えます。この「よこしまな者たち」は、人を人とみなしていません。自分の欲望を満足させるためなら、男であろうと女であろうと構わないのです。レイプ自体、相手が人格を持った人間であると認識したら、本来できないことです。でも悲しいことに、今もいつの時代にも起こっています。
ただこのギブアの町は、かなり道徳的に退廃していて、老人の対応からもこのようなことが日常茶飯事に起きていたことが感じられます。アブラハムの時代に、ソドムに住むロトの家が同じような人たちに囲まれました(創世記19章)。その時には、神の使いが彼らの目をくらませ、ロト一家はソドムの町から逃げ、その後ソドムの町は天からの硫黄の火で町ごと滅ぼされました。
レビ人は、そばめの遺体を切り、イスラエルの12部族に送りました。イスラエル中の人が、「こんなことは起こったこともなければ、見たこともない」(30節)と言いました。このことがきっかけで、この後イスラエルとベニヤミン族との全面戦争へと発展していきます。
とても痛ましい事件ですが、ここから神が何を語っておられるのでしょうか?
① 神のことばに立ち返ることの必要
士師の時代、「イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」(17:6)ため、これまでイスラエルが土台としてきた神のことばの大切さを示したり、国の目指すべき方向性を示す者がいませんでした。めいめいが自分の目に正しいと見えることが基準であったため、各基準がぶつかり混乱が起き、また無秩序な社会となっていきました。このような暗い社会の出来事を通して、神のことばを後ろにすることが霊的暗黒をもたらし、社会の腐敗を促進していくことを示しています。ですから、たえず神のことばに立ち返りましょう。聖書を本気で読みましょう。聖霊が主のことばを思い起こさせてくださいますが(ヨハネ福音書14:26)、聖書を読んでいなければ思い起こすこともできません。宗教改革の時にも、「聖書に帰ろう」が一つのスローガンでした。理解できないことにとらわれずに、聖書を通読しましょう。日々聖書を読んでいれば、聖霊が必要な時に思い起こさせてくださいます。みことばを相談相手にしましょう(詩篇119:24)。神は今も聖書のことばを通して、私たちの具体的な問題を解決してくださいます。みことばが私たちを生かします(詩篇119:50)。
② 人間の根本は皆同じであることを認めましょう。
この士師記で起きていることは、決して他人事ではありません。同じ罪の根が私たちの中にあるのです。ギブアのよこしまな者たちのように、自己中心が高じれば、自分の欲望を満足させるためなら何だってするように人はなりうるのです。人を人とも思わないようなことさえできてしまう罪の爆弾を抱えているのです。よこしまな者たちと同じ環境に自分の身を置いたら、同じことをしかねない要素を皆持っているのです。レビ人は、自分を守るためにそばめを犠牲にしました。何て冷たい男だと思いますが、いざとなれば自分を守ろう、自分を第一にかばおうという思いが働くのです。そのような自己中心と欲が蔓延(まんえん)していくと、社会全体も荒(すさ)んでいきます。
このような罪の根を抱えていることを認めて、キリストの十字架によって罪をきよめられ続けないと、何をするかわからないのが人間です。クリスチャンであっても、それは同じです。今日も明日も罪赦され、罪きよめられ続けていく者として、十字架のキリストを求めていきましょう。
どのような者であっても、キリストにより罪きよめられ続けている者たちを神は「地の塩」としていてくださり、社会の腐敗を防ぎ神の国を広げてくださっています(マタイ5:13)。そのような存在とされていることも感謝し、神の国の前進のために仕えましょう。
|
 |
 6月17日 6月17日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「人生の優先順位」
ルカの福音書23:53~56 三浦真信牧師
<53節>
ローマ総督ピラトは、アリマタヤのヨセフの願いを聞き入れ、イエスのからだを取り降ろし、墓に納めました。原則としてローマの死刑囚の死体は、葬(ほうむ)ることも持ち出すこともできませんでしたので、特例のことでした。
ヨセフがイエスのからだを納めたのは、「まだだれをも葬ったことのない墓」でした。それはヨセフが自分自身のために用意していた墓です(マタイ27:60)。誰の遺体も納めたことのない墓でした。イエスが十字架にかけられたゴルゴタの丘に一つの園があり、そこにこのお墓がありました(ヨハネの福音書19:41)。イエスがこの後墓からよみがえります。イエスの復活は、死のとげである罪に勝利したことの証でもあります。これは新しい出来事、人類史上初めてのことです。イエス・キリストを信じる者は、もう罪の結果である死を恐れなくてよいようになる出来事が、この墓で起こるのです。ですから「だれをも葬ったことのない」新しい墓が用意されたのはふさわしいことです。
ルカは、イエスの葬りにヨセフの名前しか記していませんが、ヨハネはもう1人の人物のことを記しています。それはニコデモです(ヨハネ19:38~42)。「前に、夜イエスのところに来たニコデモ」とは、ヨハネ福音書3章にある出来事です。ニコデモは、パリサイ人でユダヤ人指導者でした(ヨハネ3:1)。パリサイ人律法学者たちは、イエスの教えに反対していました。またイエスを死刑に決めたユダヤ人最高議会サンヘドリンの多くもパリサイ人でした。ですから、ニコデモは昼間堂々とイエスに質問できず、夜こっそりイエスのもとに行きました。律法学者であるニコデモは、律法を一生懸命行うことでは救いの確信を得ることができずにいました。そこでどうしたら神の国に入れるか、どうしたら救われるかをイエスに尋ねに来たのです。恐らくこの時から、イエスを求めるようになったのでしょう。ニコデモは、他のパリサイ人たちがイエスのことを批判している時に、イエスを弁明しています(ヨハネ7:45~53)。その時ニコデモは、イエスの弟子になっていたか、少なくともイエスに信頼を寄せていたことでしょう。
そのニコデモも、アリマタヤのヨセフ同様、イエスの十字架の死後はパリサイ人という立場もささげ、堂々とイエスのからだの葬(ほうむ)りに立ち会いました。他のパリサイ人仲間からどのように思われても、批判されても、パリサイ人を辞めさせられても構わないという覚悟でした。イエスのためなら、何を失っても構わないと思えるほどに、十字架のイエスの愛と力を受けたのです。
<54節>
「準備の日」とは、安息日の前日です(木曜夕方から金曜夕方)。当時は金曜夕方から土曜夕方までが安息日でした。キリスト復活後は、イエスがよみがえられた日曜日を安息日としています。安息日を迎えるために、前日から準備がなされていました。今も心からの礼拝をささげるためには、前日から準備をし、心を整えることが大事です。
イエスの死は金曜日の午後3時ごろです。もうすぐ安息日が始まろうとしていました。安息日に墓に葬ることはできなかったので、急いで墓に納める必要がありました。ですから、ヨセフの用意していた墓が、イエスが十字架にかけられた場所近くにあって良かったのです。これも神のご計画でした。
<55~56節>
「ガリラヤからイエスといっしょに出てきた女たち」はたくさんいました。その中には、マグダラのマリヤ、ヤコブとヨセフの母マリヤ、ゼベダイの子らの母がいました(マタイ27:55~56)。彼女らは、アリマタヤのヨセフ、ニコデモと共に、ヨセフが自分のために用意していた新しい墓にイエスのからだが納められる様子を見届けました。彼らは、イエスを墓に確かに納めたという事実の証人となったのです。
「香料と香油」は、腐敗する死体の消臭効果と死者に対する尊厳・弔意(ちょうい)を表すために、当時用いられました。つまりイエスのからだを、復活するからだとしてではなく、遺体として扱っていたのです。また古代ギリシャ・ユダヤでは、死体の管理は主に女性が行いました。
これまでキリストの弟子であることを隠していたアリマタヤのヨセフ、また夜こっそり人目を忍んでイエスに質問してきたパリサイ人ニコデモも、イエスの十字架の死後は、堂々とイエスのからだを引き取り、墓に手厚く葬りました。それによって、イエスの弟子であることを公に表明したのです。またイエスが確かに死なれ、墓に葬られたことの証人ともなりました。
イエスの十字架は、人々に力を与え、勇気を与え、そして何が本当に大切なことなのかを教えます。私たちは、生きている間にすべてのことができるわけではありません。限りある人生の中で、常に優先順位をつけながら、大切なことを最優先にしていきます。その優先順位を決める土台を何とするかが問われます。
ヨセフもニコデモも、十字架のキリストが人生の土台となりました。イエスの十字架の死を通して、彼らの優先順位の土台が変えられたのです。自分たちの立場も持ち物も、人の評価も二の次になりました。十字架のキリストが第一となったのです、大胆に自由にイエスのからだの引き (裏面に続く) 渡しを願い、墓に葬ることができました。これまで彼らを束縛(そくばく)していた自分の立場や持ち物から解放されたのです。何が本当に大切なのか、何を第一に人生を、また日常生活を考えていくのか、十字架のキリストを見てはっきりしたのです。これまで、これだけは失いたくないとしがみついていた社会的立場、財産、名誉…結局それらに束縛(そくばく)されていた不自由な自分に気がつき、それらよりもっと大切なものを優先する生き方に変えられたのです。
第一のものを第一として歩んでいくときには、すべて必要なものは神から与えられます。第一の者を二の次にしていると、あるものまで逆に失っていきます。神の国と神の義をまず第一に求めましょう(マタイ6:31~34)。それが聖書の鉄則です。それを第二にしているから、与えられていても満足できないのです。十字架のキリストを土台として、優先順位を決めましょう。実践していくときに、すべてが整えられていきます。
|
 |
 6月10日 6月10日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「神の国を待ち望んでいた議員」
ルカの福音書23:50~52 三浦真信牧師
<50節>
ヨセフという、立派で正しい議員がいました。「議員」というのは、ユダヤの司法最高議会サンヘドリン(70~71人で構成)の議員ということです。ヨセフは「りっぱな、正しい人」でした。律法をしっかり守り、正しいことを追及して生きていた人であり、周囲からもそう思われ尊敬されていた人であることがわかります。 <51節> この議員ヨセフは、「アリマタヤ」というユダヤの町出身で「金持ち」でした(マタイ27:57)。また「イエスの弟子」でした。ですからサンヘドリンの議員でありながらも、「議員たちの計画や行動には同意しなかった」のです。ユダヤの議員たちは、イエスを死刑にすると議会で全員一致で決めています(マルコ14:55、64)。イエスの弟子となっていたヨセフは、恐らくこの時の議会は欠席したのでしょう。イエスの弟子でしたから、当然サンヘドリンの他の議員の計画や行動には反対していました。しかし彼は自分がイエスの弟子であることを、他のユダヤ人を恐れて隠していました(ヨハネ福音書19:38)。自分がイエスの弟子であり、他の議員たちの考えに反対であることを堂々と言うことができませんでした。もし言ったら、自分の議員としての立場を失うかもしれない、身に危険が及ぶかもしれない、財産を没収されるかもしれない…そのような恐れから、イエスの弟子であることを隠していました。持っているからこそ、かえって不自由でした。立場もお金もなければ、堂々とキリストの弟子だと言えたかもしれません。
ヨセフにとって、キリストの弟子であるということは、自分のアイデンティティーでした。議員であることよりも、大切なことでした。しかしそれを言えないジレンマを抱えていたのです。
ヨセフは「神の国を待ち望んでいた」人でした。現状に決して満足をしていなかったのです。議員という立場もあり、お金もあり、人徳のある人でしたが、それで満たされていたわけではありませんでした。ユダヤ社会の混沌(こんとん)とした状況、救い主を抹殺(まっさつ)していく霊的鈍さ、ローマの支配にあえぎ苦しむ民たち、そして何よりもキリストの弟子でありながら、師であるキリストのために議会で声を上げられない自分に対する情けなさを感じながら、神の国を待ち望んでいたのです。弱さと痛みを抱えつつ、神の国を待ち望むヨセフでした。
<52節>
そのヨセフが、イエスの十字架の死後、大胆な行動に出ます。ローマ総督ポンテオ・ピラトのところに行って、イエスのからだの下げ渡しを願いました。十字架刑はローマの処刑方法で、ローマによって執行されたものです。ですから、ピラトに直接求めに行きました。このことは、当然ユダヤ人議員たちにも知られることです。「イエスの死刑を決めたサンヘドリンの一員でありながら、イエスを葬ることなどとんでもない裏切り行為だ」と言われるかもしれませんでした。
アリマタヤのヨセフは、イエスの十字架の死を目の当たりにし、あるいは十字架上のイエスの言葉を聞き、もう隠れキリシタン議員をやめました。「自分の立場も財産もどうなっても構わない…」と手放したのです。「キリストの弟子として、どうしてもイエスを手厚く葬りたい」と願い、ピラトに願ったヨセフの行動は、公の信仰表明でした。これまでは人を恐れ、立場や持ち物を失うことを恐れて言えなかった「キリストの弟子である」という事実を、自然に公に言えるように、十字架のキリストが変えてくださったのです。キリストの十字架の死が、ヨセフを変えました。
ローマの慣例では、死刑囚の遺体はそのまま十字架に晒(さら)されました。しかしユダヤの律法はそれを許しませんでした(申命記21:22~23)。死体を翌日まで木に残してはならないとあり、ヨセフはすぐにピラトにイエスのからだの下げ渡しを願ったのです。
この時に、ヨセフがユダヤ人最高議会サンヘドリンの議員であるという立場が用いられました。一般ユダヤ人でしたら、ローマの総督ピラトと直接会うことはできなかったでしょう。サンヘドリンの議員であったからこそ、ピラトと会うことが許され、またピラトも彼の願いを受け入れました。ヨセフとしては、サンヘドリンの議員でありながら、師であるイエスを守ることもできずにいたことを悔やみ、また自分がキリストの弟子であることも言えない情けなさを感じていました。議員でありながら、議員であることに葛藤を抱いていたのです。でもイエスの十字架の死後、何を失っても良いという覚悟でピラトのもとに行った時には、その議員であることが用いられたのです。
与えられている社会的立場、持ち物、能力などは、いざという時には主のために用いていただくためのものです。ただ出世するため、金持ちになるため、自分の欲を満足させるために技術や資格をとっても、それは地上にいる間の一時的なことで終わります。しかしそれを主のために用いていくときには、神の国のために後々まで祝福をもたらしていく出来事となるのです。ヨセフがイエスのからだを受けとり、墓に葬ることで、その後キリストの復活が起き、それは今に至るまで人々を新しく造り変え、全地に神の国が広がる出来事へと続いているのです。
日ごろは仕事や生活のために用いていても、いざという時のために、神が一人ひとりに与え ておられるものがあるのです。与えられている立場、能力、技術、資格、時間、体力、忍耐…いざという時に主のために用いていくためのものです。
アリマタヤのヨセフは、地位も財産もあり、立派で正しい生き方をしていた人でした。3拍子揃(そろ)っていて、人からはうらやましがられていたかもしれません。でも彼の心は決して満足せず、神の国を待ち望んでいました。そしてキリストに出会って心満たされ、弟子になったのです。でもキリストの弟子になった後も、自分の立場や持ち物を失うことや人を恐れて、キリストの弟子であることを公に言えず、また議会のキリスト抹殺(まっさつ)計画を知りながらも、面と向かって反対することもできずにいました。いざとなれば、自分を守るために真実も言えない弱さを抱えていました。でもその弱さが、キリストとの関係を深めるものとなりました。
キリストの弟子になってからも、私たちは完璧になるわけではありません。グレーゾーンな部分があり、なかなか捨てられない弱さがあります。でもそのことを認めてなお主のあわれみを求めていくなら、その弱さの場所で神の愛を知り、神との濃密な関係へと導かれていくのです。その弱さを認めずに、自分の強気で覆(おお)ったりかばっていくと、いよいよ頑(かたく)なになり、律法学者パリサイ人たちのように、歪(いびつ)で偽善的で表面だけの、いのちのない信仰生活になってしまいます。キリストの弟子でありながら、「ここに触れられると手も足も出ない」という自分の弱さを認めて主にすがり、そこで主のあわれみをなお求めていくなら、主と親密な関係を持つことができます。「この弱さをもつ私のためにイエス・キリストは十字架で死んでくださった」と、キリストへの感謝が湧き上がってきます。十字架のことばこそ、神の力なのです(Ⅰコリント1:18)。神の国を待ち望み、自分の弱さや社会の現状に悲しみ痛む者にとって、「十字架で死なれたキリストこそ救い主、神の力」なのです。「キリスト・イエスは罪人を救うためにこの世に来られた」(Ⅰテモテ1:15)のです。キリストの弟子となった後は、キリストの赦し(裁きではなく)を受け続ける罪人なのです。ハレルヤ!
|
 |
 6月3日 6月3日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「多くのキリストの証人たち」-召天者記念礼拝-
ピリピ人への手紙3:7~21 三浦真信牧師
キリストに出会った召天者の方々の地上の歩みがどのようなものであったのかを、聖書を通して確認しましょう。
<①執着していたものから解放され続ける人生(7~9節)>
この手紙を書いたパウロは、学歴もあり家柄も良く、立派な生き方をしてきました。律法をしっかり学び良く守ることにおいて、自信を持っていました。しかし律法を守ることに重点を置くあまり、キリストを信じるだけで救われるというクリスチャンの生き方を否定し、クリスチャンを迫害していました。努力して頑張れば人は完璧(かんぺき)な生き方ができ、神からも正しいとお墨付きをいただける生き方ができると、自信を持っていたのです。そのパウロにとって、自分の罪を認めてキリストを信じれば救われるという教えは受け入れ難く、またキリストを神の子とすること自体が、神への冒涜(ぼうとく)と思えたのです。
しかしパウロがクリスチャンを迫害していたある日、復活のキリストご自身がパウロに近づいてきて「どうして私を迫害するのか」と声をかけられます。その時から、パウロの人生は180度変わりました。キリストに出会ってから、もう一度旧約聖書を読み返してみると、旧約に出てくる信仰の人たちも、最期まで不完全な人間であったことを知ります。人間がどれほど頑張っても、人間の力で神の基準には到達できないこと、だからこそキリストの救いなしには誰一人救われないことを理解するようになりました。
誰よりもパウロ自身が、救われるにふさわしくない罪深い者であることを認識するようになります。どれほど立派な生き方をしてきた人でも、人から良い人だとほめられる人でも、神の前に立つ時には人からの評価など吹っ飛んでしまいます。パウロも、キリストに出会って、それまでの「自分は完璧だ、神からも人からも認められる生き方をしてきた」という自信は消え去りました(ローマ7:15~8:2)。神の前に罪深い者であることを認めた時に、今度はキリストがその罪から解放してくださったのです。ですから、罪を認めて悩み果てるのではなく、むしろ罪からの救い主を送ってくださった神への感謝が湧き上がってきました。キリストの素晴らしさを知った結果、これまで執着してきたプライドなどちっぽけな「ちりあくた」のように思えるほどになったのです。
キリストの素晴らしさが心の中で大きくなって、今まで大切な宝のように思ってきたものが、小さなものとなりました。「キリストの中にある者と認められたこと」「キリストを信じる信仰による義を持つことができること」「神から与えられる義を持つことができること」が、大きな望みとなりました。人間の行いによって得られる正しさは不完全で、不安定です。でもキリストによって神から与えられる義は、完全で永遠に変わりません。人間の側の状態によらないので、安心で望みがあります。
たえず自分の心の中にうごめく罪があります。こうすれば良いとわかっていても、そうできない自分がいます。神の言葉から外れている自分の姿にたえず気づきます。醜(みにく)いことばかり考える自分がいます。もしもそのような自分ではなくなって、心の中まできれいな思いだけにならなければ救われないとしたら、人は絶望するか、表面だけきれいに整えて偽善的に生きるしかありません。でも神はそのどちらでもなく、「キリストを信じるだけでよい」と言ってくださったのです。私たちの罪汚れに代わって、神の子キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえり、このキリストを信じるだけで神の完全な義の衣を着せてくださると約束してくださいました。地上にある限りは罪の残骸(ざんがい)を持っています。でも神の怒りを背負い続ける罪人としてではなく、神に赦され続ける罪人として生きる望みが与えられているのです。召天者の皆様もこの望みを抱きながら、どこまでも不完全なまま神が与えてくださる完全な義を求めながら、様々な執着心から解放され続けて人生を歩まれました。
<②目標を目ざして一心に走り続けた人生(10~14節)>
パウロは、復活のキリストに出会って、キリストが今も生きておられることを身をもって体験しました。キリストを伝える中で、弱さの中にある時、大変な状況にある時ほど、驚くべきキリストの復活の力を体験してきたのです。それにもかかわらず、パウロは「どうにかして死者の中からの復活に達したい」と、なお復活のキリストと一つになることを追及していることを告白しています。「キリストの復活の力はこの程度ではない、まだまだ自分はその力を体験していない」と、復活のキリストの力と一つになることを目標として前に向かって進み続けました。キリストの復活の力をもっと知りたい、もっとキリストの愛に満たされたいと、現状に満足せず、悟ったような顔をせず、キリストを求め続けました。多くの信仰者たちも、そのように最期の時までキリストを追い求めて走り続けたのです。
<③天の国籍を待ち望む人生(20~21節)>
最終ゴールがはっきりしている人生は安心です。安心して、地上ですべきことに専念できます。万物をお造りになった神は、「万物をご自身に従わせることのできる御力によって」私たちの地上のからだを、天において「ご自身の栄光のからだと同じ姿」に変えてくださいます。地上の体は歳と共に衰え、また病気や怪我(けが)もします。しかし天に用意されている復活の体は、朽ちることも病気をすることもありません。また罪が完全に取り除かれ、完全な義の衣を着せていただけるのです。
天の国籍をはっきりして、地上の生活を旅人として生きるなら、地上のあらゆるものに執着せず、とらわれず、軽やかな歩みとなっていきます。やがてキリストと同じ栄光のからだに変えられるという望みは、今の苦しみをも「取るに足りないもの」と思えるようにします(ローマ8:18)。キリストと共に歩んだ人々は、将来与えられるこの栄光を待ち望んで、試練をも乗り越えていきました。
私たちは、多くのキリストに出会った証人たちから、その証言を聞いてきました。またこれからも聞くことができます(へブル12:1)。生きている限り、心の重荷や罪がまとわりついてきます。それでも、「信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないで」(へブル12:2)生きましょう。天のゴールを目指し、地上で目の前に置かれている競走を走り続けましょう。どこまでも地上では不完全ですが、やがて救いが完成する日を待ち望みつつ、キリストを見上げて前進しましょう。人生の苦しみの中でも、キリストを見上げて生きる喜びを証言してくださった人々に倣(なら)って、義の栄冠を目ざしてまいりましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()