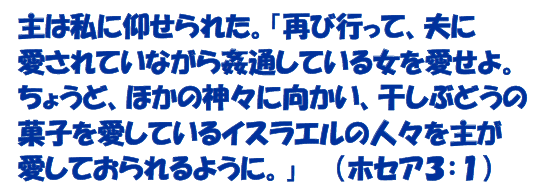7月29日 7月29日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「魂の夜を越えて」
ローマ人への手紙8:28他
陣内俊師・「声なき者の友」の輪(FVI)事務局長
<発病>
2013年12月から2015年12月までの丸2年間、燃え尽きに伴う鬱(うつ)病となり、療養をしました。病気の前兆として2011年ごろから、疲れが取れない、物忘れが多くなる、話している人の意味を把握するのに時間がかかるなどの兆候が出ていました。読んでいる文章の漢字の角が自分の神経に刺さるような感覚さえ覚えるようになり、病院に行かざるを得なくなりました。
当初は2週間くらい休めば仕事に戻れると考えていたのですが、結局2年間休むことになりました。最初の半年は「抵抗期」で、病気を受け入れられない時期でした。次第に本を読めるようになったので、本からの知識を得て、この状態から脱するためにジョギングを試みたら、人とすれ違うのが怖くてどうにもならない。コンビニに入ると店員と対するのが怖い、対人恐怖症の状態です。それから、心の深いところで病気を受け入れる「受容期」、これが1年くらい続きました。そして「回復期」となり、 1週間に2時間くらいは幸せの感情を思い出せるようになった時期です。鬱(うつ)病はセロトニンという脳内物質の枯渇によると言われます。自分の好きなものが絶望にしか思えなくなります。通常処方される薬が合わなかったので、漢方薬を処方されました。3つのカウンセリングを受けました。燃え尽きになった牧師をカウンセリングした経験のある人、牧師でありカウンセラーである人、全く別の方法を取る人です。
<病気の時に興味をひいた話>
闘病中に見たDVDの中の「深い穴に落ちた人の話」が心に残りました。深い穴に落ちて出ることができず絶望した人、その穴の前を3人の人が通ります。1人目の人は「頑張れ、前向きに考えろ」と声をかけて通り過ぎました。2人目の人は、紙にみことばを書いて落とし、あなたのために祈っていると言って去って行きました。3人目の人はその穴の中に飛び込んできて、「私はかつてこの穴の中にいた事があり、ここの絶望を知っている。出る方法を知っているから、この穴から出よう」と言ったというのです。DVDはここで終わるので解決法が分からず、釈然としない思いを持ちつつも、病気の2年間この話が思い起こされました。
聖書に登場する、絶望した人物を友人のように感じました。全財産と子供を一夜にして失い、自身も重い皮膚病にかかったヨブ。神様に反抗し3日間魚のお腹の中にいたヨナ。そして涙の預言者エレミヤ。エレミヤは文字通り、穴の中に落ちた人です(エレミヤ38:6、哀歌3章14〜24)。この哀歌の箇所を、聖書を読んだことのない精神科医に見せたら、おそらく鬱(うつ)病患者との診断を下すことでしょう。
<鬱(うつ)病になって分かったこと>
自分が当事者になってみて分かったことは、次のようなことです。
① 鬱(うつ)病になるというのは、気分の落ち込みや「鬱(うつ)っぽい感じ」の延長線上にあるのではないのです。風邪とマラリアが違うように、全く次元が違うものです。朝、起き上がって布団を押し上げる、コーヒーを入れるということすら、「気力が出ない」。朝ご飯を食べるかと聞かれて、その判断ができなくてパニックになる。コンビニに行くと全身から汗が止まらない。
② 鬱(うつ)病の自殺については、「逃げている、心が弱いから」ではありません。高層ビル火災で上階に取り残された人が、迫って来る火に、どうしようもなくなって飛び降りてしまうのと同じような状況です。インフルエンザの症状の10倍の苦しみが、ずっと続くのだとも言われます。
③ 誰でも鬱(うつ)病になりうる。精神論では治すことができません。教会の中で、鬱(うつ)病の人に対して「信仰が足りない、み言葉をもっと聞いて」と勧めるなら、病人を更に追い詰めることになります。
<回復のきっかけ>
回復のヒントとなった一つには、イタリアの諺(ことわざ)の「どん底に落ちたら、地面を掘れ」があります。また、鬱(うつ)病を経験した人の手記を読むようになり、その中でヘンリ・ナウエン司祭に関する「傷ついた癒し人」という著書を読みました。これらを通して、療養の後期には、ひたすら休むことと、徹底して苦しみの中にとどまる事にしたのです。
病気は不運な出来事、地雷を踏んでしまったようなものと思っていましたが、2015年の春頃には宝くじに当たったようなものと思えるようになりました。
<価値観の転換>
私たちが心の中に価値観として根強く持っているのは、次のようなものです。 病気<健康 挫折<成功 休息<能率 できない<できる
信仰が弱い<信仰が強い 【 注: < は、右側が左側より大きい(良い)ことを示す記号】
このような、近代の右肩上がりの価値体系を、別の見方に変えられるかどうかという事です。
北海道にいる友人に、疾患、障がいを持つ子供専門の病院長がいて、彼は幼くして亡くなることの多い彼らの親から「この子の人生は何なのか」と問われると返答に窮していました。ある時から、障がい者が生きているだけで、社会を変革しつつあるのだと考えられるようになったと言いました。病気は乗り越えるべき障がいではなく、友達のようなもの、挫折は宝かもしれない、と考えられるようになったのです。
「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」(ローマ書8:28)
ここでの「益」の意味を、以前は「災い転じて福となす」という諺(ことわざ)のように、マイナスの事からプラスの事に転じるものと解釈していました。夜空の星には喜びや希望、成功、幸福を示す黄色い星があり、また病気、悲しみ、挫折などを示す黒い星もあります。私は、黄色い星だけを結んで星座を作ろうとしていましたが、この黄色い星と黒い星の両方を結んだより大きい星座、それがここのみことばで言う「益」なのではないかと思うようになりました。社会や教会の中には問題が必ずあり問題を起こす人がいますが、それらが社会や教会に必要な要素なのではないかと考えるように変わりました。私の人生における価値観が、完全性から全体性へと移行したのです。
<病気により教えられた事>
この病気によって、以下のことを教わりました。
① 人生は作品という視点が与えられた。それに奥行き・陰影を持たせるのが、死、老、苦しみ、弱さ、挫折・・・。
② 近代の右肩上がりの価値観から、新たな物語への変化を与える。
③ 完全性から全体性への移行。完全性を追求する人には病気は害でしかない。全体性の視点から見ると、病気になる人生は宝ともなり得る。
エレミヤは穴に投げ込まれて苦しんだ後、超自然的な出来事によってではなく、友人に助けてもらいました(エレミヤ38:12〜13)。私の病気の回復には、友人、妻、カンセラー、教会員などから大きな助けを受けました。神様は明日の教会を描いていますが、そこで必要とされるのは、能力や若さ、信仰だけでなく、弱さ、老い・病、不信仰と葛藤する日々など多岐にわたります。全体性と言う観点から見ると、捨てるものは一つも無いのです。
(要約まとめ:田内博)
|
 |
 7月22日 7月22日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「力ある者たちの敗北」
士師記20:1~48 三浦真信牧師
<1~7節>
ベニヤミン族の町ギブアで、レビ人のそばめがよこしまな者たちに暴行され死にました(19章)。レビ人は、彼らの卑劣で恥ずべき行為をイスラエル中に知らせるため、そばめの遺体をイスラエル各部族に送ります。そしてイスラエルの全部族、民のかしらたち、40万の歩兵たちがミツパ(ギブアから5キロの場所)に集まり、レビ人から事件の真相を聞きます。
<8~16節>
全イスラエル部族は、ベニヤミン族にレビ人のそばめを暴行死させたよこしまな者たちを引き渡すよう要求しますが、ベニヤミン族はそれを拒否し、全イスラエルと戦うためにギブアに集まりました。ベニヤミン族は、2万6千人の剣を使う者を招集し、その他にギブアの住民から700人の精鋭を召集します。合計2万6千7百人の兵士の中には、700人の左ききの精鋭がいました。「彼らはみな、一本の毛を狙って石を投げて、失敗することがなかった」というほどの実力がありました(士師記3:15、Ⅰ歴代誌12:2)。
<17~28節>
全イスラエル軍はベテルに上り、ベニヤミン族と戦います。全イスラエル軍は40万人と人数が圧倒的に多いにもかかわらず、初日も2日目も大敗してしまいます。彼らの中には、自分たちは人数も多いし、悪いことをしたのはベニヤミン族だから、勝って当然という思いがあったかもしれません。でも2度の敗北で、彼らの自尊心が砕かれ、自分たちの力や兵士の数によってではなく、神に全面的により頼むべきことを学びました。
2日目の戦いのあと、彼らは主の前にすわり、夕方まで断食をし、いけにえを主の前にささげて礼拝します。そして主は「あす、彼ら(ベニヤミン族)をあなたがたの手に渡す」と宣言します。
<29~32節>
イスラエルは、ギブアの町の周りに伏兵(ふくへい)(奇襲攻撃のために密かに隠れている軍勢)を置きます。そして全イスラル軍は3日目にベニヤミン族を攻め上り、ベニヤミン族が彼らを迎え撃つために町を出てくると、おびき出すために来た道を引き返して逃げていきます。ベニヤミン族は、「彼らは最初のときのようにわれわれに打ち負かされる」と2日間戦いで優勢だったことで自信を持っていました(32、39節)。
<33~48節>
全イスラエル軍は、伏兵(ふくへい)たちを信頼して引き返します。ベニヤミン族は、退却した全イスラエル軍を追いかけ、その隙(すき)にギブア周辺にいた伏兵たちがギブアの町に突入します。そして町が壊滅すると、合図ののろし(煙)を上げます。その合図を見て、逃げたはずの全イスラエル軍はまたギブアの方に引き返してきます。ベニヤミン族は荒野に逃げますが、伏兵たちや町々から出て来た者たちも合流してベニヤミン族を追い詰め、彼らを包囲し、最終的に2万5千人のベニヤミン族が打ち殺されます。そして600人はリモンの岩に逃げ込み4か月間そこで身を隠しました。全ベニヤミン族の兵士2万6千7百人のうちのほとんどがこの日倒れました。
この個所から、3つのことを心に留めましょう。
① 神は敗北を通してご自分の民を砕かれます。
全イスラエルは、罪を犯したのはベニヤミン族であり、自分たちは正しいと思っていました。しかしギブアに攻め上った初日は2万2千人殺され(21節)、翌日は1万8千人がベニヤミン族に殺されます(25節)。両日とも全イスラエル軍は主に祈り、主が戦いに出るように命じています。それにもかかわらず敗北しました。神のことばに従ったのに、なぜ2日間敗北したのでしょうか?彼らはその敗北を通して、自分たちが正しいからでも人数が多いからでもなく、ただ神が共におられ、神が戦われる戦いであるから勝利することを学びます。自分たちの正しさや力に一切よらず、神によって勝利がもたらされるのです。負けることで、自分たちの心の高ぶりを砕かれ、ただ主に従う者とされたのです。
私たちが敗北を経験する時、思うようにことが進まずがっかりする時、それは神の御前に私たちが砕かれる時です。逆にベニヤミン族が最初2日間の勝利によっておごり高ぶったように(32,39節)、成功している時や順調に進んでいる時には心が高ぶり、思わぬ痛みを経験することもあります。順調な時にはいよいよ主の御前にへりくだり、敗北したときには主の砕きを受けていきましょう。
② 神を信頼するゆえに人を信頼しましょう。
全イスラエルは、ギブア周辺に置いた伏兵(ふくへい)を信頼したので、安心してベテルに引き返すことができました(36節)。伏兵たちを信頼できずに、「やはり自分たちが直接戦わなければ負けてしまう…」と言って退却しなかったら、この戦いで勝つことはできなかったでしょう。
彼らが伏兵を信頼できたのは、神を信頼したからです。神が「攻め上(のぼ)れ。あす、彼らをあなたがたの手に渡す」と全イスラエルに言われたことを信じたからです。詐欺が横行し、教会にも異端が紛れ込む時代ですから、やみくもに誰でも信じてよいわけではありませんが、神ご自身が託された兄姉であるなら、神に信頼してその人をも信頼していくことも大切です。逆に神が信じられないと、誰も信じられなくなってしまうことがあります。「この人は自分に危害を加えるのではないか、今は親しくしていてもやがて裏切るのではないか…」となっていきます。「神が立ててくださったから、また神が自分の近くに置いてくださった人だから」という神への信頼によって、その人に任せていく時があります。神への信頼が、人への信頼につながっていきます。神が信頼できないと、次々に人に不信感を持つようになり、良い関係が築けず、折角の賜物が生かせないことが良くあります。ある時には、神を信頼するゆえに、神が遣わし身近に置いてくださった人をも信頼していきましょう。
③ 神の前では力ある者も敗れます。
ベニヤミン族には、左ききの精鋭という強者たちがいました(16節)。そして全イスラエルとの戦いでも、最初の2日間はベニヤミン族が優勢でした。しかし「主がイスラエルによってベニヤミンを打ったので」(35節)、最終的にベニヤミン族は大敗します。ベニヤミン族の兵士たちは「力ある者たちであった」と繰り返し記されています(44、46節)が、それにもかかわらず彼らが敗北したのは、主が彼らを打たれたからです。
主が戦われる時には、敵がどれほど力があっても、すごい武器があっても、関係ありません。絶対勝てないと思う戦いに、主が共におられて勝つことがあります。逆に自信満々で臨んだのに、完敗することもあります。私たちの勝利は、すごい武器を用意したとか、人数をたくさん集めたということには必ずしもよらないのです(詩篇33:16~18)。「主の手にどれだけ謙虚に頼ったか」が問われていきます。私たちが誇りとするのは「私たちの神、主の御名」だけなのです(詩篇20:7)。神の御手にいよいよ依り頼みましょう。
|
 |
 7月15日 7月15日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「主イエスとの食卓」
ルカの福音書24:33~43 三浦真信牧師
<33節>
エマオ途上で復活したイエスに出会った2人の弟子は、すぐにエルサレムに引き返します。エルサレムからエマオに向かっていた時には暗い顔をしていた2人ですが、復活の主イエスに出会ったあと、エマオからエルサレムに向かう道は、喜びと希望に溢れていたことでしょう。もしイエスが十字架で死なれて終わりでしたら、私たちは実質のないものを信じていることになり、遺体を神格化する空しい信仰になってしまいます。そして相変わらず罪の中でもがき苦しむことになります(Ⅰコリント15:14、17)。しかしイエスは確かによみがえられました。そして今も、永遠に生きておられる神なのです。この方を信じる者は、今も日々主イエスにお出会いすることができるので、どのような時にも望みを失うことはありません。
<34節>
2人の弟子がエルサレムに戻ってみると、イエスの弟子たちがすでに集まっていました。エルサレムにいた弟子たちは、「ほんとうに主はよみがえって、シモンにお姿を現された」と報告しました。イエスがよみがえったことを御使いから聞いた女性たちの話を聞いて、シモン・ペテロは、すぐに墓に行きました(12節)。恐らくその後に、イエスはシモン・ペテロに復活の姿を現したのでしょう。パウロも、まずケパ(ペテロ)に復活のキリストが現われて、その後500人以上の兄弟たちに同時に現れたことを伝えています(Ⅰコリント15:5~6)。ペテロと、エマオに向かう2人の弟子たちに、ほぼ同じ時間帯にイエスは姿を現したのでしょう。復活したイエスのからだは、時間空間に制約されるものではありません。同時に違う場所にいることができるのです。また今も同時に世界中の人の祈りを聞き、お応えになることができる方です。
復活の主イエスは、シモン・ペテロ、エマオ途上の2人の弟子たちにその姿を現しましたが、それよりも前にマグダラのマリヤにその姿を現しました(ヨハネ福音書20章)。
<35節>
エルサレムの弟子たちは、主イエスが本当によみがえってシモン・ペテロに姿を現されたことを報告し、エマオから引き返して来た2人の弟子も、エマオに行く途中からイエスがいっしょに歩いてくださり、聖書を説き明かしてくださって心の内が熱く燃やされたこと、食事の時にパンを裂かれた時にイエスだとわかったことなどを報告しました。イエスの復活の事実が次々に証言され、弟子たちは驚きと喜びに包まれます。
<36節>
弟子たちが、復活のイエスのことを話題にしている時に、「イエスご自身が彼らの真ん中に立たれ」ました。今もイエスについて話しているところに、復活の主イエスは立たれます。2人、3人でもイエスのことを分かち合っている場所に、主イエスは立っていてくださるのです。そこで私たちの心を燃やしてくださいます。主イエスを崇め礼拝する場所に、復活の主は立たれます。復活の主イエスが、私たちの真ん中に立っておられることを信じて、生ける主を礼拝しましょう。
脚注にもありますが、ここで主イエスは「あなたがたに平安があるように」と言われました(ヨハネ福音書20:19~23)。ユダヤ人がイエスの弟子であることで自分たちを捕まえにくるかもしれないと恐れて、戸と鍵を閉め切っていた部屋に、復活の主イエスは立たれました。そして2度「平安があなたがたにあるように」と言われます。ここの「平安」は、イエスがかつて「わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません」(ヨハネ福音書14:27)と言われた「平安」と同じ言葉です。人を恐れて閉じこもっていた弟子たちに、イエスご自身が平安を与えてくださると約束してくださいました。
<37~38節>
イエスが復活された事実をこれまで分かち合っていたにもかかわらず、いざ復活の主がその場に現れると、まるで亡霊でも見るかのように弟子たちは驚き恐れました。「なぜ疑いがあなたがたの心の中に浮かんでくるのか」(原文)と主は問いかけます。「疑い」は、イエスの復活を信じないことです。復活の主が姿を現されたことをたった今まで皆で喜んでいたはずなのに、いざそこに主が来られると取り乱してしまうのは、この時の弟子たちだけではありません。私たちも、みことばは真実だと兄弟姉妹と分かち合ったり、主のみわざを讃美しているのに、いざ主のみわざが起こると、「偶然だよ」とか、「このようなことが起きるはずがない」と、主のみわざと関係のない出来事にしてしまう頑なさ、不信仰があるのです。
<39節>
すぐに疑い取り乱す者にもイエスは愛想つかさず、「わたしの手やわたしの足を見なさい」と、なお主が語られた復活が事実となったことを示し続けてくださいます。主イエスは、弟子たちにわかる形で現れてくださいました。透明人間みたいな姿ではなく、肉体ごと復活してくださったのです。見て触ってわかる形でよみがえられたのです(締め切った部屋に姿を現わしたり、同時に違う場所に姿を現わしたり、通常の肉体とは違います)。
<40節(脚注)>
写本によってはこの文がないのですが、多くの写本には記されており、またヨハネ福音書20:20にもあるため、新改訳2017では本文に載っています。イエスは、弟子たちに十字架の釘跡がある手と足をお見せになりました。
その時にその場にいなかった弟子のトマスは、イエスの十字架の釘跡を見て触らないと決して信じないと言っていました。しかしその8日後にイエスはトマスにも現れて、「見ずに信じる者は幸いである」と言われました(ヨハネ福音書20:24~29)。信仰とは、まだ見ていないことを、主がそうおっしゃるからという理由で信じることです。見える状況ではなく、みことばの方を信じていくことです。主イエスがよみがえると言われたのだから、それを見なくても信じてほしいとイエスは願っておられます。でも弟子たちも私たちも弱いため、なかなか信じられません。ですから主は様々な出来事を通して、「見ずに信じる者」となるように訓練をしてくださっているのです。今見ている事象がすべてではなく、主のことばが必ず事実となることを信じるようになってほしいと、願っておられるのです。その信仰を与えるために、様々な試練を通して訓練をしてくださっているのです。
<41~43節>
よみがえられた主イエスの手足を見て、嬉しいけどまだ半信半疑の弟子たちに、なおイエスは復活の事実をわからせるために、弟子たちが持ってきた「焼いた魚」を召しあがりました。「食事をする」という行為は、肉体の復活を示すだけでなく、かつてのキリストと弟子たちとの親しい食卓の交わりを思い起こさせる行為でもありました(5:29、22:14など)。イエスと共に食事をしたということは、ただお腹を満たしたというだけではなく、そこで心を開いて本音の交わりをしたことであり、食事をしながら心がうちに燃えるような経験でもあったのです。今も主イエスは、「だれでもわたしの声を聞いて戸を開けるなら、わたしは彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしと食事をする」(ヨハネ黙示録3:20)と言われます。私たちが今日心を開いて主イエスを迎えるなら、キリストとの親しい食事の交わりを体験できるのです。
イエスと水入らずの食事も楽しいし、主イエスを真ん中にして兄弟姉妹と共にする食事の交わりも力と励ましを得ます。食事をするたびに、復活の主がそこにおられることを覚えましょう。ただお腹を満たすためではなく、食事をしながら復活の主を覚えるのです。愛餐会、ランチタイム、家族や知人との食事の席でも、復活の主を覚えましょう。
私たちの罪咎をすべて担って十字架で死なれたイエス・キリストは、たしかに死からよみがえり、今もそして永遠に生きておられます。信じられない者にも信じられるように、その復活の事実を示し続けてくださいます。すぐに様々な出来事で不安や恐れに包まれ暗い心になる者をも、みことばでまた熱く燃やしてくださり、また兄弟姉妹との交わりの真ん中に立って励ましてくださいます。私たちが御国に行くまで、地上の旅にずっと同伴してくださっています。この復活の主イエスとの親しい交わり、また主を愛する者たちが生けるキリストを中心にしている食事の交わりを通して、復活の力を受けることができます。主イエスとの食卓を楽しみましょう。
|
 |
 7月8日 7月8日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「心が燃えるイエスのことば」
ルカの福音書24:13~32 三浦真信牧師
<13~14節>
イエスがよみがえられた日に、ふたりの弟子がエマオという村に向かっていました。ひとりの名は「クレオパ」でした(18節)。クレオパは、ギリシャ語で「クレオパトロス」の短縮形です。同じく「クロパ」も、クレオパトロスの短縮形です。イエスの十字架のそばに立っていた女性で、「クロパの妻マリヤ」という人がいました(ヨハネ福音書19:25)。イエスが十字架にかけられた時にすぐ側にいたのですから、彼女もイエスの弟子でしょう。もしこの「クロパ」と、「クレオパ」が同一人物でしたら、エマオ途上のふたりの弟子は、クロパ(クレオパ)とその妻マリヤという可能性もあります。
ふたりの弟子は、エルサレムで起きたイエスの出来事について話し合いながら、エマオに向かって歩いていました。
<15~16節>
なぜイエスのからだを納めた墓は空になっていたのか、イエスは本当に復活したのか…と話し合ったり論じ合っているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らとともに道を歩いておられました。エマオに着くまで、この同伴者がイエスだとふたりはわかりませんでした。彼らの目が「さえぎられていた」からです。でも彼らが気づかなくても、復活の主イエスは、彼らと共にこの道を歩んでくださっていたのです。私たちも、やがて復活の主イエスと顔と顔を合わせてお会いする日がきます。その日まで、イエスは私たちの人生の同伴者として共に歩いてくださるのです。私たちが意識していてもいなくても、変わりなく主イエスは共に道を歩いてくださっているのです。
エルサレムで起きたイエスの出来事に心がとらわれて、彼らの目はさえぎられていました。心が様々なことにとらわれていると、イエスが一緒にいてくださることがわからなくなってしまうことがあります。こちらがパニックになっていても、主がおられることを忘れていても、主イエスは変わりなく共にいてくださり、御声をかけ続けてくださっています。
<17~18節>
ふたりと一緒に歩いていたイエスは、彼らが話していることが何のことかを尋ねます。ふたりは暗い顔をして、近頃エルサレムで起きたイエスの出来事を「あなただけが知らなかったのですか」と言います。「あなただけが」とは、とても強い言葉です。でも実際は、この「あなた(イエス)」こそ、誰よりも復活の事実を知っておられる方なのです。
<19~24節>
ふたりの弟子たちは、イエスのことを「行いにもことばにも力のある預言者」であり、「この方こそイスラエルを贖ってくださるはずと望みをかけていた」と話しました。その望みが、イエスの死によって失せてしまったということです。彼らも他の弟子たちのように、イエスがイスラエルをローマ帝国の支配から解放する政治的メシヤとして期待していました。イエスの死によってがっかりしていたところに、仲間の女性たちが墓に着くとイエスのからだはなく、御使いによりイエスが復活したことを告げられたと聞いて、ふたりは気が動転していました。
<25節>
ふたりの話を聞いて、イエスは「ああ、愚かな人たち、心が愚かで鈍い人たち」と言って、旧約聖書からこの出来事を説き明かしました。決してふたりを馬鹿にしているのではなく、真理に気づいてほしいために、強い口調で言われたのです。イエスは、鈍い私たちに聖書の事実をわからせるため、ある時強い口調で語られたり、ショック療法によって気づかせてくださいます。それによって、私たちの心の目をさえぎっている様々な思い煩い、とらわれなどを取り除いてくださり、みことばの事実を見せてくださるのです。
<26~27節>
キリストはが苦しみを受けて栄光を受ける方であることは、旧約聖書の中でも、イエスご自身も、予告していました。旧約聖書ですでにイエスのことが預言されています。キリストの光を通して読むときに、旧約聖書も福音として、神の恵みの言葉として、私たちの心の中に入ってくるのです。
<28~31節>
ふたりの弟子は、イエスに一緒に泊まるように「無理に願い」ました。イエスから聞いたキリストに関する聖書の説き明かしをもっと聞きたいという強い求めと、日が暮れていたので旅人をもてなす必要を感じたのでしょう。
食卓で、普通は家の主人がする「パンを裂いて祝福する」行為を、あえてイエスがされました。その時に、ふたりの目が開かれます(神的受動態)。神が、彼らの目を開かれて、ずっと一緒にいた方が、イエスだとわかったのです。
「目が開かれ」の、「開かれ」は、「目をさえぎっていたもの、とらわれていたものが、すーっと取り去られた」という状態です。目が閉じられていた状態から、目が開かれて光が差し込んできたような状態です。みことばの戸が開く時に、光が差し込み悟りを与えるのと似ています(詩篇119:130)。
ふたりの目が開かれてイエスだとわかると、イエスの姿は見えなくなりました。イエスのからだは、すでに復活のからだです。イエスの復活の事実を知らせるために、特別見える形で現れてくださいましたが、もう彼らがわかったので、肉眼で見える必要はなくなったのです。
<32節>
イエスが見えなくなっても、ふたりの弟子たちの心の中には、熱い思いが残っていました。イエスが説き明かしてくださった聖書の真理を聞いていた時に、ずっと「心はうちに燃えていた」のです。主イエスが、ずっと聖書を説き明かしてくださっていたから、心があれほど熱く燃えたのだとわかりました。私たちは幸いなことに、今聖書を通していつでもイエスの説き明かしを聞くことができるのです。
イエスが道々ずっと説き明かしてくださった聖書のことばを通して、弟子たちの心は熱く燃やされました。悲しみとパニックで暗い顔つきをしていたクレオパたちですが、イエスの姿が見えなくなっても、イエスが語られた言葉によって、心は熱く燃やされていたのです。
イエスとの関係をさえぎり、みことばを心に入らせなくするものがあります。それらが、重く心にのしかかり、私たちの心を暗くします。でもさえぎっているものが取り除かれ、目が開かれて復活の主イエスを見る時に、そしてそのような主の言葉を聞く時に、私たちの暗い心は熱く燃やされます。
復活の主イエスは、エマオ途上の弟子たちといっしょに歩んで語りかけてくださったように、御国を目ざして旅を続ける私たちの同伴者となってくださっています。そして目には見えなくても、私たちの冷めた心を、みことばによって熱く燃やし続けてくださるのです。神の言葉が、私たちの喜びとなっていなければ、私たちは悩みの中で滅んでいたことでしょう(詩篇119:92)。悩んでいても、心が暗くなっても、聖書を読めばまた心が燃やされます。同伴者なる主は、今もみことばを通して私たちの心を燃やしてくださいます。毎日聖書を読みましょう。私たちの目をさえぎっているものを、聖霊に取り除いていただきましょう。みことばが、私の何よりもの喜びとなりますように!
|
 |
 7月1日 7月1日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「事実となるみことば」
ルカの福音書24:1~12 三浦真信牧師
<1節>
イエスの復活が「週の初めの日」であったことを、4福音書すべてが記しています。人類史上初めてのすばらしい出来事が起きたのです。イエスはすべての人の罪の身代わりに十字架で死なれましたが、それだけでしたら本当に罪が赦されるのか実感することができません。でも罪のとげである死にキリストが勝利してよみがえられたことで、キリストを信じる者たちも、罪と死に勝利することが明らかになったのです。この新しい出来事が、週の初めに起きます。そしてやがてキリスト教会は、主イエスが復活した週の初めである日曜日を安息日として礼拝するようになります。
イエスが墓に納められるのを見届けた女性たち(23:55)は、準備しておいた香料を持って墓に着きます。ギリシャ語原語では「その墓」となっています。アリマタヤのヨセフが自分のために買って用意していた、誰も葬ったことのない「その墓」です(マタイ27:59~60)。
その墓は、「岩に掘られた」(23:53)墓で、その中にイエスのからだを置き、大きくて丸い石(成人男性5~6人でようやく動せる重さ)で穴をふさいでいました。彼女たちは、墓に向かう途中で、その大きな石を転がしてくれる人がいるだろうかと話し合っていました(マルコ16:3)。「明け方早く」で、人がいるかもわかりませんでした。それでも彼女たちは引き返しませんでした。イエスの墓に一刻も早く行きたいという思いが強かったのでしょう。またイエスと共にこれまで歩んできて、何か不安なことがあっても、いつもイエスが何とかしてくださった奇跡を見てきたので、心のどこかに「神が何とかしてくださるから大丈夫」という思いが染みついていたのかもしれません。
<2~3節>
不安なまま墓に着いた彼女たちは、墓穴をふさいでいた「石がわきにころがしてあった」のを見て驚きます。ここの「ころがしてあった」の原語は「ころがされてあった」(受動態分詞形)になっていて、行為者がない受け身になっています。これは「神によってころがされてあった」ということです。そして墓の中に入ってみると、「主イエスのからだ」はありませんでした。
大きな墓石がころがされてあったのは、誰のためでしょうか?それは主イエスのためではあ りません。復活の主イエスは、石で墓がふさがれたままでも復活できましたし、外に行くこともできました。鍵を閉めて引きこもっていた弟子たちのいる部屋の中にも、復活の主イエスは現れています(ヨハネの福音書20:19)。墓石が転がされていたのは、香料を持って墓に来た彼女たちのためでした。彼女たちが墓の中に入って、イエスのからだがないことを目撃し、主イエスの復活の証人となるためでした。イエスが確かに復活して、今も生きておられることを証しする者と彼女たちがなるために、神は石をわきに転がされたのです。
神は、私たちが復活の主イエスと出会うために、この墓の大石のような障害物を取り除いてくださる時があります。女性たちが、障害となる墓石を取り除かれてお墓の中に招き入れられ、「主イエスの(死んだ)からだはなかった」という事実を見たように、主イエスが復活して今も生きておられる事実を、私たちにも見せてくださるのです。「これでもあなたは信じないのですか?」と、キリストが生きておられる事実を否定できないように、復活の主の元に私たちを招いてくださいます。
<4~8節>
墓の石が転がされ、イエスのからだがなかったことで、彼女たちは途方にくれました。「イエスのからだがないということは、イエスが復活したのだ」とわかっていれば、途方にくれることはなかったのです。むしろ喜ぶべきことでした。同じ出来事に遭遇しても、イエスの復活を信じるか否かで、喜びにもなり途方にくれることにもなるのです。環境は関係ありません。同じ環境でも、信仰に立つなら喜びとなり、復活のキリストを信じないなら途方にくれるしかないのです。彼女たちは、折角イエスのからだに香料を塗ろうとしてきたのに、それすらできないことで悲しくなりました。きっと誰かが石を転がして、イエスのからだを盗んだと思ったのでしょう。
途方にくれている彼女たちのところに、「まばゆいばかりの(原語は「稲妻のように明るい」)衣を着たふたりの人が近寄ってきます。この二人は「主の使い(御使い)」でした(マタイ28:2,4)。御使いは、「なぜ生きている方を死人の中で捜すのですか」と言います。ここの「生きている方」(現在能動分詞形)には、「死とは全く関係なく、永遠に生きておられる方」というニュアンスがあります。
イエスは、まだガリラヤにおられるころに、すでに弟子たちや彼女たちに、ご自身の十字架の死と復活のことを語っておられました(9:22,44)。それにもかかわらず、実際にその通りのことが起きたら、全く忘れてしまっていたのです。彼女たちは、御使いからそのことを聞いて、ようやく「イエスのみことば」を思い出しました。そして主が語られた通り、主イエスはよみがえられたことを理解したのです。ずっとイエスと一緒にいた彼女たちでさえ、主のことばを忘れていたのです。ですから主のみことばは、何度も繰り返し聞く必要があるのです。1回聞いて、頭でわかっただけではだめなのです。
<9~12節>
御使いのことばを聞いて、イエスがご自分で言われた通り死からよみがえられたことを知った彼女たちは、イエスの弟子たちに一部始終を報告しにいきます。もう途方にくれてはいません。感動と喜びに溢れて報告したことでしょう。彼女たちは、自分たちが見た事実を「報告した」のです。事実を報告することが、そのまま証しとなっていきました。
この女性たちの中で、マグダラのマリヤの名前は、4福音書すべてに記されています。7つの悪い霊によって苦しい人生を歩んできた彼女は、イエスによって悪霊を追い出され、解放されて自由になりました(8:2)。その彼女が復活のイエスに真っ先に出会っています(ヨハネ福音書20:11~18)。
このマグダラのマリヤはじめ複数の女性たちが、イエスの復活の出来事を弟子たちに報告しました。しかし弟子たちは彼女たちの話を「たわごと」(原語「レーロス」は医学用語で「精神錯乱状態者のうわごと」の意味)として信用しませんでした(11節) ペテロも信じてはいなかったようですが、気になったのか墓に走っていきました(12節)。そして墓の中に、イエスのからだを巻いたはずの「亜麻布」だけがあるのを見て、驚いて家に帰ります。
11節の「話」という言葉は、原語で「レーマ」が使われおり、8節の「みことば」と同じです。また1:37でイエスの母マリヤが「神にとって不可能なこと(出来事)は一つもありません」と言っている「出来事」も、同じ「レーマ」です。つまり、イエスが語られたことば(みことば)は、そのまま出来事(事実)となっていくのです。単なる話では終わらないのです。イエスが語られたことは、そのまま具体的な出来事となっていくのです。聖書のみことばを読むときに、そのことばがそのまま事実となるレーマなる言葉として受け取りましょう。主イエスが、十字架で死んで三日目によみがえると語られたら、その通りになったのです。主イエスは、確かに死からよみがえり、今もそして永遠に生きておられる方です。主が語られた言葉は、そのまま事実となります。みことばを読むときに、「今日私の上に、このみことば通りの事実が起きるのだ」と信じ期待して読みましょう。
|
 |
![]()
![]()
![]()