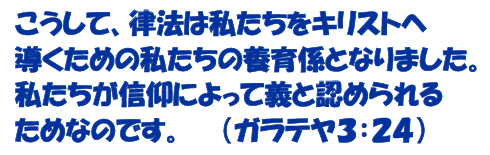10月28日 10月28日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「救いを得させる神の力」
ローマ人への手紙1:16〜17 三浦真信牧師
マルチン・ルターが1517年10月31日にヴィッテンベルク大学の城教会に「95か条の提題」を掲示したことが宗教改革のきっかけとなり、プロテスタントが誕生します。ルターはいつものように神学講義のための論題を掲示しただけですが、それが当時の印刷機の普及もあり、瞬く間にヨーロッパ中に広がっていきました。
直接のきっかけは、免罪符を買えば罪が赦されるという教えに抗議する内容でした。ルターは、キリストの十字架によらなければ人間の罪は赦されないことを強調し、またそのような教えを人々が鵜呑みにしてしまうことの問題も感じ、聖書に立ち返ることを訴えました(使徒17:11)。
その影響を受け、チューリッヒではツヴィングリが「聖書のみ」の原則を伝えました。特に当時レント期間中に肉を食べることを禁じていたことの是非を巡って、「聖書が明らかに命じ禁じること以外、何もキリスト者を拘束しない」と主張しました。ジュネーブでは、27歳のフランス人カルバンが、ジュネーブが神の言葉の支配する社会となることを理想とし、聖書の言葉に従うことの大切さを訴えます。
宗教改革者たちは、人ではなくキリストが崇められるべきこと、人の声ではなく神の言葉である聖書にたえず聞いていくこと、そして万人祭司としてすべてのクリスチャンが神と人を仲介する祭司の役を担っていることを大切にし伝えました。いつの時代もカリスマ的な人物が登場し、また現代は今まで以上に情報が溢れていますが、だからこそたえず神の言葉に聞き従い、キリストを崇めましょう。
また宗教改革者たちが大切にした「信仰のみ」の原則を、ローマ人への手紙の続きから受け取りましょう。
<16節>
パウロは、まだ訪れたことのないローマにおいて、「ぜひ福音を伝えたい」と願っていました(15節)。その理由は、「私(パウロ)は福音を恥とは思わない」からです(16節最初に「なぜなら」が原文には入っています)。そしてその後にも、「なぜなら」が原文には入っています。なぜ福音を恥とは思わないかというと、「福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力」だからです。福音が、まずイエスを通してユダヤ人に伝えられ、そして使徒たちによってギリシャ人またあらゆる民族に宣べ伝えられていきます。その福音は、民俗地域を超えて「信じるすべての人にとって救いを得させる神の力」なのです。
この「神の力」の「力(デュナミス)」から、「ダイナマイト、ダイナミック、ダイナモ(発電機)」という言葉が派生していきました。福音によって自我と罪が打ち砕かれ、霊的に新しくされ、ダイナミックな生き方ができるのです。パウロ自身が、福音を伝える中でそのことを経験し続けていました。私たちは、救われた後は天国に行くまでじっと地上の待合室で待っているわけではありません。万人祭司として福音を伝える中で、神のデュナミスの力を体験することができるのです。神の国がこの地に広がっていく喜びを兄弟姉妹と共に味わい続けることができるのです。
パウロは、かつては福音を恥としていました。だから教会を迫害しました。しかし死からよみがえられたキリストに出会って、福音の力を自分自身が知り、恥とするどころか福音を誇る者となりました。私たちも、「信じるすべての人にとって救いを得させる神の力」である福音のダイナミックな力を体験させていただくように祈り求めましょう。
<17節>
ルターは、落雷の中で死の恐怖に怯え、献身の誓いをしてそれまでの法律の学びを捨てて修道院に入りました。そのころ教会では、「救いのためには神の恵みだけでは不十分で、それに加えて人間の善行が必要である」と教えられていました。「救いに必要な量の善行が功績として神に受け入れられた時に、罪人に対して怒る義の神は、恵み深い神になる」と教えられていたのです。「いかにしたら私は恵み深い神を私のものに…」と始められたルターの修業は失敗の連続でした。修道院で難行苦行をしても、いよいよ罪深い自分の惨めさが明らかにされるばかりで、恵みの神の片鱗すら発見できません。
そのようなルターが迷路から抜け出すきっかけとなったのは、先輩から勧められた聖書の学びでした。ルターは熱心に聖書を学び、1512年に聖書学で博士号を受け、翌年からヴィッテンベルク大学で詩篇、ローマ書、へブル書、ガラテヤ書を次々と講義しました。そのための深い聖書研究の中で、ルターは少しずつ福音を理解していきます。そしてローマ人への手紙1:17「福音のうちには神の義が啓示されていて…」の「神の義」の真意を見出します。従来ここは「神が義であり、それにより罪人を裁く義」と理解されていましたが、ルターはここを「神が、不義である罪人を義と認める義」と理解しました。それはルターの勝手な解釈ではなく、聖書全体を学んでいく中でわかってきたことです。神が、罪しか出てこない不義なる者を、恵みによって義と認めてくださることを受け取ったのです。神が遣わされたキリストを信じる信仰によって義と認めてくださる恵み深い神だとわかった時に、ルターの人生は変わりました。
「その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです」の別訳として「その義はただ信仰による」があります(脚注)。「信仰に始まり信仰に進ませる」は、「神が罪深い私たちを義(正しい)と認めてくださるのは、ただ信仰による」ことを強調する表現です。善行や修行によっては決して神の義は得られません。人間の力では決して得られないのです。キリストを信じることによってのみ、人は神に義と認められるのです(信仰義認)。
「義人は信仰によって生きる」は、ハバクク2:4の引用で、ガラテヤ3:11でも引用されています。律法の行いによっては、だれも神の前に義と認められないのです。むしろ神の律法の前に、いよいよ不義である自分を認めざるを得ないのです。いよいよ罪しか自分の中には見出すことができず、キリストの元に行くしか救いはないのです。それでよいのです。律法は私たちをキリストの元に導くための養育係です(ガラテヤ3:24~26)。律法によって、本来救われえない罪人を救ってくださるキリストにいよいよ結びつけられていきます。罪がわからなければ、キリストの恵みもわかりません。ですから、罪を示す律法は大切なのです。いかに神から外れている者かを知れば知るほど、キリストの恵みの大きさを知り感謝が溢れてくるのです(ローマ5:20)。
人間の罪は、お金を出して免罪符を買うくらいで赦されるものではありません。神の子が十字架で死ななければならないほどの罪です。キリストが、この罪の借金の重荷を肩代わりして取り去ってくださったのです。聖書が示すこの信仰に立ち続けましょう。不義なる私たちが義とされるのは、ただ信仰によってのみです。ですから私たちの側には何の誇りもありません。福音(キリスト)だけが誇りです。キリストを遣わしてくださった神への感謝があるだけです。
|
 |
 10月21日 10月21日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「福音を伝える動機」
ローマ人への手紙1:13後半〜15 三浦真信牧師
<13節>
パウロは、「ほかの国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って」何度もローマに行こうとしましたが、妨げられてまだ行くことができないでいました。だれでも願っていたこと、計画していたことが閉ざされたら、がっかりするでしょう。パウロもローマ行きだけではなく、これまでも道が閉ざされ計画していたこととは違う方向に道が開かれていく経験をしています。第2回伝道旅行でも聖霊に禁じられて、計画していた場所には行けず別の場所に導かれていく経験をしています(使徒16:6~10)。でもその導きについて行った結果、マケドニヤ地方に導かれ、初代教会において大切な役割を果たす群れがそこに起こされていきました。数々の神様の力あるみわざをそこで見ることができたのです。
またパウロは、迫害のために何度も牢に入れられたり、むち打たれたり、難船して海の上を一昼夜漂ったり、盗賊にあったり、偽クリスチャンに会って騙されたり、飢えや寒さで眠れない夜があったり、様々な艱難(かんなん)に会いました(Ⅱコリント11:23~30)。神がパウロを異邦人伝道のために召されました。そしてその働きのために労しているのに、次々に艱難(かんなん)が起き、道が閉ざされ、思うようにいかないことばかりです。しかも伝道のためにつまずきとなりかねないパウロの肉体のとげ(弱さ)を取り除いていただきたいと何度も祈りましたが、「わたしの恵みは十分である」と神は言われ、取り去ってはくださいませんでした(Ⅱコリント12:7~9)。神のみこころだからといって、何でも上手くいくわけではありません。むしろ神のみこころだからこそ、神に頼らずにはいられないような出来事が次々に起きてくるのです。神のみこころと受け取って進んだ学校、会社であっても、思うようにいかないことや試練が起きてきます。みこころの人と受け取って結婚しても、夫婦関係に困難を感じたり難しい問題が家庭に起きてきたりします。神のみこころだからこそ、信仰の訓練として試練がやってくるのです。神が私たちに与えたいのは、人生の成功ではなく、どのような状況でも神を信頼していく信仰です。
内村鑑三は、「聖書が一番よくわかる注解書は、人生の苦難である」と言いました。願っていた道が閉ざされる経験、苦しみ悲しみ痛みの経験が、一番の聖書の注解なのです。試練の中でこそ、今まで見えなかった真理に気づき、聖書の奥義を理解し、キリストの復活の力を体験します。
パウロも自分の計画通りにいかないことで、神がなさることが最善であることを学び、いよいよ神への信頼が深まりました。ローマ行きが延長されることで、さらに別の地域にも福音を語る機会が与えられ、神の素晴らしいみわざを見ることになります。ですから、自分の計画通りにならないことがあっても大丈夫です。願っていた道が閉ざされても大丈夫です。その時こそ、神のみを信頼する時です。
<14~15節>
パウロの熱い伝道の思いがどこからきているかがここに記されています。それは、あらゆる人たちに「返さなければならない負債を負っている」とパウロ自身が感じていることです。ギリシャ人(へレニズム文化の影響下にある人たちの総称)にも未開人(ユダヤ人などへレニズム文化の外にいる人たち)にも、知識のある人にもない人にも、あらゆる地域のあらゆるタイプの人に対して、福音を伝える責任をパウロは負っていると自覚しているのです。それは、キリストの計り知れない愛に対する負債です。負債と言っても、決してそれはパウロにとって重荷ではありませんでした。なぜなら、彼はキリストにあって、誰に対しても自由だったからです(Ⅰコリント9:19)。パウロはキリストにあるとてつもない自由と解放を味わっていました(ガラテヤ5:1)。このキリストが与えてくださった自由により、パウロは神に仕えました。ですから他の人にキリストを伝えるためなら、喜んですべての人の奴隷となることができました(Ⅰコリント9:19)。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法を持たない異邦人には異邦人のように、弱い人々には弱い者のようになりました。それは何とかして幾人かでも救うためです(Ⅰコリント9:20~23)。福音のためなら、どのタイプの人の目線に立つことも仕えることもできたのです。
キリストの十字架の苦難と犠牲により、私たちは返しきれない罪の借金を帳消しにされました。神からいただいた恵みの大きさと、神の子がそのために払われた犠牲を思うなら、感謝とともに、とてつもない借りを作ったような感覚になるのです。到底その借りを返すことはできないのですが、それでも神が望んでおられることをすることで、少しでも借りを返したい、少しでもこの福音を伝えるために役立つことをしたいという願いが、伝道の動機となるのです。罪の借金をキリストの十字架により帳消しにされた(コロサイ2:14)感謝が、「返さなければならない負債を負っている」という思いとなりました。パウロにとって福音を伝えることは、どうしてもしなければならないことなのです(Ⅰコリント9:16)。キリストを通して示された神の愛への応答として、福音を伝えずにはいられないのです。そのためにパウロは今、ローマに行くことを切望しています。
キリストがいのちを捨てて、滅びに向かっていた私たちを救い出してくださいました。その方が、一人でも滅びることなく救われてほしいと願い(Ⅱペテロ3:9)、また足りない私たちを通して福音を伝えてほしいと願っておられるのですから(Ⅱコリント5:20)、私たちもすべてのことを福音のためにしましょう。いのちの恩人であるキリストの思いを受け取りましょう。
|
 |
 10月14日 10月14日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「福音の実」
ローマ人への手紙1:13(前半) 三浦真信牧師
<13節>
パウロはローマ訪問を切に望んでいましたが、まだ実現できないでいました。その理由の一つに、ローマ皇帝クラウデオによるローマからのユダヤ人追放令(使徒18:2)による影響が考えられます。
パウロがローマ訪問を切望する理由の二つが11~12節に記されていますが、13節で三つ目の理由が記されています。そしてその理由が一番重要であることが、13節の表現からもわかります(原語では「わたしはこのことをあなたがたに知らないでいることを欲しない、兄弟たち」となっています)。それは、「ほかの国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得たい」という理由です。
ここでいう「実」というのは、福音の種がまかれて実を結ぶことです。その福音を信じて人々が救われ、「永遠のいのちに入れられる実を集める」ことです(ヨハネ福音書4:36)。福音の実は、すでに世界中で実を結び広がり続けています(コロサイ1:6)。事実パウロがこの手紙を書いている時点でも、すでにコリント、ピリピ、テサロニケなど、至る所で福音の実は結ばれ、信じる者たちの群れができていました。ですから、決してローマだけが特別というわけではなく、「ほかの国の人々の中で得たと同じように」ローマでも、「いくらかの実を得ようと思って」パウロはローマ行きを何度も計画しました。すでに信じる者たちの群れができていたローマですが、パウロが行くことでさらに救われる者たちが起きてほしいと願ったのです。
パウロも、またイエスの弟子たちも、実を結ぶために主イエスに選ばれました。そのためにイエスの名によって神に求めるなら、何でも与えてくださると約束しています(ヨハネ福音書15:16)。パウロは特に、異邦人伝道のために主イエスから召されました。かつてパウロはキリストを迫害していましたが、その最中で復活のキリストに出会い、人生を変えられます。そして今度は自分が迫害していたイエス・キリストを宣べ伝える人になりました。その使命を主イエスから与えられたのです。そのために国々を巡っていました。ローマでも同じようにキリストを伝え、キリストを通して与えられる素晴らしい救いを一人でも多くの人に受け取ってほしいと願ったのです。
パウロは、迫害のために獄中にいた時に「私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です」と告白し、「この肉体のいのちが続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになる」ので感謝だと言います。死ぬなら「世を去ってキリストともにいること」になるので、それも感謝だと言っています(ピリピ1:20~24)。パウロにとって、自分の働きを通して福音の実を結ぶことが生きる目的でした。ですから、当時は迫害下で苦難の中でしたが、生きることも感謝でした。死ぬことも、キリストによって死が恐怖ではなく希望と変えられているので感謝でした。生きるのも死ぬのも、キリストにあっては感謝なのです。パウロは、最後の最後まで「福音の実」を得たい、そのためならなお生かされたいと牢獄の中でも思っていました。
パウロがローマ行きを切望する一番の理由は、「いくらかの実を得たい」からでした。実際には、パウロを通して多くの実を結びましたが、パウロ自身としては「自分がローマに行くことでいくらかの実を得られれば感謝、一人でも救われればいい、いや直接その救いの実を見ることができなくてもいつか実を結ぶなら感謝だ」という思いだったのです。
私たちは、「福音の実をいくらかでも得よう」として生きているでしょうか?もしも「パウロは伝道者だから特別でしょう」とするなら、それは聖書を他人事のように読んでいることになります。パウロは、この福音の実を結ぶことに対する熱い思いを、すべての人に共有してほしいと願って、実を結ぶことの大切さを繰り返し伝えています。クリスチャン一人ひとりが、「実を得ようとして」生きることを願っています。「私のこの身を通して、福音の実が成ってほしい」と願い求めながら生きてほしいと願っています。
神ご自身も、福音を伝えるため、また実を結ぶために私たち一人ひとりを選ばれました。神が私たちを選ばれた目的を忘れて生きる時に、当然すべてが空回りし空しくなります。何のために今生かされているのかを、主からしっかり受け取りましょう。「キリストがすべての人のために死なれたのは、生きる人々が、もはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです」(Ⅱコリント5:15)。
「このようにして労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が『受けるより与えるほうが幸いである』と言われたみことばを思い出すべきこと…」使徒20:35)と、主イエスが言われた通り、「与える」人は、それに上回る幸いを与えられるのです。神から与えられたものを人々に分かち合い、福音の実を得るために仕えましょう。
|
 |
 10月7日 10月7日 |
聖日礼拝メッセージ要約 主題:「共に励ましを受ける交わり」
ローマ人への手紙1:8~12 三浦真信牧師
<8節>
パウロは、ローマのクリスチャンのことで神に感謝していることを伝えます。その神を「私の神」と呼んでいます。この表現から、いかにパウロが神と親しい関係にあるかがわかります。キリストが私たちの罪をきよめてくださったので、今大胆にキリストの御名によって「私の神」と呼ぶことができるのです。
パウロが神に感謝していることは、ローマのクリスチャンたちの「信仰が全世界に言い伝えられている」ことでした。パウロはローマを訪れたことがありません。これから初めて訪問するために、この手紙を書いています。それでもすでにローマにはクリスチャンの共同体がいくつもありました。ペンテコステ(聖霊降臨日)の日にローマの人々がエルサレムにいて、そこで神の大きなみわざを見ています(使徒2:10)。そこで救われた人たちがローマに帰って福音を伝えたのでしょう。またパウロが伝道旅行で訪問した地域に教会ができ、そこで救われた人たちがローマの人たちと交流する中で信仰を持つ人たちが起こされたこともあったでしょう。
福音は一ヶ所に留まらず広がっていくものです。エルサレムから福音が広がり、ローマ帝国の中心であるローマに信じる者たちが起こされ、また今度はローマから「全世界(地中海沿岸のローマ帝国全土)」に福音が伝えられていきました。「すべての道はローマに通じる」という諺(ことわざ)のように、ヨーロッパ各地から道路が整備されて通じていたことも用いられたのです。パウロは、このようにローマの信徒たちが信じるキリストの福音が、また全地に広がっていることを神に感謝しました。
<9~10節>
9節の原文を直訳すると、「神が私の証人です。その神に私はわが霊をもって御子の福音において仕えているのです」となります。パウロがこの後、「あなたがたのことを思わぬ時はなく、いつも祈りのたびごとにあなたがたのところに行けるように願っている」と伝えます。ローマの人たちが、「まだ一度も会ったことのないパウロが、本当にそこまで思ってくれているのだろうか」と疑うかもしれないので、「神が、私の思い願いが真実であることの証人です」と強調しているのです。ただここでも、「神が私の証人です」で終わってもよいのに、パウロは隙(すき)あらば神との関係について伝えようとしていて、「その神に、私は心から仕えているのです。神の子キリストの福音を伝えることで仕えています」と記しています。「神の福音のために使徒として召されたキリストのしもべ」パウロ(1節)、「キリストによって恵みと使徒の務めを受けた」パウロであることを、繰り返しローマの信徒たちに伝えています。どこまでも神が一方的にパウロを、キリストの福音を伝えるために使徒として召されたのです。
パウロの心には、いつもローマ訪問の願いがありました。とりなして祈っている人には、自然に会いたいという願いが生まれます。会って、神がどのようにその人に働いておられるかを直に見たいと思われるのです。でもその願いはあっても、「神のみこころ」によらなければ、実際に会うことができないのです。
事実パウロはローマ行きを切望してきましたが、なかなか実現しませんでした。このローマ人への手紙を第3回伝道旅行中コリント滞在中に書いた(紀元58年前後)あとに、パウロはエルサレムによって(エルサレムを支援するために集めた献金を渡すため)、その後ローマを訪問する計画でいました。しかしエルサレムでユダヤ人たちの迫害に会い暴動になり、パウロはカイザリヤに連行され、囚人として2年間そこで幽閉されます。神のみこころの時でなければ、どれほど願っていても行くことができないのです。エルサレムの暴動の最中で、「勇気を出しなさい。あなたはエルサレムでわたしのことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない」(使徒23:11)と神から語られました。その神の約束を信じて、パウロは神の時を待ち望みました。そしてカイザリヤでの幽閉生活の後、囚人としてローマに行くことになります。しかも囚人であったため、兵士たちに護衛されて一番安全な方法で、ローマに行くことができたのです。またその途中にも、数々の神のみわざを経験し、福音を伝える機会がありました。神のご計画と、私たちの思いは異なります。神の道は高く、神の思いは私たちの思いよりも高いのです(イザヤ 55:7b~9)。
<11~12節>
パウロが、なぜローマの信徒たちに会うことをそこまで切望しているのでしょうか?
① パウロに与えられている御霊の賜物を少しでもローマの信徒たちに分け与えて、彼らを力づけたいから。
様々な「御霊の賜物」があります。パウロの場合は、福音に対する明確な理解、聖書知識が御霊の賜物として与えられていました。また聖霊に満ち溢れ、神の愛と力が豊かに注がれていました。それによってローマの信徒たちを励まし強めたいと願っていたのです。
御霊の賜物は、人それぞれ異なったものが与えられています。その異なった賜物が組み合わされて教会は成長していきます。技術的な能力、財力、時間、あまり苦にならない仕事、苦しみ痛んだ経験(病気、家庭問題、いじめ、死別、喪失、被災経験…)なども賜物です。
与えられた賜物は、神と人のために用いるために与えられているのです。そのように用いていく時に、さらにその賜物が生かされていくのです。「自分なんかが行っても何にもならないだろう」と言ってとどまっていたら、託された1タラントを地中に埋めてしまった人のように、「不忠実なしもべよ」と主人から叱られ取り上げられてしまいます(マタイ25:25~29)。与えられているものが明確にはわからなくても、「主がお入り用なのです」(マルコ11:3)と言われた時には、主が遣わされたところに出ていきましょう。主のために、誰かのために、仕えましょう。主がそれぞれに与えておられる賜物を用いてくださいます。
パウロは、「御霊の賜物をいくらかでも」と、たとえわずかであったとしても、分け与えることでローマの信徒たちが強められることを願って、ローマ訪問を切望していました。
② 共に励ましを受けたいから。
パウロがローマ訪問を切に願っているもう一つの理由は、パウロが御霊の賜物を一方的に分け与えるだけでなく、パウロ自身もローマのクリスチャンたちとの交わりを通して励ましを受けたいからでした。「互いの信仰」によって、互いに益を与えることができるのです。どちらか一方だけが与えて終わることはありません。信仰の出来事は、みな「give&take」です。病の人を訪ねる時も、訪問した人もされた人も恵みを受けます。神が喜んでおられるからです。交わりで、誰かが一方的に教えて、誰かは教えられるだけということもありません。必ず両者ともに教え、教えられることがあります。キリストのことばをしっかり内に住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め合うのがキリストにある交わりです(コロサイ3:16)。
パウロが直接には福音を伝えていないローマにも福音が広がり、信徒の群れができていました。そしてその福音はローマからまた地中海沿岸諸国に、そしてやがては世界中に広がっていきます。パウロは、ローマ行きを切望していましたが、なかなか道が開かれていきませんでした。しかしやがて神の御心の時に実現します。
パウロがこれほどまでにローマ行きを願った理由は、パウロに神が与えてくださった御霊の賜物を分け与えて信徒たちを強めたいこと、そして互いの信仰によってパウロ自身も励ましを受けるためでした。私たちも、主から遣わされた時には、人と比べて「自分なんかが行っても何にもならない」などと言って与えられたものを地中に埋めてしまわず、「主が与えてくださったものをいくらかでも分け与えて力づけられれば嬉しい」「私も遣わされることで主の恵みを受けたい」という思いで、遣わされましょう。
「このようにして労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が『受けるより与えるほうが幸いである』と言われたみことばを思い出すべきこと…」使徒20:35)と、主イエスが言われた通り、「与える」人は、それに上回る幸いを与えられるのです。
|
 |
![]()
![]()
![]()